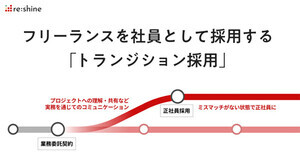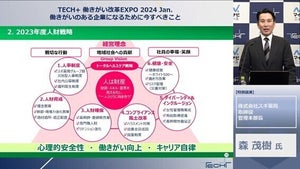人材獲得競争が激化する中で、企業文化にフィットした人材を採用するには、従来の求人広告や人材紹介といった手法だけでは限界があります。そこで近年注目されているのが、社員のネットワークを活用した“巻き込み型”の採用戦略です。
本稿では、現役社員による紹介制度である「リファラル採用」と、退職した元社員とのつながりを活かす「アルムナイ採用」に焦点を当て、それぞれの実践事例を交えながら、その可能性や効果、導入・運用時の留意点について解説します。
リファラル採用の可能性と成功の鍵
リファラル採用とは、社員が自らの知人や元同僚など信頼できる人物を企業に紹介し、採用につなげる手法です。社員のネットワークを活用することで、企業文化にマッチする人材と出会いやすいだけでなく、採用のミスマッチを抑え、結果として定着率の向上にもつながります。
ただし、制度を形だけ導入しても、期待した効果は得られません。単に「紹介してください」と一方的に呼びかけたり、「1人紹介ごとに報酬〇万円を支給します」とインセンティブだけで動機付けしようとしたりしても、制度がうまく運用されず、形骸化してしまうケースも見られます。
リファラル採用を活性化させるには、社員が“紹介したくなる”心理的ハードルの低さと、制度を日常的に意識できる社内環境の両面を整えることが鍵です。
たとえば、あるIT企業では、社員に毎月1回「リファラル候補者アンケート」を送付しています。アンケートといっても堅苦しいものではなく、気軽に名前だけでも記入してもらえるようなフォーマットを採用して運用しています。たとえその時点で応募につながらなくても、会社側から候補者に情報を届け続けることで、数カ月後に応募という形で実を結ぶこともあります。
また、社内報や社内SNSなどで紹介制度の成果を積極的に可視化し、「紹介で入社した◯◯さんがどのように活躍しているか」といった情報を共有することで、制度に対するポジティブな認知を社内に醸成しています。
重要なのは、「使いやすくすること」と「使いたくなる文化をつくること」。この両輪が揃ってこそ、リファラル採用は一時的な取り組みに終わらず、持続的に機能する強力な採用チャネルとなるのです。
アルムナイ採用の効果と関係構築
一方、近年注目されているのが退職者(アルムナイ)との関係を活用する「アルムナイ採用」です。これは、単なる再雇用にとどまらず、元社員が新たな人材を紹介するケースや、業務提携・協業など、新たな関係性を築く事例も増えています。
アルムナイ採用の最大の強みは、企業文化や業務の理解度が高い即戦力人材を確保できる点です。入社時のオンボーディングがスムーズで、再雇用時のカルチャーフィットに関する不安も起こりにくいのが特徴です。
さらに、「また戻りたいと思える会社」であるというイメージを醸成することは、現役社員のロイヤルティやエンゲージメントの向上にも寄与します。 ただし、アルムナイとの関係は、退職後に自然と維持されるものではありません。退職時の丁寧な対応や、その後の継続的なコミュニケーション設計が重要な鍵となります。
私自身がかつて在籍していたリクルートでは、卒業生らを「元リク」と呼び、再雇用・出戻りを歓迎する企業風土が根付いていました。また、アルムナイ同士のネットワークやコミュニティが存在し、情報交換や新たなビジネスのきっかけが生まれる場として機能していました。
あるメーカーでは年2回、アルムナイを招いたイベントを開催。会社のビジョンや業績報告、新たなサービスの紹介といった情報提供に加え、現役社員との懇談の場を設けることで、アルムナイが「会社の今」を知る機会になっています。こうした接点づくりは再雇用にとどまらず、新たな事業創出やブランド価値の強化にもつながっています。
採用とインナーブランディングの連携で文化を醸成
リファラル採用・アルムナイ採用のどちらにおいても、本質は「人が人を呼ぶ」文化や仕組みをいかに構築するかにあります。
その文化形成には、社員一人ひとりが企業に対してどれだけ誇りや愛着を持っているかという、インナーブランディング(社内広報)の力が深く関わっています。
自社の理念や価値観に共感し「この会社で働くことに誇りを持てる」社員が増えることが、紹介制度や再雇用といった文化を根付かせる土台となります。つまり、採用戦略とインナーブランディングは、表裏一体の関係にあるのです。
実際に、社員インタビューを定期的に社外に発信している企業では「あのインタビュー記事を読んで共感し、応募を決めた」という声が増えているといいます。現場社員のリアルな言葉こそが、企業の信頼性や魅力を伝える、有用なコンテンツになり得るのです。
実践事例にみる工夫と効果
以下に、実際にリファラル・アルムナイの制度を積極的に取り入れている企業の取り組みをいくつか紹介します。
リファラル事例
社内SNSで紹介文化を醸成
Slackや社内チャットに「◯◯部門でこんな人材を探しています。心当たりがあれば教えてください」といった投稿を日常的に実施。紹介が特別な行為ではなく、日常的な行動として根づいている。紹介者の想いを可視化する発信
紹介した社員にもインタビューを行い、「なぜこの人を紹介したか」「どんな仕事を一緒にしたいか」など、紹介者の想いを社内記事として発信。紹介の背景が共有されることで、チーム間の信頼関係や社内のつながりも深まる。
アルムナイ事例
LINEオープンチャットで情報共有
退職者専用のオープンチャットを運用し、会社の最新情報を定期的に発信。復職や紹介希望者が気軽に相談できる場としても活用されている。オンボーディングに紹介者を巻き込む工夫
「◯◯さんの紹介で入社されました」と社内に共有し、紹介者と新入社員をつなげることで心理的安心感を醸成し、入社初期の定着にも貢献している。
これからの採用に求められる「共創型」戦略
リファラル採用もアルムナイ採用も、単なる採用チャネルではありません。そこには「人を信頼し、関係を育てる」企業姿勢が表れます。
社員や元社員が「誰かに紹介したくなる」「また戻ってきたくなる」─ そんな企業は、採用力だけでなく、組織としての信頼性や魅力も自然と高まっていきます。人事部門だけに採用を委ねる時代は終わりを迎えつつあります。
今後は、全社員を巻き込んだ「共創型」採用戦略が、新たなスタンダードになっていくでしょう。リファラル・アルムナイの活用は多くの企業が本気で取り組む価値のある領域です。
採用を「企業と人との関係構築」と捉え直し、人とのつながりを大切にする企業姿勢こそが、組織全体の持続可能な成長を支える土台となり、未来を切り拓く力になるのです。