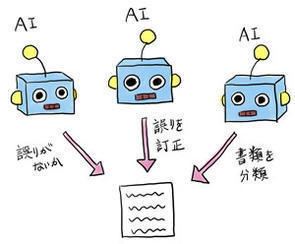2022年11月のChatGPT登場から始まった生成AIムーブメント。最近になってようやくトレンドが一周した感がありましたが、2024年にまた新たに大きな話題がやってきました。AIの話題に関して唯一沈黙を保っていたビッグテック、Appleの参入です。
Apple参入により、生成AIを取り巻く状況はどう変わるのか。今回は、進化し続ける生成AIの現状と課題、そして今後について見ていきたいと思います。
激化する生成AIの開発競争
まずは簡単に生成AIについておさらいしておきましょう。
生成AIとはAIの一種であり、文章や画像、動画、音楽といったさまざまなコンテンツを「生成」できるAIです。ChatGPTの登場が衝撃的だったため最近誕生したAIだと思われがちですが、実際にはもっと以前から存在していました。ただ、現在の生成AIほどの精度が出せなかったため、一般ユーザーからは注目されていなかったのです。
そんな生成AIがブレイクするきっかけとなったのはやはりChatGPTです。米OpenAIが2022年11月に発表し、その高い応答精度とチャット形式を採用したキャッチーなインタフェースによって世界中で大ブームを巻き起こしました。当初のChatGPTはテキストで指示を与えてテキストを生成させることしかできませんでしたが、現在ではOpenAIが開発した画像生成AI「DALL·E 3」との統合によって画像を生成したり、ExcelやPDFのファイルを読み取らせてさまざまなコンテンツを生成したり、ユーザーがGPTをカスタマイズできるGPTs機能が実装されたりと、できることが拡大しています。
進化しているのはChatGPTだけではありません。Googleからは「Gemini」、Facebookを運営するMetaからは「Meta AI」、Anthropicからは「Claude 3」といった生成AIが続々登場し、しのぎを削っています。これらがわずか1年半の間に起きた出来事なのですから、いかに生成AIの開発競争が激化しているかがうかがい知れます。
一歩先を行く米国
こうした生成AIの開発競争の中心となっているのは米国です。前述した生成AIはいずれも米国製であり、現時点では他国にライバルと呼べる生成AIは存在しません。むろん、米国以外の国々が生成AIの研究や開発を行っていないわけではありませんが、どうしても米国のスピードや規模感には追いつけていないのです。
その理由は、生成AIの性能を決める大きな要因が「物量」だからです。生成AIは「大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)」と呼ばれるAIモデルを搭載しており、このLLMの性能を決める要素の1つがデータセンターやGPUといった計算資源です。計算資源を増やすにはコストがかかるため、米国の大規模なIT企業が有利になるというわけです。
ちなみに計算資源によって増やせる生成AIの性能は、AIモデルの「パラメータ数」で表せます。2020年に開発されたGPT-3.5のパラメータ数は推定ですが355B(ビリオン)といわれており、これは2019年の生成AIの3500倍のボリュームです。そこから2年たった現在はおそらくもっと加速度的にパラメータ数が増えていることでしょう。生成AIの開発競争は留まることを知らず、今後も拡大し続けていくと思われます。
進まない生成AI活用の現状とApple参入の衝撃
一方で、開発競争ほど進んでいないのが肝心の「生成AI活用」です。ChatGPTが登場した当初こそ人々は熱狂し、2023年はまさに生成AI一色といえる状況でした。しかし、どんなに素晴らしい技術も、生活に根ざした使い道が生まれなければいずれ廃れてしまいます。これは、過去に何度も起きては消えていったAIブームが物語っています。
実際のところ、生成AIの活用は初期の予想ほど進んでいるとはいえません。話しかければ答えてくれるし、絵も音楽も作り出せる。でも、それをどう使えばいいのか。さまざまな企業が業務やビジネスでの生成AI活用を模索していますが、今のところ「多少便利なFAQ」か「プログラミングのコード生成」くらいしか有用な活用方法が見いだせていないのが現状なのです。
そんな状況に一石を投じたのがAppleです。
2024年6月、Appleは開発者向けのイベント「WWDC24」にて独自の人工知能「Apple Intelligence」を発表しました。Apple Intelligenceの特徴は、一般的な生成AIのようにブラウザやアプリからアクセスするのではなく、OSレベルで組み込まれていることです。
例えば文章作成で生成AIを活用する場合、これまでは文章作成ソフトを開き、文章を入力。その途中で生成AIに作ってほしい箇所については別途、ブラウザなどで生成AIを開き、プロンプト(生成AIに指示を出す文章)で指示して作成。そこで生成された文章を再び文章作成ソフトに貼り付けるーーといった手順が必要でした。
しかし、Apple IntelligenceはOSに組み込まれているため、いちいち生成AIツールを別に開く必要がありません。文章作成ソフトで文章を入力しながら、その中でAIが文章を自動作成したり、校正したり、要約したりしてくれるのです。
また、通知機能にもApple Intelligenceは組み込まれています。これまではさまざまな通知が届いた順番で表示されていましたが、Apple Intelligenceは通知の内容から緊急性を判断し、優先度の高い順番に表示してくれます。もし、これを一般的な生成AIにやらせようとしたら、別途ブラウザなどで開いた生成AIに通知の内容をプロンプトで提示し、「どれが優先度が高い?」と聞く必要があります。もちろん、そんなことをするなら自分で判断すればいいだけなので、まったく無駄な作業ですが……。
このように、OSレベルで組み込まれたApple Intelligenceは、これまでの一般的な生成AIとはまるで違う使い勝手を提供してくれることが期待できます。これこそが生成AI活用の1つの答えだと私は感じています。
「OSレベルでAIを組み込む」ことの意義
ちなみに、WWDC24でAppleがApple Intelligenceを発表した際、Appleの株価は一瞬大きく下がりました。これは、Apple Intelligenceの機能の1つである「質問に対して回答する」部分にChatGPTを採用したことが原因でしょう。Apple Intelligenceと聞いて、Apple独自の生成AIを期待していた投資家が「なんだ、ChatGPTなのか」とがっかりしたのだと思います。
一度は下がったApple株ですが、翌日には再び上昇しました。これは、少し時間を置いたことで、「OSレベルでAIを組み込む」ことの新規性と可能性に投資家が気づいたからではないでしょうか。実際のところ、Apple Intelligenceは、初めてiPhoneが発表されたときのように「珍しいものではなくなった技術を再定義し、本当の意味で世の中に浸透させる」というAppleの本領が存分に発揮された提案だったと思います。
今回のAppleの提案が、今後の生成AI活用における1つのターニングポイントになると私は見ています。一方で、かねてから指摘されている生成AIの課題に関してはまだ完全に解決できたわけではありません。その課題とは「セキュリティ」、「自社データの活用」、「ハルシネーション」の3点です。
次回はこの3つの課題について詳しく紹介するとともに、解決策に関しても解説します。
AI関連の注目ホワイトペーパー
自動車とその業界を取り巻く環境の変化に、製造ラインはどのようにキャッチアップすべきか?エッジAIはマイコンで。エッジAI処理、セキュリティ、低消費電力―すべてを高いレベルで実現するマイコンの実力
自己学習型AIによるセキュリティ対策がもたらす強みとは? 脅威の予兆を自動識別、攻撃をピンポイントで自動遮断
AI関連のオススメ記事
LLMとは? 生成AIとの違いや企業の活用事例を解説機械学習とディープラーニングの違いを徹底解説
AIと機械学習の違いを理解して、業務効率化や新規事業創出に役立てよう
ローカルLLMのメリット/デメリット、“使いどころ”を分かりやすく解説
AI活用でビジネス変革を実現するには? 押さえておきたい基本と活用事例
AIエージェントの基本を知る - ビジネス活用の可能性と課題とは?