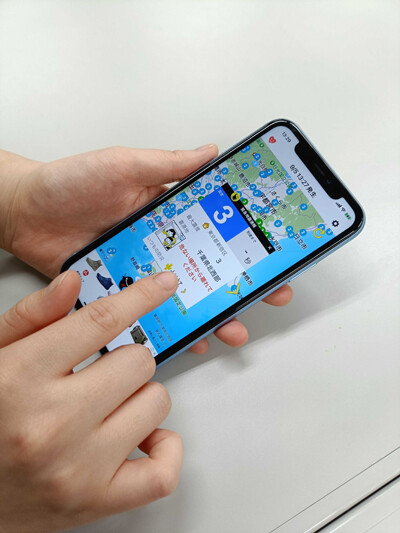自社の商品やサービスを「その企業ならでは」と認識してもらう企業ブランディングへの注目が集まっている。国内外の競争激化や物価の上昇などが背景にある。しかし、大企業と違い、中小企業がブランド戦略を打ち出すのは容易ではないとされる。こうした中で、インターネットを活用してコストを抑制しつつ、効果的なブランディングを実施する中小企業やB to B(企業間取引)企業も出始めている。この連載では、ITなどを活用してブランディングを行っている事例を紹介する。
第34回はソフトウェア開発を手掛けるアールシーソリューション(東京・新宿)を取り上げる。同社は観光庁に協力し、外国人観光客向けの災害時情報提供アプリを開発・運営している。同庁によるアプリの広報活動にも助けられ、潜在顧客の信頼を獲得している。国と連携することで、ブランディングにつながった事例だ。同社の栗山章社長は、ブランディングの必要性について「ニッチ(隙間)分野にも大企業が進出する時代になり、ニッチ分野を得意とする中小企業も差別化への努力が必要になった」と話す。聞き手はZenkenの本村丹努琉(もとむら・たつる)氏。
1963年新潟市出身。大学進学を機に上京し、在学中から世界各国を一人旅で巡る。南米から帰国後に大手IT企業に就職し、システムエンジニアとして従事。2002年にアールシーソリューション株式会社を設立し代表取締役に就任。2005年にはセキュリティシステムの開発に携わったことがきっかけで、安全・安心につながるシステムに関心を持つ。防災分野とITとの相性の良さに注目し、緊急地震速報「ゆれくるコール」の開発に取り組み、2007年にリリース。スマートフォンアプリのダウンロード数700万を達成。現在は防災に関わるシステム開発で培った技術を応用したサービスの展開に重点を置き、事業を進めている。
ポイント
①中小企業のブランディングは大企業との差別化につながる②中小企業は製品開発の時点でブランディングの観点が抜け落ちることも
③訪日外国人向けの災害情報アプリで観光庁に協力し、潜在顧客の信頼を獲得
④サービスなどの名称や内容変更は慎重に。愛着を持つユーザーへの考慮が必要
本村:貴社は企業のソフトウェア開発や運営を手掛けています。会社の概要と強みを教えて下さい。
栗山:当社は2002年8月に東京で私が創業しました。防災・減災ソリューションの仕組みを提供し、企業のBCP(事業継続計画)を支援しています。また、防災情報の提供やコンサルティングにも携わっています。
当社の強みは、顧客や潜在顧客から「ITを活用した防災サービスの専門的な知見があり、それを事業化できている」と評価されていることだと考えています。専門的な知見や経験はもちろんですが、企業や個人が「防災関連の課題をITで解決してもらおう」と考えた際に、当社を有力候補にしていただけるのが強みだと思います。
当社のサービスが知られるきっかけの一つは、2007年10月に開始した緊急地震速報アプリ「ゆれくるコール」でした。これは、気象庁が発表した緊急地震速報をもとに利用者のいる場所の予想震度やゆれの到達時間をプッシュ通知ですばやくお知らせするアプリです。東日本大震災などをきっかけにSNSなどで知名度が上がり、多くの方々に利用していただいています。
本村:東日本大震災の際には、多くの人たちが緊急地震速報を注視しました。今後も大きな地震の発生が予想されており、貴社のアプリは重要な役割を果たすと思います。こうしたサービスや製品のブランディングの意義について、栗山社長はどう考えていますか。
栗山:当社のような中小企業にとっては他社、特に大企業との違いや差別化をアピールするツールの一つだと考えています。創業した2002年当時は「中小企業は大企業が対応できないニッチ(隙間)市場への進出を目指すべきだ」と言われていました。ところが現在は大企業がどんな分野も隙間なく事業を展開しています。そのため、単純にニッチ分野の事業を展開するだけでなく、ブランディングを通じて知名度や認知度向上を目指す必要があると考えています。
本村:ニッチ分野のブランディングは難しいと思いますが、成功するにはどうしたら良いと考えていますか。
栗山:当社の場合は意図的にブランディングを実施したわけではなく、結果的にうまくいったケースだと思います。知人に緊急地震速報に関連するアプリをやることを相談したところ、他のアプリとは明らかに反応が違っていました。関心を持ってもらいやすい製品やサービスをブランディングすることで、その成功の確率は高まります。
本村:とはいえ、中小企業がブランディングを実施するのは難しいとの見方もあります。
栗山:確かに難しいと思います。中小企業の経営者や従業員はブランドやブランディングへの知識が不足しているからです。最初にサービスや製品開発をする時点ではお金を稼ぐことに精一杯で、ブランディングの観点が抜け落ちています。当社のサービスでも、防災分野であるにもかかわらず機能が分かれた複数のアプリが乱立する場合もあり、最初からブランドを統一しておけば良かったと思うことがあります。
ブランディングへの社内の理解度が低いことも問題です。中小企業の場合は「なぜブランディングをするのか」を従業員らに理解してもらうのも大変です。世代が代わっていきますから、若い人材にブランディングの意図を浸透させることも容易ではありません。
本村:確かに、ブランドの統一は社外だけでなく社内もやらなければならないように思います。
栗山:当社には多くのシステムエンジニアが在籍しています。エンジニアの製品作りはマーケティングやブランディングではなく、「技術」がスタートになることが多いためビジネスモデルやブランディングの構築は後回しになりがちです。それだけに社内理解が必要なのです。
本村:ブランディングの成功例は。
栗山:当社のサービスに、外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety tips(セーフティチップス)」があります。これは観光庁に協力を求められて製作したアプリで、災害情報全般を訪日外国人に14カ国語で伝えるものです。
観光庁が監修しており、プレスリリースまで出してくれました。実際に同庁が発表したリリースには「観光庁監修」という言葉も入っており、当社の信頼性を高めてくれています。当社はこのアプリを個人には無償提供しており、もうけがあるわけではありません。しかし政府に協力して災害情報のアプリを作っているというイメージが高まり、当社や当社のサービスへの信頼感を著しく高めました。このアプリは、いわば当社の「看板」になっていると言えます。
このアプリを通じて当社を知ってくれた潜在顧客も多く、Safety tipsのサービス開始後は企業から「課題解決の相談に乗ってほしい」「こんなアプリを作れないか」といった相談が多く入りました。すでにアプリを知った方々から10件程度の問い合わせがありました。今期はセーフティチップス関連が売り上げを伸ばしています。また、アプリを通じて当社の知名度が上がったことから、有能な人材の確保にも役立っています。
本村:ブランディングの失敗例はありますか。
栗山:「ゆれくるコール」を総合防災アプリ化して、名称を「PREP(プレップ)」に変えたところ、愛着の強い利用者から「元に戻してほしい」「名前を変えないでほしい」など1日に数十件も要望やお叱りを受けたことがありました。せっかく知名度やブランド力が向上したのに、私たちがサービスに愛着を持ってくれた顧客の心理を考えていなかったのが原因です。ユーザーのことを常に考慮に入れて事業を進めることが必要だと思います。
本村:Zenkenのサイトに貴社のサービスが掲載されています。
栗山:2024年7月から記事を掲載してもらっています。Zenkenの記事を読んでくれた潜在顧客は、当社のことを相当理解してくれています。当社のサービスに本当に興味がある方が問い合わせをしてくれるのは大歓迎ですし、実際にサービスを使ってくれる確率も高まります。
当社に問い合わせする人たちは、具体的には企業の危機管理担当者やBCP(事業継続計画)の担当者などです。実際にZenkenのサイトの記事を読んで、試験的に当社のサービスを使ってくれている企業も出てきました。
(編集協力 P&Rコンサルティング)