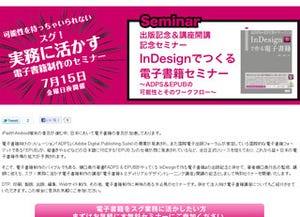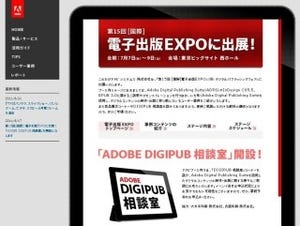この連載では、「Adobe InDesign CS5.5」を核としたソリューション「Adobe Digital Publishing Suite」(以下、ADPS)による、電子出版制作のための新しいワークフローについて考えていく。今回は、ADPSのワークフローを説明していきたい。
DTPデザイナーは、これまでのスキルを活かしてオーサリングが可能
さて、ADPSのワークフローを簡単に説明しよう。ADPSでは、まず「InDesign CS5/CS5.5」にて、本ソリューションの専用ファイル形式となる.folioデータを作成する。次に、そのファイルを、オンライン上のADPSにアップロードして、必要とあらば.folioファイルを編集し、最終的な.folioファイルとしてまとめ、ビューアーを含んだ電子書籍アプリとして書き出す。最後にこのアプリを、ADPS内のディストリビューションサーバーを使って、各マーケットへ配信するといった流れになっている。
ワークフローの最初の段階の、InDesignを使った.folioファイル作成までは、ローカルのマシンにて行う。たとえば、自社でADPSのアカウントを持つ出版社が、アカウントを持っていない社外のデザイナーに、.folioファイルの作成だけを依頼をすることも可能だ。なお、作成した.folioファイルは、iPad向けの無料アプリ「Adobe Content Viewer」に取り込んで確認することができる。
筆者は、昨年、アドビ システムズのジェレミー・クラーク氏と米Conde Nastのスコット・ダディッチ氏にADPSについてのインタビューを行った。その時に、聞いた事例だが、Conde Nastでは、既に紙/電子の区別なくメディア制作をしており、紙媒体でデザイナーと呼ばれていた人は、"ブランドデザイナー"という肩書きとなり、紙とデジタル両方のデザインを行っているそうだ。使い慣れたInDesignを制作の軸としていることもある、紙媒体のデザイナーでも、スムースに電子版作成に取り組めているようだ。
このように、InDesignをベースとしたコンテンツ作成により、紙媒体と並行して、ブランドの意図を統一した電子出版物制作ができることから、アドビでは、このソリューションを、出版社や紙メディアを扱う企業に適したものとしている。紙の雑誌との並行した制作フローやブランディング、スタッフの負荷を考えた場合、現状では画面サイズの大きなタブレットが最も親和性がある。こうした配慮から、ADPSでは、画面サイズの小さいiPhoneやスマートフォンへの適用は見送られたのだろうか。
ADPSのメインターゲットは、中堅・大手の出版社や広告代理店や印刷会社などで、対象企業別にふたつのエディションがある。一般企業や中小の出版社が自社コンテンツをすぐに各種マーケットで展開できるよう規格化されているのが「プロフェッショナル版」。大手出版社向けには自社運営やサードパーティが利用できるようカスタマイズできるエディションとして「エンタープライズ版」が用意されている。また現在のところ検討中とされているが、広告代理店や印刷会社など、第三者の制作工程を請け負い、サービスを代行するタイプの「エージェンシー版」も今後登場するとしている。
ADPSの導入価格はどうなっているのか
プロフェッショナル版の標準価格は、年間60万円で、発行できる媒体数に制限はなく、5,000ダウンロード分のサービス費用も含まれる。5,000ダウンロードを超える場合は、別途年間契約となるサービス費の前受金を支払う必要があり、2万5,000ダウンロードまでが62万5,000円(1ダウンロードあたり25円)、25万ダウンロードまでが425万円(1ダウンロードあたり17円)、50万ダウンロードまでなら700万円(1ダウンロードあたり14円)となっている。
エンタープライズ版は、個別の見積りとなっており、標準価格は公表されていない。プロフェッショナル版との違いは、SiteCatalystとの統合、ビューワーのカスタマイズ、カスタムストア用APIの提供、大部数発行時のボリュームディスカウントなどだ。
個人やSOHOのクリエイターにとっては、なかなか手の出しにくい金額と思う人も多いと思うが、前述したとおり.folio形式のファイルを作成するだけならInDesign CS5/CS5.5があればよく、上で示したADPSの年間費用などは必要ない。紙媒体と同じように、出版社などから発注を受けて作成したものを納品できるのだ。
次回からは、いよいよ.folioファイルの作成方法について解説する予定だ。