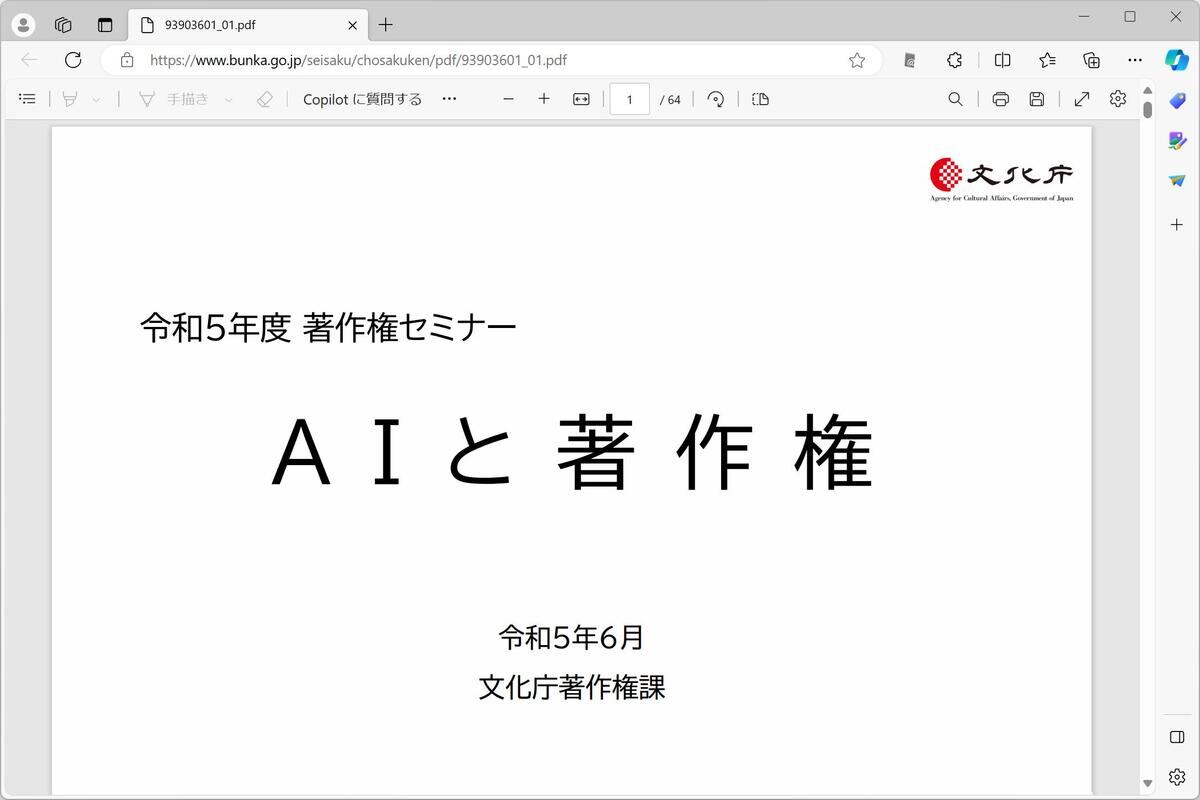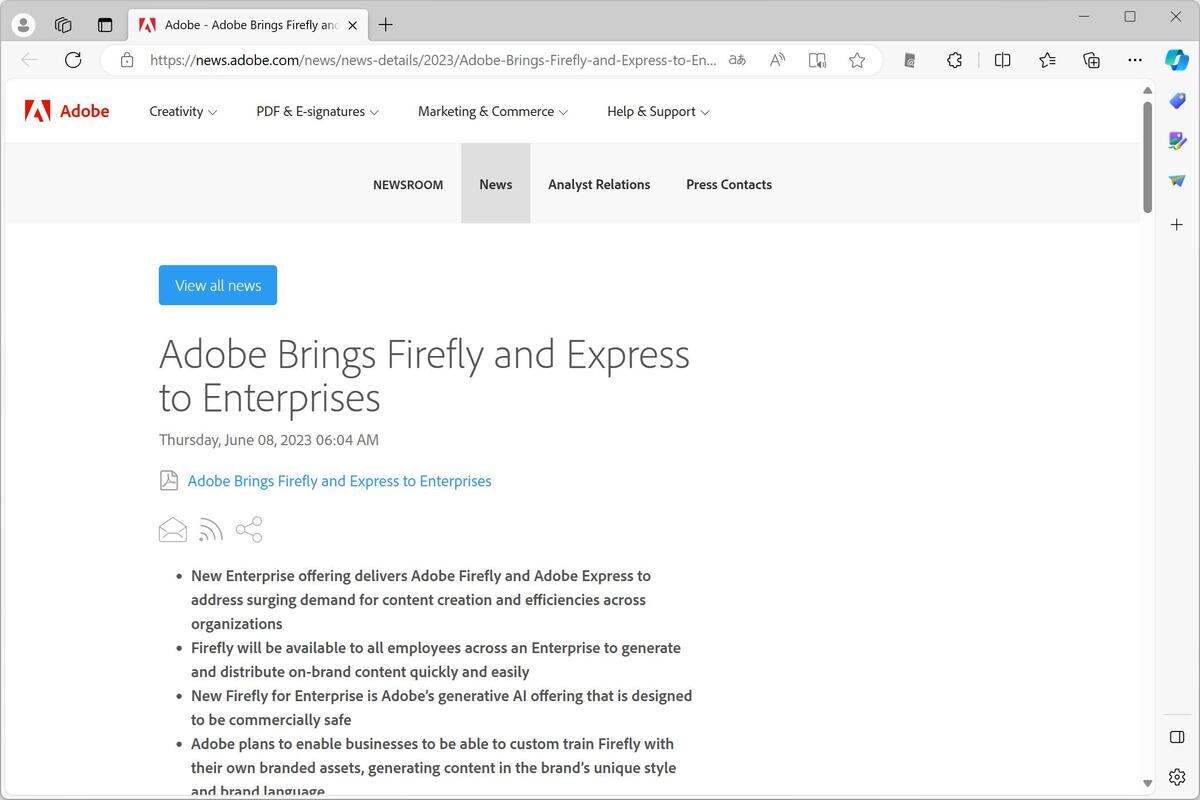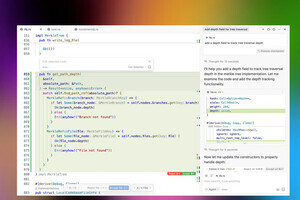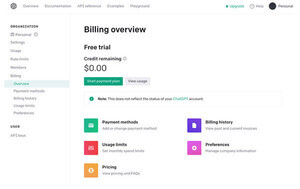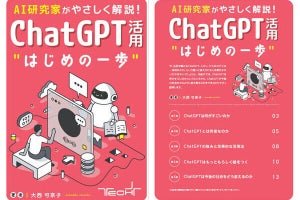ご存じの通り、DALL·E 3のような生成AIを使うことで画像を自動生成することもできる。だが、多くのデータを学習させたAIによって生成した画像の著作権は誰が保有するのだろうか。成果物を商用利用しても良いのだろうか。業務で使用するには、この辺りを明確にしておく必要がある。今回は生成AIと著作権について見ていこう。
-

DALL·E 3/GPT-4 ChatGPT Plusにて「生成AIが生成した画像の著作権は誰が持つことになるのか考えている博士の絵を生成してください。画像は横長にしてください。光り輝く荘厳な感じにしつつ、アニメ風に仕上げてください。」で生成した画像(その1)
生成AIで生成した画像の著作権は誰にあるのか
DALL·E 3のような生成AIの技術を使って画像を生成し、業務で利用したい場合、まず最初に「その画像の著作権は誰にあるのか」という点をはっきりさせておく必要がある。この辺りの情報は、文化庁のサイトに掲載されている資料 に分かりやすくまとめられており、参考になる。
上記の資料には、AIが生成した著作物について次のような説明が掲載されている。
AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。(例)人が何ら指示※を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり) 「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したもの
人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。
そしてその判断に関わるものとして次の説明が掲載されている。
人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。
どのような行為が「創作的寄与」と認められるかについては、個々の事例に応じて判断することが必要ですが、生成のためにAIを使用する一連の過程を総合的に評価する必要があると考えられます。
DALL·E 3の場合、ユーザーが自然言語によって出した指示を基に画像の生成を行う。生成までの会話は1回だけかもしれないし、複数回のやり取りが発生するかもしれない。上記説明によると「簡単な指示」を与えるだけにとどまった場合は著作物として認められないことになるが、著作物となる場合とならない場合の線引がどこになるのかはケースバイケースであり、最終的に裁判所で判断しなければわからないということになる。
結局、執筆時点ではDALL·Eのような生成AIが生成した画像の著作権については「利用者が著作権を持つ可能性が高いと考えられるが、ケースバイケースで判断する必要がある」という表現が当てはまるようだ。
このような技術が簡単に利用できるようになったのはここ1、2年の話だ。今後、法律が改正されていく可能性も高く、生成AIと著作権についてはこれからも最新の情報を収集して認識をアップデートしていく必要がある。
生成AIで生成した画像は使っても大丈夫か?
では、そのような曖昧な状況にある生成画像を使っても大丈夫なのだろうか。本連載で想定しているのは、「すでに学習済みのデータを使って提供されている画像生成サービスを利用して生成された画像の利用」についてであり、先の文化庁のサイトに掲載されている資料においては「生成・利用段階での著作物の利用」という項目の説明が該当する。
先の資料は生成・利用段階での著作物の利用について次のように説明している。
AIを利用して画像等を生成した場合でも、著作権侵害となるか否かは、人がAIを利用せず絵を描いた場合などの、通常の場合と同様に判断されます。
⇒「類似性」及び「依拠性」による判断
AI生成物に既存の著作物との「類似性」または「依拠性」が認められない場合には、既存の著作物の著作権侵害とはならないとされている。そして類似性については既存のコンテンツと同様の判断、依拠性に関しては複数の見解が例として取り上げられている。どちらにせよ、「最終的な判断は作品ごとに裁判所において判断される」と説明されており、著作権の有無と同様に簡単に使えるような基準は現時点ではないように見える。
OpenAIの考え方
生成AI技術を使った画像生成機能を提供しているベンダーは、どういったスタンスを取っているのだろうか。本稿執筆時点で、この分野の中心的な存在であるOpenAIは「Terms of use」に同社の考えを示している。
「Terms of use」(利用規約)の第3条「Content」の項a「Your Content」に次の文章が記載されている。
You may provide input to the Services (“Input”), and receive output generated and returned by the Services based on the Input (“Output”). Input and Output are collectively “Content.” As between the parties and to the extent permitted by applicable law, you own all Input. Subject to your compliance with these Terms, OpenAI hereby assigns to you all its right, title and interest in and to Output. This means you can use Content for any purpose, including commercial purposes such as sale or publication, if you comply with these Terms. OpenAI may use Content to provide and maintain the Services, comply with applicable law, and enforce our policies. You are responsible for Content, including for ensuring that it does not violate any applicable law or these Terms.
この項の説明によれば、法律が最初にありきという前提の上で、インプットデータはユーザーが所有し、アウトプットデータは規約を遵守する限り「OpenAIが全ての権利、権限、権益をユーザーに譲渡する」とされている。アウトプットの販売や出版などの商業利用も可能だとされている。
ただし、OpenAIは、サービスの提供や維持などの目的でインプットデータ/アウトプットデータを使うこともあるとしており、OpenAIも入出力データを使う可能性を匂わせている。
利用規約を読む限りでは「著作権は利用者が持つ」という見解のようだが、最終的にはやはり、裁判所の判断に委ねられるということになりそうだ。
なお、OpenAIはサービスを利用するユーザーの保護には積極的な姿勢を見せている。
同社は2023年11月6日(米国時間)、「GPT-4 Turbo」や「DALL·E 3 API」といった新しいサービスを発表した。
OpenAIはこの発表の中で「Copyright Shield(著作権シールド)」という著作権に関する保護の取り組みについて発表した。上記ページでは、Copyright Shieldに関して次のような説明を行っている。
OpenAI is committed to protecting our customers with built-in copyright safeguards in our systems. Today, we’re going one step further and introducing Copyright Shield-we will now step in and defend our customers, and pay the costs incurred, if you face legal claims around copyright infringement. This applies to generally available features of ChatGPT Enterprise and our developer platform.
説明は、ユーザーが著作権侵害に関する法的請求に直面した場合に、ユーザーを保護し、発生した費用を支払うといった内容になっている。対象はChatGPT Enterprise、および開発者プラットフォームとされていることから、これらの機能を業務に活用しようとしている企業を保護するのが目的だろう。つまりOpenAIは、著作権に関する懸念が生成AIの企業利用を阻害する要因の一つになっていることを認識しており、それを回避するための取り組みを着々と進めているのだ。
Microsoftの考え方
Microsoftは2023年9月7日(米国時間)に行った発表で、同社の姿勢を明らかにした。その内容は、先に取り上げたOpenAIのCopyright Shieldに似ている。
Microsoftは生成AIをCopilot系のサービスで提供しており、それらのサービスを使って生成された成果物に関して法的な問題が発生した場合、同社がユーザーを保護するといった内容になっている。Microsoftはすでに類似のIP補償サポートを行っており、今回の発表はこれを生成AIに対しても適用するといった内容だと言える。また、発表では生成AIの出力物に対して知的財産権を主張しない旨も説明している。
MicrosoftはDALL·E 3を利用した画像生成サービスも提供しているが、利用規約を読む限り、成果物に関しては商用利用に関して許可しているのか、禁止しているのかが曖昧な印象だ。商用利用したい場合は、Microsoftに問い合わせる方が良いだろう。
Googleの考え方
Googleも同社の生成AIが生成するサービスに関して同様の発表を行っている。
Googleの発表は、Google Cloudの生成AI関連サービスに関するもの(Google WorkspaceのDuet AI/Cloudサービス、Vertex AI Search、Conversation API、Text Embedding API、Visual Captioning、Codey APIなど)だ。具体的には、「トレーニングデータが第三者の知的財産権を侵害する、という主張に対する補償を行う」という内容と、「生成AI機能によって生成されたコンテンツが第三者の知的財産権を侵害する、という主張に対して保護を提供する」という内容が発表された。ユーザーが意図的に他社の権利を侵害しようとしない限りは、Googleが保護するというものになっている。
Adobeの考え方
その他の例としては、例えばAdobeが同社の製品である「Adobe Firefly」および「Adobe Express」の生成AI機能について、知的財産権の補償を提供すると発表しているものなどがある。
今後も情報収集を!
各社の考え方も見てきたが、総括すると、やはり本稿執筆時点では「生成AIを使って生成したコンテンツは利用者が著作権を持つ可能性が高いと考えられるが、ケースバイケースで判断する必要がある」というのが現状ではないかと考えられる。
-

DALL·E 3/GPT-4 ChatGPT Plusにて「生成AIが生成した画像の著作権は誰が持つことになるのか考えている博士の絵を生成してください。画像は横長にしてください。光り輝く荘厳な感じにしつつ、アニメ風に仕上げてください。」で生成した画像(その2)
画像をアップロードして公表したり、販売したりする行為は、利用許諾の対象だ。もし仮に、AIが生成したコンテンツの著作権が自身に存在していなかった場合は、著作権侵害になる可能性がある。こうした行為を行う場合は、事前に法律の専門家に相談するなどの措置を取ることが望ましい。
生成AIを活用した画像生成とそのユースケースについては、今後も続々と情報が発信されることが予想される。そうした情報の収集を積極的に行い、問題なく利用できそうなユースケースをまねていくというのも悪くない方法だ。受け身的なアプローチではあるものの、リスク因子が不確定なため、状況を見ながら利用シーンを増やしていくのが負担の少ない現実的な方法となる。
一方、どのような画像を生成できるのか試験するような段階では、こうした問題が発生する可能性は低いだろう。「プロンプトにどのような指示を出せば期待する画像を生成することができるのか」を研究すること自体は、知見を深めていく意味でも価値がある。生成AIが魅力的な可能性を持っていることは事実であり、何もせずに放置しておくのはあまりにも惜しい。少なくとも、調査・研究には取り組んでおこう。