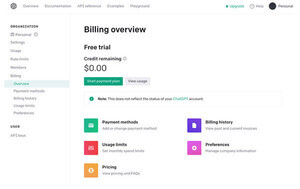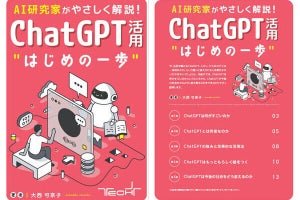前回は、ChatGPTがどのようにして誕生したのか、どういった仕組みで動いているのかを解説しました。ChatGPTが何者なのか、簡単にまとめると次のようになります。
- ChatGPTは突然生まれたわけではなく、2018年の初期GPTから進化を繰り返して現在に至る
- ChatGPTはWebの膨大な言語情報を学習し、前の単語の続きを予測して文章を生成している
- ChatGPTは人の質問に答えているのではなく、人の質問を書き出しとして続きを考えている
一見すると「会話」しているように見えるChatGPTが実は会話をしておらず、我々人間が書き込んだ質問の続きを予測して文章を生成しているという仕組みを知ってショックを受けた人がいるかもしれません。
でも、もしかすると私たち人間だって同じかもしれません。私たちもまた、会話の相手の質問に答えているのではなく、「会話の相手が発した言葉の続きとしてそれらしい文章を口にしている」だけで、結果としてそれが質問に対して答えているようにお互い錯覚しているのかもしれませんよ。
……と、これ以上この話を広げると「会話とは」「生命とは」のような哲学の領域に踏み込んでいきそうなのでいったんやめましょう(本当はとても面白い考察なのですが)。
ともあれ、ChatGPTが会話をしているわけではないことは事実です。
そして、このChatGPTの仕組みを分析すると、ChatGPTの“強み”と“弱み”が見えてきます。
本連載を1冊にまとめました!
【限定eBook】AI研究家がやさしく解説! ChatGPT活用“はじめの一歩”
>> ダウンロードはこちら
究極にパーソナライズされた応答を得られる
ChatGPTの強みの1つ目が「究極にパーソナライズされた応答を得られる」ことです。つまり、汎用的な文章ではなく、完全に自分だけに合わせた内容を生成できるのです。
お詫び文の生成を例に考えてみましょう。
あなたが勤めるアパレル企業の問い合わせフォームに、お客様から怒りの声が届きました。その内容は、2週間前に注文した運動靴がまだ届いていないというもの。
このお客様に対するお詫びのメール文章を作成する際、自分でゼロから考えるのは時間がかかるので、ひな型が欲しいとします。あなたはどうするでしょうか。もしChatGPTがなければ、おそらくWebでひな型を探すでしょう。「謝罪メール 書き方」とか、「謝罪メール テンプレート」などのキーワードで検索し、見つかった文章を一部書き換えて作成する人が多いはずです。
この場合、「そもそも今回の件に最適な謝罪文のテンプレートを探すのが大変」「テンプレートを書き換えるのに手間がかかる」といった課題があります。
そこでChatGPTを使用するのです。
例えば、次のように入力してみましょう。
「お客様が2週間前に注文した『A』という商品がまだ届かず、お客様はとてもお怒りのようです。このお客様へお詫びのメールを書きたいのでひな型を考えてください。その際『1週間以内にお届けいたします』という文章は必ず入れてください。なお、弊社は株式会社◯◯です」
すると、ChatGPTはこちらの事情をくみ取って、固有名詞も盛り込んだ謝罪文を生成してくれます。生成された文章はほぼ完成形と言ってよいもので、ほとんど手直しも必要ありません。
こうした完璧な謝罪文をWebで見つけるのは不可能です。ChatGPTに対して行った上記のような「プロンプト(ChatGPTに文章を生成させるために入力する文章をプロンプトと呼びます)」をそのままWebブラウザの検索欄に入力しても、ChatGPTが生成したような謝罪文は見つかりません。
当然ですよね。Web検索は“すでにWeb上にあるものしか探せない”のですから。しかし、ChatGPTはこちらのプロンプトに合わせて、文章をゼロから生成します。だからこそ、その内容は究極にパーソナライズされたものになるのです。
これが、Web検索にはできないChatGPTならではの強みと言えます。
対話によって少しずつ欲しい応答に近づけていける
続いてもう1つの強みとして挙げられるのは、「対話によって少しずつ欲しい応答に近づけていける」ことです。
ChatGPTが本質な意味で会話していない点は前回指摘しましたが、ここでは便宜上、プロンプトとChatGPTの生成文章のやり取りを「対話」と呼びます。
これも前回述べたように、ChatGPTはプロンプトに続く文章を予測して続きを生成しています。例えば最初のプロンプトを参照してChatGPTが生成した文章に対し、さらにプロンプトを続けると、ChatGPTは「最初のプロンプト+生成した文章+次のプロンプト」を参照してさらに続きを予測します。この仕組みにより、ChatGPTは「対話の流れを踏まえた回答」が行えるのです。
例えば、「知人を招いてホームパーティーを行う際、どのようなお酒を用意すべきか」を考えるとしましょう。あなたはお酒に詳しくないため、お酒の銘柄以前に何がホームパーティーにふさわしい飲み物なのかもよくわかっていません。
そこで、ChatGPTに「8月に知人を招いてホームパーティーを行う際、どのようなお酒を用意すべきでしょうか」と質問します。すると、ChatGPTは「8月は猛暑のため、スパーグリングワインがぴったりです」と返してきます。
次にあなたが「知人は20代です。スパーグリングワインのどの銘柄がお薦めですか」と質問すると、ChatGPTは「20代の方とのホームパーティーにはカジュアルで飲みやすい◯◯◯という銘柄がお薦めです」と回答します。
このやり取りのポイントは、そもそもあなたはお酒に詳しくないため、スパーグリングワインの銘柄を知らないどころか、そもそもスパーグリングワインを用意するというアイデアすら浮かんでいなかったことです。
つまり、ChatGPTとのやり取りの中でスパークリングワインというアイデアを知ったからこそ、さらにChatGPTに掘り下げた質問を行えたわけです。そして、ChatGPTもまた、この対話の流れを踏まえた回答を行っています。上記の例で言えば、「20代の方とのホームパーティーにはカジュアルで飲みやすい◯◯◯という銘柄がお薦めです」という回答は、直前の「知人は20代です。スパーグリングワインのどの銘柄がお薦めですか」という質問だけでなく、その前の対話の内容である「ホームパーティー」というシチュエーションも押さえたものになっていることがわかるでしょう。
こうしたChatGPTの特性を利用することで、あまり詳しくない分野についての疑問や課題をとりあえずChatGPTにぶつけてみて、返ってきた答えからさらに掘り下げていくことが可能になります。これは、自分で適切な検索単語を考えなければならないWeb検索では決して代用できない活用法と言えます。
ChatGPTに単に質問して回答させるだけだとWeb検索と変わらないかもしれませんが、このようにChatGPTの強みを理解することで、より効果的な活用法が見えてくるのです。
一方で、ChatGPTの使用には気をつけるべきポイントもあります。次回はChatGPT活用の注意点について解説します。