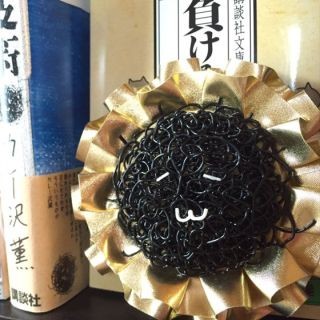今回のテーマは「フリーミアム」である。
「タダに慣れすぎて、有料コンテンツに抵抗を示す」
近年、「無料」なものが格段に増えた。昔は、無料エステ体験に行ったら、体験終了後、帰す気も寝かす気もねえというような武者に4方を囲まれ、気づいたら50万のエステローンを組んでいるなど、金を払う気がないなら、逆に無料のものには近づくべきではなかった。
しかし現在、特にデジタルコンテンツにおいては、後で何か要求されることもなく、無料で楽しめるゲーム、漫画、音楽などが数多くある。
もし画面に「会員登録ありがとうございます。期日までに16万振り込んでください、あなたのIPアドレスは把握しました」と出たのなら、ただのフィッシング詐欺なので振り込んではいけない。あと、無料のセクシーを探求するのもほどほどにした方がよい。
逆にタダに慣れすぎて、有料コンテンツに抵抗を示す者も増えてきた。そうなると、「金を払ってもらわないと、クリエイター側は活動を続けられなくなり、結果的に音楽や漫画が衰退する。長く楽しみたいなら、金を払うべき」というつぶやきが5000リツイートぐらいされ、それに対し「金を払わせる力がないのが悪い。こっちのせいにするな」というリプが100件ぐらいつく、という流れをここ数年、5億回ぐらい見ている。もはや熟年夫婦の会話の域だ。
この件に関しては、金を払わせる力がない側としては何とも言えないのだが、それでも買ってもらわないと餓死するのは事実なので、買え、買って燃やしてまた買え、と言うことを止めることはできない。
前置きが長くなったが、「フリーミアム」とは、そのような「タダ」のものである。
フリーミアム(Freemium)とは、基本的なサービスや製品は無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能については料金を課金する仕組みのビジネスモデルである。英語圏ではビデオゲームの場合、フリー・トゥ・プレイという。(引用:「フリーミアム」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』2017年10月30日 (月) 17:00)
これを聞いて、まず一番に思い浮かぶものがあるだろう。何も思い浮かばなかったならそれでいい。そのまま頭からっぽの方が平和だし、夢もつめこめる。
そう、俺たちのソシャゲがまさに「フリーミアム」である。
ソシャゲというものを、凄まじい金がかかる石油王の遊びと思っている人もいるかもしれないが、ソシャゲは基本無料だし、やろうと思えば永遠に無料で遊べるものだ。この先に進みたかったら課金しろとか、もう1枚脱いでほしければ金を払えとか、誠意を見せろとか言わない。もしかしたら最後の例は言うところもあるかもしれないが、少なくとも「基本プレイ無料」はウソではないのだ。
だが、無料で進めようとしたら、時間がかかったり、待ったりしないといけないし、レアリティの高いキャラクターやアイテムの入手は諦めなければいけないことがほとんどだ。そして、プレイヤーの中には、それが我慢ならねえという人間がいる。1秒でも早くゲームを進めたいし、レアキャラは全部欲しいという奴だ。
そういう石油王でなければ配偶者にしたくないタイプがどうするかというと、「課金」だ。課金して、待たなければ回復しない体力を回復させ、ゲームを進めたり有料ガチャを回したりして、レアリティの高いキャラを手に入れるのだ。
つまり、一部のこういうタイプの客が落とす金でソシャゲは収益を出しているのである。
課金型ペイントソフトの「確実性」
これはソシャゲだけの仕組みではない。ソフトウェアでも、「基本機能は無料で使えますが、さらに高機能にしたければお金を払ってください」というものがある。
ペイントソフトで例えると、無料だと赤、青、黄でしか描画できないが、金を出せば群青色でも描かせてやる、というわけだ。
しかし、そういうソフトは「課金すればランダムで何らかの機能がつく」とかいう状況にはならないし、「課金したとしても、場合によって群青色は追加されず、すでにある赤が5個ぐらいツールバーに表示されることもある」などということはない。そんなことをしたら訴訟ものだろう。
しかし、ソシャゲのガチャはそれが普通なのだ。「俺はこの群青色がほしいぜ」と課金しても赤が出る、それがガチャである。つまり、群青色が欲しければ出るまで課金するしかない。
また、課金型ペイントソフトであるなら、無課金の奴は絶対に群青色で絵を描くことはできない。しかし、ソシャゲだと無課金の奴が、課金者が出せなかった群青色を無料で引けるガチャで出して使っていたりするのである。
プレイヤーはよくこんなルールを受け入れているなと思うが、ここで「正気じゃねえ」と気づいた人間は課金をしない。つまり、正気じゃない人間により成り立っているのがソシャゲであり、私も正気を失っている側だ。
無料コンテンツが増え、有料に抵抗を感じるのはわかる。だが、ガチャと違い「金を払ったら意中の物が確実に手に入る」ということ自体、尊いことである。
私の本も、金を出せば確実に買え、火をつければ絶対に燃えるので、遠慮なく買って燃やして、また買って欲しい。
 |
<作者プロフィール>
カレー沢薫
漫画家・コラムニスト。1982年生まれ。会社員として働きながら二足のわらじで執筆活動を行う。デビュー作「クレムリン」(2009年)以降、「国家の猫ムラヤマ」、「バイトのコーメイくん」、「アンモラル・カスタマイズZ」(いずれも2012年)、「ニコニコはんしょくアクマ」(2013年)、「やわらかい。課長起田総司」(2015年)、「ねこもくわない」(2016年)。コラム集「負ける技術」(2014年、文庫版2015年)、Web連載漫画「ヤリへん」(2015年~)、コラム集「ブス図鑑」(2016年)など切れ味鋭い作品を次々と生み出す。本連載を文庫化した「もっと負ける技術 カレー沢薫の日常と退廃」は、講談社文庫より絶賛発売中。
「兼業まんがクリエイター・カレー沢薫の日常と退廃」、次回は2017年11月7日(火)掲載予定です。