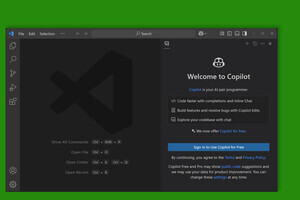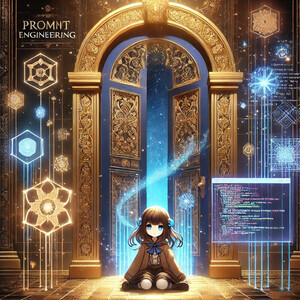2022年から爆発的に広がっている第四次AIブームはとどまることを知りません。毎日のように新サービス・技術が登場し、大手のプロダクトも頻繁にアップデートが繰り返されています。本連載では生成AIを中心に、今注目すべきAIのサービス/ソフト/ハードなどのレビューやニュース、インタビュー、イベントレポートなどを紹介します。
生成AIと言えば、ChatGPTが思い浮かぶ人も多いでしょう。2022年にローンチされ、第4次生成AIブームを引き起こした立役者です。その後、GoogleからGemini、AnthropicからClaudeという生成AIがリリースされ、現在でもしのぎを削り合っています。
この3つだけでも、何を使ったらいいのかわからない、という声もよく聞きます。Claudeは最新のAIモデルClaude 3.5 Sonnetをリリースした時に、各AIのベンチマーク結果を公表しました。
ライバルであるChatGPT 4oやGemini 1.5 Proよりも優れている、というものです。とは言え、そこから数カ月しか経っていないのに、OpenAIはChatGPT Proをリリースし、GoogleはGemini 2.0を発表しました。
そもそも、このChatGPT、Gemini、Claudeの御三家は、単にLLM(大規模言語モデル)がすごいというだけではありません。生成AIのメリットを最大限享受できるように様々な機能を搭載しています。
GPT-4o/o1やClaude 3.5 Sonnet、Gemini 1.5 ProなどのLLMのみを使いたいなら、「天秤AI」などの無料サービスも公開されています。今回は、Claudeの最新AIモデル「Claude 3.5 Sonnet」と便利機能の活用方法を紹介します。
UIは英語だが日本語の生成能力はトップクラスなので幅広く活用できる
Claudeは無料プランと有償(月額20ドル)のProプランが用意されています。Claudeで利用できるAIモデルはClaude 3.5 SonnetのClaude 3 Haiku、Claude 3 Opusの3種類です。
無料モデルでも最も賢いClaude 3.5 Sonnetを利用できるのですが、5時間に10数回という利用制限があります。Proプランは無料プランの5倍利用できるうえ、軽量モデルのClaude 3 Haikuもえます。他にも新機能へのアーリーアクセス、大容量データのアップロード、APIなど、多くのメリットがあります。
Claudeにログインすると、中央にフォームが表示されます。ここにプロンプトを入力します。AIモデルはその左下にあるプルダウンメニューから選びます。もちろん、Claude 3.5 SonnetでOKです。
「Style」では、出力のボリュームや形式を選べます。デフォルトは「Normal(普通)」でそのままでよいでしょう。他に「Concise(簡潔)」「Explanatory(説明的)」「Formal(丁寧)」も選べます。
ちなみに、ClaudeのUIは英語です。ChatGPTやGeminiのように日本語にできないのはマイナスポイントですが、操作は難しくないので何とかなると思います。もし、どうしても日本語で使いたいなら、ブラウザの翻訳機能などを利用しましょう。
例えば、メール文面を考えてもらいましょう。あまり書くことのない謝罪メールを書くときに、どういう表現にすれば角が立たないか迷うことがあるでしょう。そんな時は、友人に愚痴るようにプロンプトを書いてしまいましょう。
Claudeは人間が書いたような自然な文章を書くのが得意なので、そのまま使えるレベルのたたき台を出してくれます。気に入らない場合は「Retry」をクリックして再生成できます。問題なければ「Copy」をクリックしてコピーし、メール作成画面に貼り付けて使いましょう。
-
プロンプト
顧客に謝罪のメッセージを送るので簡潔に本文を書いて。到着した製品が破損していたとのことだが、調査の結果、配送業者のミスによるものと判明。こちらは悪くないんだけど、気分を害さないような内容にして。新品を送付する。なので、住所などの送付先をください。
ClaudeはチャットAIです。プロンプトの完成度を上げるよりは、アウトプットを確認し、追加で指示を出すことでブラッシュアップしていきましょう。例えば、上記の出力では、配送業者に原因があることを明記していません。そこははっきりさせておきたい、というならClaudeに返信しましょう。
「原因が配送業者にあるということは入れ込んでください」と書くだけで、想定通りのメール本文を再生成してくれました。
-
出力
構造化して視覚的に成果物を表示する「Artifacts」でWebアプリを作る
Claudeは成果物を構造化して別領域で表示する「Artifacts」という機能を備えています。視覚的でインタラクティブな操作が行えるので、Webページや論文など、何かを作り上げるときに便利です。プログラムの実行も可能で、さまざまなことができるため活用したいところです。
日本語で指示するだけで、HTML/CSSやJavaScriptなどでコードを生成できるのは、非エンジニアにとっては驚きの体験なので、ぜひ試してみましょう。
筆者は以前、飲食店向けeラーニングシステムの開発にチャレンジしたことがあるのですが、コロナ禍でダメになってしまいました。その時に作成した問題データがあるので、Artifactsでチャレンジしたところ数分でドラフトが完成して驚きました。
まずは、問題や答え、解説などを大量に貼り付け、eラーニングアプリを作ってもらうように依頼します。要件定義などはしたことがないので、欲しい機能を単純に箇条書きにします。
-
プロンプト
問題データを添付します。このデータベースを使って学習アプリを作成してください。
クイズゲームのようなeラーニングアプリのデザインにする
問題文を表示する
選択肢1~4を表示し、ユーザーに選ばせる
選択肢1○~4○が、1であれば正解、2であれば間違いなので、それを参照してすべての選択肢がきちんと選ばれていれば正解、一つでも抜けていれば不正解とする
そして、解説を表示。
次の問題へのボタンを表示する
点数はカウントする
終了ボタンも用意する。そのほか、必要な機能は自分で考えて搭載してください。
プロンプトを送ると、右側の領域にコードが生成されていきます。内容はわかりませんが、少し待つと右側に問題文と選択肢が表示されました。デザインの確認かと思いきやクリックすると動作します。
テストをしたところ、正答率を回答数ベースでなく、収録問題数ベースで出してきたのでそこを指摘するとすぐに直してくれます。指示していなかったのですが、正解と不正解は色分けで教えてくれるようになっています。
そこも、文字や記号でわかりやすくしてもらいました。その後も、テストをしていてスコアが加算されないバグを指摘するなどしていると、その都度修正されていきます。
でき上がったアプリは、右下の「Published」をクリックするとURLを発行し、他の人と共有することができます。コードを書けない筆者としては驚愕の体験です。
もちろん、コードの良しあしを判断できないので、重要な業務では使えませんが、近い将来そこも対応できるようになるでしょう。今はノーコードが主流ですが、逆に「Everyone codes」になる日が来るのかもしれません。
タスクによって資料やセッションを分類できる「プロジェクト」が超便利
チャットスタイルの生成AIとは言え、情報を集約したり、分類したいこともあるでしょう。タスクによっては前提情報として渡すファイルが決まっていることもあります。
そんな時、毎回ファイルをアップロードしたり、以前生成したスレッドを探し回るのは手間がかかります。そんな時に便利なのが、「プロジェクト」機能です。特定の用途や目的に特化したAIアシスタントを作成し、業務効率を向上させることができます。
メインメニューから「Project」をクリックし、「Create Project」をクリック。プロジェクト名を付けると、プロジェクト画面が開きます。やり取りしたセッションはそのプロジェクトにまとめられるので、いつでも振り返ることができます。また、右側の領域にファイルをアップロードすることで、そのプロジェクトでのみ利用する情報源として利用できるのです。
試しに、ビタミンCに関する論文を検索し、8個のPDFファイルをアップロードしました。合計ファイルサイズは約14MBで、約34万5000文字でした。この規模でも、アップロードできる容量は62%とのことなので、50万文字分くらいは入れられそうです。
社内ルールや製品マニュアルなどをアップロードし、質問することができます。総務やサポート担当の業務を肩代わりさせることもできそうです。筆者は現在、これまで書いた原稿や原稿を書く時の心得などをアップロードし、ライターとして稼働させられないか研究しているところです。
以上が、Claudeの解説となります。「Claude 3.5 Sonnet」の性能がすごいのは確かですが、アーティファクトとプロジェクトという機能も活用することでその真価を発揮します。ぜひ有償プランを契約して使い倒しましょう。