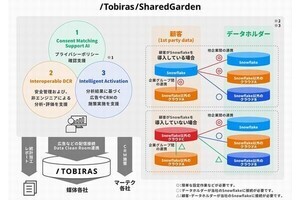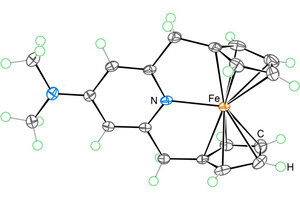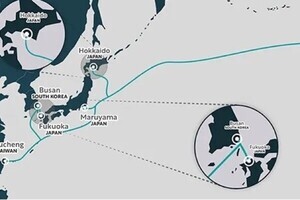「可能な限り、現地現物を自分の目で見ること」は筆者の信条。最近、本連載で過去に取り上げたことがある機体の実物に接する機会がいくつかあったので、その辺の話を取り上げてみようと考えた。「鉄は熱いうちに打て」ならぬ「ネタは熱いうちに出せ」である。。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
爆撃機の爆弾倉いろいろ
本連載が始まってからまだ間もないころに、爆撃機の爆弾倉について取り上げたことがあった。何トンもの爆弾を搭載するためのものだから、必要なスペースを確保するだけでなく、投下する前と後での重心位置の変動が少ない方が望ましい。そんな難しいアイテムである。
ボーイングB-29
そこで引き合いに出した機体の一つがボーイングB-29。この機体は主翼の前後に爆弾倉を分割設置して、その間で翼桁を左右に貫通させて胴体と結合している。構造上の合理性を考えた結果といえるが、個々の爆弾倉の長さは小さくなるので、搭載できる爆弾のサイズが限られる難点がある。
B-29の特徴として、機内を与圧している点が挙げられる。だから搭乗員は特別な装備がなくても過ごせるわけで、与圧機能がない他の爆撃機と比べたときの大きなアドバンテージといえる。もっとも、機内の温度がやや高めになる傾向があった、との話もある。
機内を与圧する一方で、爆弾投下の際に扉を開放する爆弾倉は与圧できない。そこで、与圧する区画は爆弾倉の前方と後方に分けた。そして爆弾倉の上部に円筒形のトンネルを設けて、前後の行き来ができるようにした。その爆弾倉とトンネルの現物を、ついに目の当たりにできた。それがこれである。
イギリスのアブロ・ランカスター
一方、イギリスのアブロ・ランカスターは、ぶち抜きの長い爆弾倉を胴体下面に設けて、その上部に主翼の桁を通したり、前後を行き来するための通路を設けたりしている。機内を与圧していないから、これでも差し障りはない。それに、ランカスターは夜間爆撃を主用しており、その際の飛行高度はそれほど高くなかった。
こうすると、爆弾倉の高さはB-29よりも抑えられる一方で、前後長を大きくとれる。だから、巨大なサイズの爆弾を積み込むには具合が良い。そしてとうとう、5トン爆弾の「トールボーイ」や10トン爆弾の「グランドスラム」を積んでしまった。
アブロ・リンカーン
そのランカスターの発展型が、アブロ・リンカーン。そのリンカーンB Mk.IIが、イギリスのコスフォードにある英空軍博物館に展示されている。当然、現物を見れば爆弾倉をのぞき込んでみる仕儀となる。それがこれ。
ボーイングB-52ストラトフォートレス
同じように、長い単一の爆弾倉を設けた機体として、ボーイングB-52ストラトフォートレスがある。1960年代に発注したB-52Hが未だに現役にあり、しかもこれからエンジンを換装して、さらにしばらく使い続けようというのだからすごい話ではある。
それだけ有用性が高い機体ということだが、それを支える要素のひとつは、この「大きくて柔軟に使える爆弾倉」かもしれない。
B-1Bランサー
ちなみに、B-52の後で登場したB-1Bランサーはというと、3カ所の爆弾倉に分割されており、それが前後に並んでいる。ただし前方の2カ所は隣接していて、仕切壁を取り払えば単一の長い爆弾倉として使うこともできる。ホテルのコネクティング・ルームみたいなものか。
B-1Bのトイレ
爆撃機は長時間の飛行任務に就くことが多いから、生理現象の問題を避けて通ることはできない。といっても、兵装やミッション機材や燃料で埋め尽くされた機内に、そんな立派なトイレを設置するスペースはない。
先日、テキサス州アビリーンのダイエス空軍基地で行われた “Wings Over West Texas” エアショーを訪れたら、B-1Bの機内を見せてもらうことができた。乗降用ラダーを降ろしたところに空軍の人がいたので声をかけたら、「後で機内を見せるよ」というので、喜び勇んで行列した次第。行列といっても短いものだったが、日本で同じことをやったら大変なことになっただろう。
B-1Bの乗員は4名。正副操縦士が前方に座り、その後方にWSO(Weapons Systems Officer)が二人。片方は兵装投下を担当するOSO(Offensive Systems Officer)で、他方は自衛用電子戦システムを担当するDSO(Defensive Offensive Systems Officer)。
その、操縦席とDSO・OSO席の間に、トイレが設けられている。といっても、旅客機のラバトリーみたいに立派なものではなくて、狭い区画に横向きの便器が置かれているだけだ。そこに座った女性搭乗員が、機体のことをいろいろ説明してくれた。
そういう事情なので、操縦席の写真は撮らせてもらえたが、トイレの写真はない。にしても「これは大変だなあ」と思ったものである。現場現物を自分の目で見て、感じてこその話であった。
このときKC-46Aペガサス給油機の機内も見学できたが、こちらは旅客機並みのラバトリーがコックピット後方に設置されている。ベースがボーイング767なのだから、当然といえば当然か。
ちなみに、我が国のC-2輸送機も、同じようにちゃんとしたラバトリーが付いている。給油機や輸送機も長時間の任務に就くが、爆撃機と比べるとだいぶ恵まれている。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第5弾『軍用センサー EO/IRセンサーとソナー (わかりやすい防衛テクノロジー) 』が刊行された。