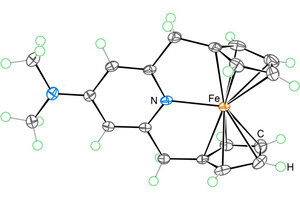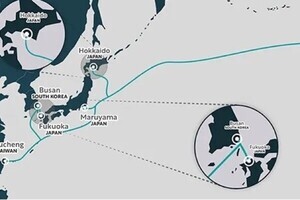この記事が公開されるときには、年末のお休みに入っているから……という、理由になっているのかよく分からない理由をつけて、今回はちょっとしたヒマネタを。
航空の業界は、フネの業界と共通する話がいろいろある。「運行」ではなく「運航」というし、機体のことをシップと呼ぶ。灯火類を見れば、左舷が赤くて右舷が緑というところも同じ。ところが、何もかも共通かというと、そういうわけでもない。
船の建造・就役にはセレモニーが多いが、飛行機は?
艦船が建造・就役を実現する過程では、セレモニーがいろいろある。
なじみ深いところでは、まず「起工式」。昔は、船体の「背骨」となる竜骨という部材を据え付けて「さあこれから建造するぞ」ということで式典を実施していた(飛行機でも、竜骨と呼ばれる部材が存在することがある)。
ところが、ブロック建造になっている現在では話が違う。すでに、ある程度まで組み上げたブロックを据え付けて式典をやっていることが多いのだ。すでに、かなりフネの形になった状態で「起工式」といわれても、看板にいささか偽りありの感がある。
そして船体の部分が完成すると、海に浮かべる「進水式」がある。それに合わせて「命名式」も行うのが普通。海上自衛隊のフネだと、「命名」は官側の行事、「進水」は造船所側の行事となる。
そして艤装工程を経て、カスタマーへの引き渡し、就役と話が進むが、その際にもまた式典がある。そういえば、まずドンガラを作ってから機器類・設備類を取り付ける艤装工程に進むところは、艦船でも飛行機でも鉄道車両でも同じであるし、艤装という用語まで同じだ。
では航空機はどうか。艦船と比べると「量産品」の傾向が強いからか、個々の機体ごとに式典を開くことが滅多にないのが、艦船と航空機の違いといえそうだ。つまり、イベントの対象になるのは、「最初の機体」と「最後の機体」に限られることが多い。
ただしこれには、「メーカーとしての」と「各々のカスタマーとしての」の2パターンがある。
航空機の製作に関わるイベントいろいろ
まず、メーカーの立場から「新型機を開発して、最初の機体の製作を開始するとき」。
よくあるのは、まず機体構造の中核となる部材が一つ、あるいは部分的にできたところで、式典を開く場面。これは艦船の起工式と似たところがあるが、それほど麗々しくやらない印象もある。最初に登場する部材として取り上げられやすいのは、胴体の隔壁(バルクヘッド)だろうか。
また、部材やコンポーネント、搭載機器が出そろってきたところで、「最終組立開始」に関するリリースを出したり、式典を開いたりする場面もあるようだ。例えば、これ。
航空機の分野で、大々的にセレモニーをやる最初の場面は、「初号機ロールアウト」が多い。つまり機体が完成して工場から引き出される場面である。ただしその場でいきなり飛び立つわけではなく、さまざまな地上試験を実施しなければならない。
だから、初号機ロールアウトから何カ月も経って、ようやく次の大イベントである「初飛行」がやってくる。筆者が生で見たことがある初飛行は、三菱MRJだけだが。
ただし初飛行の場合、場所が飛行場の滑走路になるせいか、多くの人が詰めかけるイベントにはなるが、「式典」にはならないようだ。
「式典」が登場するのは、完成した機体がカスタマーに引き渡される、いわゆる「納入式典」。もっとも、これをやるのはカスタマーごとの初号機や最終号機ぐらいのもの。たいていの場合、納入が進む途上で、いちいち1機ごとにイベントを開くわけではない。
そして運用期間を全うして退役するときに、退役・除籍の式典を開くこともある。最近だと、2024年8月7日に新明和US-2飛行艇の初号機(#9901)の除籍式が行われた事例がある。
また、民航機では退役した後で別のカスタマーに売却される、あるいはストックヤードに送られる、といった場面がある。そこで機体を送り出す際に、関係者によるお見送りを実施するぐらいのことはある。
カスタマーの立場から見ると
同じモデルの機体でも、カスタマーが複数いる場合には、イベントが増える。メーカーにとっては「量産する機体の一部」に過ぎなくても、カスタマーにとっては「ウチの最初の機体」だからだ。だから、「○○航空向けの最初の機体を納入」といって、いちいちリリースが出るようなことになる。
軍用機でも、カスタマーが多い機体では似たようなことが起きる。たとえば、ついにカスタマーが20ヶ国に達したF-35。
F-35の場合、各国ごとに1機目の組み立てにかかるところで、カスタマー国の関係者に工場まで来てもらい、レーダーを取り付ける前部隔壁のところにサインを入れてもらうのが恒例行事。米海軍の新造艦では、起工式のときにスポンサー(いわばゴッドマザー役)を務める女性のイニシャルを溶接で盛るのがお約束だが、それと少し似ている。
F-35は製造工程に載った時点で、それがどの国向けの何番目の機体になるかが決められており、それを示す番号を書いた紙が前部隔壁のところに貼られている。下の写真だと「FINAF F-35A MF-1」と書かれているのがそれだ。
-

フィンランド空軍向けF-35A初号機(MF-1)で使用する前部隔壁にサインを入れる、Henrik Elo 退役フィンランド空軍大佐(フィンランドでF-35導入計画の責任者を務めている 写真:F35.com
当然、初号機のロールアウト式典もカスタマーごとに行われている。こうしたイベントは、機体そのもの、あるいは機体の製造・納入が進んでいることを広く知ってもらうという意味で、大事な話といえよう。
ちなみに、自衛隊向けの航空機でも初号機納入の際に式典を開くが、そこでは神職が登場して祝詞をあげるのが恒例となっている。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第5弾『軍用センサー EO/IRセンサーとソナー (わかりやすい防衛テクノロジー) 』が刊行された。