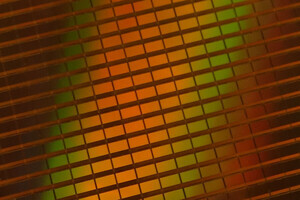軍民双方のターンアラウンドや、道路から戦闘機を離着陸させるといった話を取り上げていたら、タイミング良く(?)、自衛隊の戦闘機が演習で民間空港を使った離着陸訓練を実施した、というニュースが入ってきた。
手始めとして2023年11月13日に、大分空港では築城基地から飛来したF-2が4機、徳之島空港では那覇基地から飛来したF-15が4機、それぞれ訓練を実施したとのこと。その後も、別の民間空港で同様の訓練が行われている。連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
航空自衛隊の基地が敵の攻撃で被害を受けて使えなくなったら!?
これは、航空自衛隊の基地が敵の攻撃で被害を受けて使えなくなる場面を想定したもの。第325回で紹介したように、スウェーデンやフィンランドでは道路で離着陸しているが、日本では数千メートルにわたって幅広で平らな道路を確保するのが、そもそも難しい。
一方で、それなりの滑走路長を持つ民間空港はけっこうな数があるので、それを利用する方が現実的ではある。戦闘機が安全に離着陸できるとされる、滑走路長2,000m超の民間空港が、国内には約60ヶ所あるとされる。
使い慣れている基地以外のところに離着陸するとなれば、飛行場周辺の地形や障害物、離着陸時の飛行経路など、実際に飛んでみなければ分からない種類の話はいろいろある。だから、平時のうちに離着陸訓練を行っておく必然性がある。
ただ、滑走路だけあってもダメで、燃料・兵装の補給や機体の点検ぐらいはできないと、仕事にならない。今回の演習では、着陸して駐機場に移動した戦闘機に対して、民間の給油車を用いて民航機と同じ燃料を補給したという。
民航機と同じ燃料を使うところがミソ
実は、これが以前には簡単に実現できなかったこと。その辺の話はターンアラウンドの話にも関わりがあるのではないか、ということで、このテーマで取り上げてみた次第。
以前、航空自衛隊の戦闘機はワイドカットガソリン系のJP-4燃料を使用していた。しかし現在は、民航機と同じJET-A系列の燃料に切り替えている。
JP-4は民間では使用していない規格の燃料だから(ただし性状は民間用のJET-Bに近い)、それを平素から民間空港にストックしておくのは負担が大きい。
しかし、戦闘機でも民航機と同じJET-A燃料を使えるのであれば、すでにある燃料補給のインフラがそのまま使える。もっとも、もともと空港のタンクにある燃料を使わせてもらった場合には、後で燃料代の精算をしなければならないだろうが、それはまた別の話。
燃料以外の分野は?
上では燃料補給の話を書いたが、戦闘機は戦うための飛行機であるから、兵装の搭載も行わなければならない。これは民間空港に平素からストックしてある種類のものではないので、必要に応じて現場に持ち込む必要がある。整備点検用の機材も同様。
兵装は普段、基地内の弾薬庫にしまわれている(はずだ)から、それを引っ張り出してトラックか何かに積んで、移動先の民間空港に急いで搬入しなければならない。それをどこまで円滑に行えるか。
また、昔の戦闘機と違い、「戦うコンピュータ」と化している現在の戦闘機では、情報システムまで連れて歩かなければならないことがある。よくあるのは、飛行任務の計画立案に使用するミッション・プランニング・システム。
これは、飛行経路やウェイポイントごとの通過時刻などを事前にプランニングしておくのに使う。作成した飛行計画データをデータ転送カートリッジにコピーして、それを機体にセットすると、ミッション・コンピュータは「これからどこに行って何をするのか」を理解する。
また、F-35では機体の運用や整備補給に関わる一切合切を司る、ALIS(Autonomic Logistics Information System)や、その後継となるODIN(Operational Data Integrated Network)といったシステムがある。ALISは遠隔地のサーバに接続するし、ODINはクラウド化を取り入れているから、スタンドアロンでは仕事にならない。
こうした各種の情報システムを使うのであれば、戦闘機を離着陸させる場所に所要の機材を持ち込む必要がある。そして、情報システムの機材を可搬式にするとか、どこに行ってもネットワークに接続できるように通信機材を用意するとかいう話も出てくる。
あと、その手の「電気製品」を稼動させるのであれば、発電機まで持って行かなければならないかもしれない。有事の際に出先で所要の電源を確実に確保できるとは限らないから。
滑走路だけの問題ではない
平時に使用している母基地以外のところで戦闘機のターンアラウンドを実現しようとすれば、単に「滑走路だけあれば済みますよ」という単純な話ではない、ということを書いてみたかった次第。
実のところ、航空自衛隊はこれまで、「本来の基地ではないところを活用する分散運用」をあまり熱心にはやって来ていなかったように見える。この見立てが正しければ、民間空港を活用した分散運用についても、これから道具立てを整えて、訓練を施して、体制を作っていかなければならないだろう。
口でいうほど簡単な話ではなさそうだが、今回の訓練はそのための大事な一歩になるのではないか。この先、地上側で使用する支援用の資機材についても、以前にはなかった種類のものが出てくるかもしれない。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」の単行本第3弾『無人兵器』が刊行された。