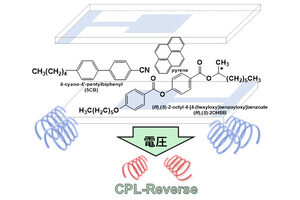前回は、機体に載せるエンジンや電子機器について、どういった形で整備を実施するかという話を取り上げた。その続きとして、二段階整備と三段階整備、そして整備を外注する際の契約形態について取り上げてみる。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
二段階整備と三段階整備
エンジンや電子機器の整備に絡んで頻出するキーワードが、二段階整備(two level maintenance)と三段階整備(three level maintenance)。その名の通り、整備作業における「段階」の違いを示している。
三段階整備とは、「列線(ライン)・中間・デポ」という意味。それに対して二段階整備とは、「列線(ライン)・デポ」という意味。ここでいう列線(ライン)とは運用現場を指す。対してデポとは、後方の整備拠点やメーカーの工場を指す。では中間とは何かというと、運用現場ごとに置く整備拠点を指す。
二段階整備では、機体の運用現場では細かい整備を行わず、外したSRUやモジュール(場合によってはLRUや計器など)を直接、メーカー、あるいは運用者の後方整備部門に送る。そちらでどういう整備を行うかは、機体の運用現場は関知しない。極端なことをいえば、整備済み品が円滑に運用現場に供給されるかどうか、だけを気にすれば良い。
二段階整備を選ぶメリット
規模が大きい運用者であれば、整備のニーズも大きくなるから、自前で整備部門を抱えて三段階整備にすることにもメリットがある。しかも、機器がブラックボックス化しない。
しかし、規模が小さな運用者がいちいち整備部門を抱えるのでは、相対的に負担が大きくなる。すると、二段階整備にして、できるだけメーカーや外部の整備専門会社に投げる方が良い、という考え方にも利がある。その代わり、開けずに整備に回す機器はブラックボックス化する。
二段階整備が円滑に機能するかどうかは、交換する予備品を安定的に確保できるかどうか、それと、整備済み品を入手するためのリードタイムに依存する。予備品が不足したり、整備済み品の入手に時間がかかったりすれば、二段階整備は画餅と化し、機体の可動率が下がる。
つまり、単に整備のための人手や設備を整えるだけでなく、モノがメーカーと運用者の現場の間で行き来するプロセス、すなわちサプライチェーン管理が課題になる。もっとも、運用者が整備を行う場合でもパーツの往来は発生するので、サプライチェーン管理の問題がなくなるわけではない。
二段階整備にしづらい場面もある
場合によっては、二段階整備を安直に導入できないことがある。その一例が空母。
陸上の飛行場なら場所が固定されているし、大型の輸送機でも発着できる。だから、整備拠点あるいはメーカーとの間で定期便を飛ばして、モジュールやLRUやSRUやパーツを輸送する体制は構築しやすい。しかし空母は動き回っている上に、発着できる機体の種類や規模に限りがある。
また、米海軍の場合、空母がいったん展開任務(デプロイメント)に出ると、何カ月も母港に帰らず、本国から遠く離れた場所で任務に就く。すると、空母における搭載機の整備にはどうしても、相応の自己完結性が求められる。
だから米海軍の空母では、中間整備部門(AIMD : Aircraft Intermediate Maintenance Detachment)を置いて、ここである程度、深度化したレベルの整備を行う体制を作っている。降ろしたエンジンを艦上で整備するから、整備したエンジンを試運転する場所も用意してある。もちろん、すべてを空母の艦上で行うのは無理な相談なので、手に負えなくなれば本国の整備拠点に投げるのだが。
こうした事情があるため、米海軍の空母に発着する輸送機(COD : Carrier Onboard Delivery)には、空母搭載機が使用するエンジンを載せられること、という条件がつく。電子機器ぐらいなら問題にならないが、エンジンは大物だから機体によっては載せられない。
エンジン整備契約の4形態
ここまで書いてきたような整備業務に関わる話を、メーカーの立場から見るとどうなるか。
整備をメーカーが請け負う場合、同じモデルの機器を使用する複数のカスタマーから整備・修理を請け負うことで、スケール・メリットを発揮できるとの期待を持てそうではある。それでコストが下がれば、カスタマーも助かる。
そこで問題になるのが契約の形態。これが実はいろいろある。エンジン整備の委託を例にとって列挙してみる。
まず、T&M(Time and Materiel)。整備作業でかかった人件費やパーツ代などを、そのまま実費計上する方式。機材の状況次第では整備費用が嵩むが、メーカー側にしてみれぱ損はしない。
次が「NTE(Not-to-Exceed)」。整備対象となる機材の状態に応じて整備費用を計上するが、上限額を設定して、それを超える分は請求しない。発注する側は安心感があるが、機材の状況が良くないとメーカーが損をする。
次が「FP(Fixed Price)」。つまり固定価格で、作業の量や内容に関係なく同一額。作業量が増えれば発注側が有利になるが、整備を請け負うメーカー側は損をする可能性が高まる(作業量が少なければ逆になる)。また、発注側にとっては固定費の削減が難しくなる。
そして「PBH(Power by the Hour)」。飛行時間に応じて費用を決定・前払いする方式で、飛行時間が増えれば費用も増えるし、飛行時間が少なくなれば逆になる。最近、増えてきている方式。
それぞれ一長一短があり、作業量の多寡、飛行時間の多寡、対象となる機材の多寡といった要因により、どの形態が有利になるかが決まってくる。
経済的な話だけでなく、メーカー側にとっては「自社のノウハウが詰まった製品を、他社にバラされたくない」「納入後の整備までまとめて請け負うことで、顧客を囲い込みたい」「その過程で、非純正部品の締め出しを図りたい」といった思惑も絡んでくる。
すると、「整備は一括して請け負うから、降ろしたエンジンをそのまま渡してほしい。その代わり、費用の面では勉強させていただく」という展開もあり得る。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」が『F-35とステルス技術』として書籍化された。