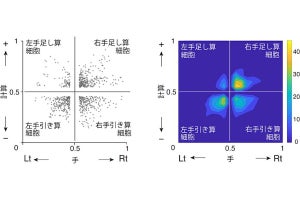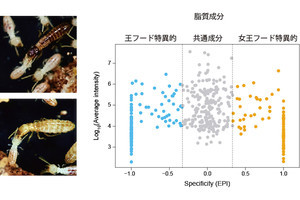慶應義塾大学(慶大)と京都産業大学(京産大)の両者は10月27日、兵庫県新温泉町の「おもしろ昆虫化石館」で保管・展示されていた約250万年前の地層から産出した化石が、これまでミツバチの化石記録の空白域であった鮮新世~更新世前期に属する新種であることを確認し、「タジマミツバチ」と命名して報告したと共同で発表した。
さらにこの化石は同時に、世界最古のミツバチ亜属の化石であり、最も新しい絶滅種のミツバチであることも併せて発表された。
同成果は、慶應義塾幼稚舎の高橋唯教諭(博士)と京産大 生命科学部の高橋純一准教授(京産大 生態系サービス研究センター センター長兼任)の研究チームによるもの。詳細は、動物の分類学や系統学、生物地理学、進化を扱う学術誌「ZooKeys」に掲載された。
“空白の時代”を埋める新発見
ミツバチは、花粉を運んだり花蜜を集めたりしてハチミツを作るため、人間と最も関わりが深い動物の1種だ。分類は、ハチ目ミツバチ科ミツバチ属に含まれる昆虫で、現在は3亜属9種(11~12種とする場合もある)が存在する。その中の1亜属であるミツバチ亜属に属するものが狭義のミツバチであり、およそ6種が現存する。そして日本には現在、在来として「二ホンミツバチ」(「トウヨウミツバチ」の亜種)と、輸入された「セイヨウミツバチ」の2種が存在する。
今回のミツバチ化石の標本は、兵庫県新温泉町の教育委員会が管理する「おもしろ昆虫化石館」による保管・展示がなされていたもの。この標本を高橋教諭が教育委員会より借り受け、ミツバチを専門とする高橋准教授と共に検討が進められた。
化石は全長1cmほどの働きバチで、翅脈や後脚の特徴からミツバチ属のミツバチ亜属と判明した。そこで、ミツバチ亜属に含まれる現生種との比較が行われた結果、現在知られているいずれの種にも当てはまらない新種であることが突き止められた。化石は、地域にちなんで和名は「タジマミツバチ」、学名は「Apis(Apis) aibai」と命名され、記載された(aibaiとは、新温泉町でチョウ化石の新種を報告した研究者の相場博明氏にちなんだもの)。
研究チームによると、この化石の重要な点は、ミツバチの進化史に横たわる3つのギャップに橋を架けたことだという。その第一は、化石記録の橋渡し。これまでのミツバチの化石記録は、古い時代である漸新世(約3800万~約2400万年前)および中新世(約2400万~約500万年前)の化石種(亜属レベルで異なる)と、更新世後期(約13万~約1万年前)からの現生種しか存在なかった。しかし今回の発見によりその間の期間(鮮新世~更新世後期)が埋められ、最も新しい絶滅種が約250万年前に存在していたことが明らかにされた。
第二は、遺伝子データと化石記録の橋渡しである。これまでのミツバチ亜属の化石記録は、更新世後期の現生種とされるものの化石のみだった。しかし、現生ミツバチの遺伝子データから、鮮新世にはすでにミツバチ亜属が出現していると推定されていた。今回のタジマミツバチの発見は、この遺伝子データと化石記録のギャップを埋める橋渡しをしたことになる。つまり、タジマミツバチは世界最古のミツバチ亜属の化石であり、かつミツバチ亜属で初めての絶滅種ということがわかったのである。
そして第三は、現生ミツバチの2種、アジアに広く分布するトウヨウミツバチと、系統的には最も近いとされるが、フィリピンのミンダナオ島とインドネシアのスラウェシ島、セベレス島、サンギヘ島にしか存在していない「クロオビミツバチ」の橋渡しをしたことだ。タジマミツバチは形態的にトウヨウミツバチよりクロオビミツバチに近いことから、今回の発見は、過去にはタジマミツバチのようにクロオビミツバチに近い種が東アジアに広く分布していた証拠となる。したがって、タジマミツバチはトウヨウミツバチとクロオビミツバチの進化をつなぐ鍵となり、ニホンミツバチの祖先種となる可能性も期待されるとしている。