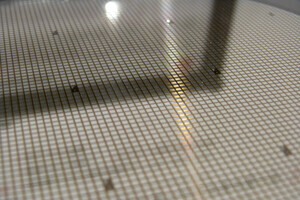日本の半導体メーカー6社が北大で学生向けイベントを開催
Rapidus(ラピダス)、キオクシア、ソニーセミコンダクタソリューションズ、東芝デバイス&ストレージ、三菱電機、ルネサス エレクトロニクスの国内半導体メーカー6社は2025年7月25日、北海道札幌市の北海道大学(北大)理学部5号館大講堂において、「SEMICON TALK 2025 in Hokudai」を開催した。
2024年12月に、神戸大学で開催したのに続き、2回目となる。また、北海道大学では、博士人材教育の一環として、このイベントを開催した。
学生は半導体に夢を持てるのか?
「SEMICON TALK」は、学生の半導体への興味を醸成したり、未来のキャリア形成を支援したりするプロジェクトで、半導体メーカー同士が連携し、イベントを開催。半導体エンジニアによるトークセッションや、企業ブースの展示などを通じて、大学生と直接接点をつくり、半導体産業の人材獲得や、興味喚起の促進などを図っている。
今回のイベントでは、「半導体に夢を持てるのか、輪になって躍ろう北海道! 〜半導体メーカーが北大へ大集結! 本音で語る現場のあれこれ〜」というサブタイトルが付けられた。北大が、半導体産業をテーマに、学生向けイベントを開催するのは、これが3回目。その言葉通り、各社の北大出身のエンジニアが登壇。会場には、約80人の大学生、大学院生などが参加した。理系専攻の学生が多くを占めており、北大出身の先輩エンジニアの話に、熱心に耳を傾けていた。
午後6時30分からスタートしたイベントの冒頭に挨拶した北大の石森浩一郎 副学長は、「北大が開催している『半導体に夢があるのか、みんなで考えよう』というイベントは、博士人材の育成を主眼に置いた企業と大学による共創教育プログラムである。半導体人材といっても、作る人、使う人、支える人があり、すべての人材が、半導体業界にとって重要である。今回登壇する半導体メーカーのエンジニアは、作る人であり、参加している学生にとって、近未来の人たちである」と前置きし、「学生は、自分と現場のギャップを解消した上で、従事する業界と企業を決めることが重要である。半導体企業に従事することの意味、自分をどういう形で活かせるのか、どういう問題に立ち向かう必要があるのかを知り、半導体業界に従事することに関心を持ってほしい」と呼びかけた。
北大出身の半導体メーカー勤務者が実際に登壇
トークセッションに参加したのは、Rapidus技術開発統括部リードエンジニアの松本悟氏、キオクシアのAI・システム研究開発センターグループ長を務める塩沢竜生氏、ソニーセミコンダクタソリューションズのモバイルシステム事業部に所属する榊飛翔氏、東芝デバイス&ストレージ 半導体事業部アナログIC製品技術部の安田健介氏、三菱電機 パワーデバイス製作所 品質保証部の工藤智人氏、ルネサス エレクトロニクス オペレーショングループ製品技術部の水野慎太郎氏の6人。先に触れたように、全員が北大出身だ。
聴講した北大 総合理系学部1年の男性は、「専攻を決める上で、企業で活躍するエンジニアの姿を直接見ることができ、社会でどのような専門性やスキルが求められるのかが具体的にイメージできた。半導体には関心があった一方で、日本は世界と比べて劣っている印象を持っていたが、世界の先端をいく技術を持つ企業の存在を知れたことは、学びになった」とコメント。同大理学部3年の男性は、「博士課程に進学し、将来はアカデミアとして研究を続けようと思っていたが、企業の研究職として働く選択肢があることを知り、視野が広がった。進学と就職の選択で迷う学生は少なくないので、今回のように企業の内側を知ることができる機会は増えてほしい」とし、同大工学部4年の女性は、「研究テーマとして半導体について学んでいる一方で、この専門を追求し続けて、将来、企業に就職して生計が立てられるのか、社会の役に立てるのかが不安だった。企業のエンジニアから仕事について直接話を聞くのは初めてだったが、半導体と社会の関わり方は一通りではないと感じられ、安心した」と語っていた。
半導体産業をキャリアとして考える機会を提供
企業ブースは、午後4時からオープンしており、午後8時30分まで対応。参加した学生と、各社の研究者や技術者、人事担当者が対話するシーンが見られていた。
SEMICON TALKは2025度中に、関東や関西の複数の大学においても開催を予定しており、参画する半導体関連企業を広げながら、持続的なイベント開催につなげる考えだ。
ソニーセミコンダクタソリューションズでは、「SEMICON TALKを通じて、より多くの学生に、半導体産業への興味を深めてもらい、将来のキャリアを考える機会の提供を目指したい」としている。
半導体は「産業の米」と言われるように、AIやIoT、自動運転などの技術革新においても不可欠なものであり、その重要性は日々高まっている。また、安全保障やサプライチェーン、国家戦略にまで影響を与える存在となっているのも周知の通りだ。
一方で、2025年4月に北海道千歳市に拠点を構えるラピダスの2nmプロセス試作ラインが稼働し、日本の半導体産業の中心地のひとつとして、北海道が注目されつつある。
半導体の認知度は高まるも、産業へのネガティブイメージは払しょくしきれず
こうした話題性や各社のプロモーションの強化もあり、半導体に対する認知は高まっており、学生の85%が認知しているという調査結果もある。
だが、日本の半導体産業のプレゼンスが大きく低下してきた過去の歴史もあり、ネガティブな印象を払拭できていない実情は見逃せない。
ソニーセミコンダクタソリューションズの調査によると、日本の半導体産業は、情報(IT)系と比較するとレガシーな産業のイメージがあること、AIや情報系は、都心勤務やリモートワークなどの先進的な働き方に積極的だという印象があるのに対して、半導体産業には地方勤務やクリーンルーム内での勤務といった地味な印象があることなどが指摘されているという。
また、半導体は、研究内容がわかりにくく、身近に感じないこと、社会への貢献や実生活への貢献がわかりにくいこと、半導体を学んだ場合、どんなキャリアを築けるかといったことが情報系に比べてイメージが湧きづらいという課題も指摘されている。
SEMICON TALKは、こうした半導体産業が抱える課題を、産学連携によって解消することを目指しており、学部1、2年生に対して、研究室を決める前に、半導体への関心を高めてもらったり、半導体以外を学んでいる理系学生にも興味を持ってもらったりすることも狙っている。
半導体産業への注目度を高める役割を担うSEMICON TALK
これまでに、人材育成を目的に、競合する半導体メーカー同士が、連携する試みはなく、半導体産業の人材獲得に向けて危機感が感じられるともいえよう。
ソニーセミコンダクタソリューションズでは、「学生と、半導体メーカーのエンジニアが直接、接点を持つことにより、半導体産業に対するネガティブなイメージを解消することを狙っている。学生のイメージを塗り替えるために体験型のイベントとすること、学生が参加しやすい大学構内での開催を前提とすること、複数企業と大学が連携することで、注目度を高めること、複数回の開催により、広く展開することを目指している」とする。
産業側は、採用できる学生の母集団形成に苦戦しており、大学側では、優秀な学生が半導体の研究に進まないという状況にあり、しかも、それが長年に渡って続いている。
半導体産業に興味や関心を持つ学生が少ないという、産業側と大学が持つ課題解決の一助としてもSEMICON TALKの活動が注目される。