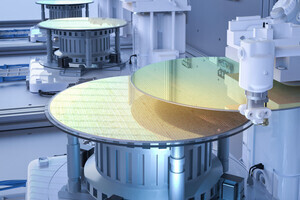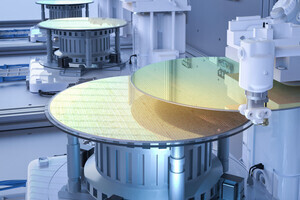富士フイルムが注力する半導体材料ビジネス
富士フイルムは7月15日、同社の半導体材料事業の現状に関する説明会を開催。2030年度の売上高目標5000億円の達成に向け、先端材料分野の開発を加速させていくことを明らかにした。
富士フイルムの現在のビジネスは大きく分けて「ヘルスケア」「エレクトロニクス」「ビジネスイノベーション」「イメージング」の4つ。2024年度の全体売上高3兆1958億円の内訳としては、ヘルスケアが1兆226億円、エレクトロニクスが4328億円、ビジネスイノベーションが1兆195億円、イメージングが5420億円となっているが、このうちエレクトロニクスの営業利益は773億円、利益率17.9%で、全体に占める割合としては23.4%とかなり利益率の高いビジネスとして存在感を発揮している。
-

半導体材料事業が含まれるエレクトロニクス分野の売上高は4328億円とほかのセグメントよりも低いが、営業利益では4セグメント中で上から2番目。利益率もイメージングに次ぐ2番目に位置づけている (資料提供:富士フイルム、以下すべてスライド同様)
そのため同社は、市場拡大が期待される半導体材料市場を自社のポートフォリオの中核をなす次世代・成長事業と位置づけ、2025年度から2026年度までの2年間で1000億円以上を設備投資とR&Dに投じることを計画。中でも微細化要素の1つであるレジスト材の先端プロセスへの対応に加え、先端パッケージを中心とする後工程材料市場は、保護膜形成・再配線層用ポリイミドだけでも2023年から2030年の年平均成長率(CAGR)は7.2%で、2023年の4億9000万ドルから、2030年には8億300万ドルへと成長することが期待されており、売上拡大の大きな機会と捉えているとする。
前工程から後工程まで幅広いプロセスをカバー
同社が提供している半導体材料は主に、前工程向けの「フォトレジスト」「現像液・剥離液・プリウェット材」「薄膜形成用CVDプリカーサ」「CMPスラリー」「ポストCMPクリーナー」「プロセスケミカル」ならびに後工程向けの「ポリイミド材料」、そしてイメージセンサ関連の「カラーフィルター用レジスト材」となっており、これらのうちフォトレジスト、CMPスラリー、洗浄工程向けのプロセスケミカルの3分野で特に存在感を発揮している。
富士フイルム 取締役・常務執行役員 エレクトロニクスマテリアルズ事業部長で、富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ代表取締役社長も務める岩﨑哲也氏は、これだけ幅広い材料を取りそろえることについて「幅広く持つことで、あらゆる装置メーカーとの協業が可能となる。隣接するプロセス含めて、パートナーの装置メーカーが新たなプロセスの対応を図っていく中で、一緒に開発を進めることで、当該装置の両隣の装置も含めて、我々の材料を活用してもらえるようになる。また、Rapidusやインドを中心に短期間でファブを一気に立ち上げるニーズが高まっており、そうしたニーズに一貫した材料の提供と技術サポートを提供できるワンストップの重要性が増しているほか、後工程に前工程の技術が投入されるようになってきている昨今、前工程で培った技術力や製品が活用できる点は競争優位点になる」と、幅広く取りそろえることが自社の強みをさらに高めることにつながることを強調する。
-

インドではタタグループが半導体前工程工場の建設を計画。その工場に富士フイルムがさまざまな半導体材料の供給を行う予定となっている。この供給は、現地での材料製造・供給のみならず、インド外からの供給も含めたものだという
好調な半導体材料市場、目標を2年前倒しで達成
こうした幅広い材料を取りそろえることで同社は、半導体材料市場の2024年~2030年にかけてのCAGR7%を上回るCAGR12%の実現を果たし、2030年度5000億円の売上高達成を目指すとしている。すでに2020年度~2024年度の実績CAGRで20%を達成、2023年に買収を発表したEntegirsのプロセスケミカル事業の買収効果を除いても15%を達成しており、その結果、2022年6月に発表した「2026年度の売上高2500億円」という目標も、2年前倒しとなる2024年度(2504億円)に達成したこととしている。
-

富士フイルムの半導体材料は1983年の合弁会社設立と、1984年の静岡工場設立と同工場でのフォトレジストの生産からスタート。以降、さまざまな企業に対するM&Aを行い、ポートフォリオの拡充が図られてきた
「市場の成長を踏まえれば、目標の到達はそれほど無理なことを言っていない」(同)とのことで、その成長をドライブする役割として、CMPスラリー、先端レジスト、そして後工程向け新規材料の3つを挙げる。CMPスラリーに関しては、前工程のみならず、後工程での活用も期待できる。というのも、現在のチップレットや3D/2.5Dパッケージの基板部分の多くがシリコンインターポーザーを用いてパッケージ基板への接続や、チップ間の再配線層(RDL)の形成が行われているが、このプロセスではパターンを形成するのにレジストの塗布やリソグラフィによる露光、CMPによる平坦化などが用いられることとなるためである。
また、レジストについては、ネガ型のEUVレジストを上市、すでに1件、量産案件を獲得済みであることに加え、2~3件ほどの案件も獲得が見えているとするほか、DRAM製造でも案件獲得が見えてきているとする。さらに、同日、PFASフリーのArF液浸レジストを開発したことも同社は発表しているが、通常の製造プロセスに対する代替のほか、メモリなどコストにシビアな製品ではEUVプロセスから一部をArF液浸プロセスに戻すといったこともあり、そうした新たなArF液浸プロセスにおけるレジストのニーズをキャッチしていきたいともしている。
市場拡大が期待される後工程向け材料
そして後工程の新規材料については、「3次元実装やチップレットで革新的な技術開発が進む」(富士フイルム シニアフェローの野口仁氏)とし、中でもSiPのチップサイズの大型化に伴い、シリコンインターポーザー(例えばTSMCのCoWOS-S)から有機インターポーザー(例えばTSMCのCoWoS-R)へとボリュームゾーンが移行していくことが見込まれており、この有機インターポーザーでは製造プロセスがシリコンインターポーザーから変更が必要となり、成長に向けたチャンスが高まるとの見方を示す。
そうした後工程向けの材料技術として同社が開発を進めている1つが、パネルレベルプロセスへの対応に向けたインターポーザー向け「感光性層間絶縁膜フィルム(フィルム型感光性ポリイミド)」。従来、層間絶縁膜としては液状のポリイミドを塗布し、加熱処理(ソフトベーク)すると、配線の有無でアンジュレーション(凹凸)が生じるため、多層化を図る場合、このアンジュレーションが影響して、うまく積層できない可能性が指摘されている。これを液状ではなくフィルムとして一括して貼ることでポリイミド表面の平坦性を向上させることが可能となるほか、大型化にも容易に対応できるようにすることができるとする。フィルムの貼り付けはFPDの製造プロセスでも活用されてきた塗布ラミネート技術をベースとし、SEMI規格に準拠した515mm×510mmや600mm×600mmにも装置を大型化すれば一回の貼り付けによって対応でき、それ以上のサイズについても対応できる見通しだとする。
-

感光性層間絶縁膜材料の概要。液状タイプでも現状のインターポーザーのサイズであれば対応可能ではあるが、大型化していくにつれて均一な塗布が難しくなってくるなど課題が生じることから、均一なフィルムによる貼り付けを提案するという
また、高集積化に伴って熱を逃がしにくくなる先端パッケージに対して「高い熱伝導率を実現する放熱接合材の需要が増加する」(同)との予測から、独自の銅ナノワイヤーを用いた放熱シート(TIM:Thermal Interface Module)も開発。マテリアルズ・インフォマティクス(MI)を活用することで、放熱シートの内部・界面の設計最適化を図れる銅と樹脂のハイブリッドのシートで、銅の持つ高い熱伝導率と樹脂による酸化の防止、そしてチップとの接触部の熱抵抗を下げることを可能としたものだという。同シートは、絶縁性が求められない部分をターゲットにしたものであると同氏は説明するが、絶縁性を有する放熱材料の研究開発も進めており、さまざまな顧客ニーズに対応していくことを目指すとしている。
このほか、有機材料を活用したハイブリッドボンディングの研究など、さまざまな先端パッケージングに必要な要素に対する研究を推進していると同社では説明しており、装置メーカーとの連携なども含め、技術の見極めを進めるなどの取り組みを通じて対応を行っていくとする。
なお、2030年度5000億円の目標の内訳としては、当初、目標を掲げた際は前工程が9割、後工程が1割と見ていたが、この2年間の間に後工程関連材料の需要が急激に伸びてきたこともあり、現時点では前工程7割(3500億円)、後工程3割(1500億円)と、後工程向けの比率を高める形に修正しているという。