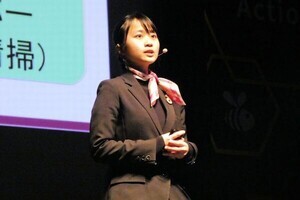サイボウズは5月13日、ノーコード業務アプリ構築ツール「kintone」のユーザーイベント「kintone hive 2025 sendai」を仙台PIT(宮城県 仙台市)で開催した。本稿では、秋田県の彌高(いやたか)神社を母体としウェディング事業などを展開するイヤタカの事例を紹介する。
コロナ禍でウェディング業界は大ダメージ
イヤタカはウェディング事業をはじめ、宴会・仕出し、フロアサービス・調理、レストラン・パティシエ・珈琲豆焙煎、デイサービス、Web制作など、多様な事業を運営している。従業員数はグループ全体で約260人。
高齢化と人口減少が進む秋田県では、担い手不足や事業承継が課題とされる。イヤタカの社長を務める大野恒平氏は東京都出身でありながら、2013年に義父が後継者を探していたことから秋田へと引越し、イヤタカへ入社した。その後、2018年に代表取締役社長に就任。
大野氏が社長に就任して間もなく、新型コロナウイルスの感染拡大によって日常が一変した。結婚式や宴会を事業の柱とする同社も例外ではない。予約のキャンセルが相次ぎ売り上げが激減。約3割の社員が離職したという。
コロナ禍を乗り越えられる強い会社へと転換を図るため、同社はワークフローシステムとしてサイボウズ Officeを導入した。これをきっかけに、kintoneを知ったそうだ。婚礼件数は減少したが、退職者が増えたことで業務負担は依然として減らなかった。しかし、結婚式の少ない時期だからこそ従来の仕事の進め方を変えるチャンスだとして、イヤタカはkintoneの活用を開始した。
イヤタカのkintone活用、3つの事例
同社はkintoneを使い、これまでに「業務改革」「網羅的なデータ管理」「顧客満足度向上」に取り組んだ。まずは業務改善だ。従前から活用していた基幹システムは結婚式の案件管理を目的に導入したものであり、料理の種類や列席人数、使用する会場の情報などを主に管理していた。
そのため、その他の目標(KPI)設定や売上集計、原価率データ、受注管理などはExcelファイルを使って管理していたという。月例会議で5分間使うための資料を作成するのに、5営業日を要している店長もいた。資料作成のプロセスが不明確で、作成作業が重複する課題もあった。
そこで大野氏は、基幹システム、会計システム、人事労務システムのデータをkintoneで吸い上げ、アプリ間のデータを集計できる「krewData」プラグインを使って集約した。これにより、役員会データや月次予実管理、残業時間管理など、さまざまなデータを自動で集計し資料に落とし込めるようになった。これにより、マネージャー層の資料作成の時間が削減され、具体的なアクションに使う時間が創出された。
次に、スタッフが使うツールをkintoneに集約した。それまでは、商談来館予定表や消費者アンケートの結果など、基幹システムに登録しない情報が多数あったという。そこでkintoneを使ってブライダル商談予定表アプリや営業部渉外管理アプリ、仕入れ情報アプリなどを構築。「krewDashboard」プラグインによりダッシュボード化し、蓄積されたデータを可視化した。
その結果、スタッフの業務効率化が図れただけでなく、レコード登録の重要性が社員に伝わり、数値への意識も向上した。また、マネージャー層の社員はダッシュボードを見ながら次のアクションを議論できるようになった。
2つ目の取り組みとして、同社はkintoneを使って網羅的なデータ管理を実現した。サービス業においては店舗運営が最優先となるため、店長は会議直前に報告資料を作成することが常態化していた。データは店舗のPCなどローカル環境にあり、社長の大野氏が見たいデータをすぐには見られない状況だったという。
当時、ウェディング事業に合わせて基幹システムを導入していたため、レストランやデイサービス、Web制作など他の事業にフィットする基幹システムを探していた。そこで大野氏は、各店舗のデータをリアルタイムで把握できることを目的として、kintoneを使った基幹システム構築に着手した。
例えば珈琲豆焙煎事業では、珈琲豆の在庫情報の他、仕入れ情報や焙煎記録を残せるようにした。これを関連レポートとして集計できるようにし、焙煎した豆の情報をすぐに把握できるようになった。
また、介護事業では介護日報アプリを作成。その日の営業状況や午前 / 午後の利用者数、稼働率などを管理できるようにした。本業のウェディングではない事業領域もkintoneアプリでデータを可視化したことで、迅速で的確な経営判断につながっているという。
「kintoneを使って、当社グループ内のほぼすべての日常のデータが可視化された。その結果、私の迅速な意思決定につながり、事業強化にもつながっている。さらに、ベースとなるシステムをkintoneで統一したことで、社員の帰属意識も向上したように感じる」(大野氏)
3つ目の取り組みは、顧客満足度の向上だ。大野氏らは顧客接点を洗い出し、Webフォームなどをkintoneで置き換えることで顧客満足度を高める施策を開始した。
その一例として、ケーキの注文画面を「FormBridge」で構築。FormBridgeとは、プログラミングの知識がなくてもWebフォームを作成できるkintone連携ツールだ。これにより、顧客はWebからの注文がしやすくなると同時に、スタッフが注文をシステムに登録し管理する手間が効率化された。
他にも、インボイス制度によりイヤタカの登録番号(T+固有の13桁の数字)が記載された領収書発行のニーズが高まっていたことから、「kViewer」を使い宴会幹事が自身で領収書を発行できる仕組みを作った。kViewerはkintoneライセンスを持たない外部ユーザーにもkintone内の情報を共有できる連携ツール。
以前は宴会ごとに数十枚~数百枚の発行が必要だった領収書を、幹事が作成できるようになり、社員の手作業での領収書発行の負担が軽減された。ちなみに、税務上の領収書発行上限といった制限も、アプリで管理しているそうだ。
会議のためのデータ集計作業がゼロに、さらに大きな導入効果とは?
イヤタカではこれまでに、60以上のプラグインを使い500以上の業務アプリを作成したそうだ。こうした取り組みの結果、会議に使うデータを集計する時間を0時間にできたという。また、介護事業部の売り上げが対前年比120%増、婚礼成約率が同9ポイント増、子会社の売り上げが同120%増と、定量的な成果が出始めている。
しかし大野氏は「これらの結果は、社員の頑張りによるもの。kintoneはその後押しをしたにすぎない」と強調した。
「最も効果があった」と同氏が話すのは、ダッシュボードなどレコードのアウトプットを見ながら社内で議論ができるようになったことだ。kintoneでリアルタイムにデータを把握できるようになり、日常的に戦略を検討できるようになった。
「一番の成功要因は、コロナ禍をきっかけに社員が『変わらなきゃ』と思いkintoneを前向きに受け入れてくれたこと」(大野氏)
これまでに500以上の業務アプリを作成したという同社だが、kintone活用で工夫しているのは「それは紙の方がいいね」という視点も忘れないことだという。例えばウェディングプランナー間の個別の連絡には、kintoneではなく付箋を使用している。その方が感情や緊急度を伝えやすいためである。
また、婚礼で使用する発注物の確認などは、ペンで印を付けながら作業する方が抜け・漏れが減らせるため、書面での作業を継続している。同社ではkintoneを使う条件として「3人以上で情報共有をする場合」「2つ以上のデータを結合したい場合」に限定しているそうだ。
大野氏は「kintoneに頼りすぎない方が、kintoneの優れた点がより明確になると考えている」と話していた。