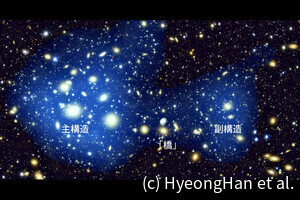国立天文台、東京大学(東大) 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)、名古屋大学(名大)の3者は6月24日、米国主導の次世代天文観測施設「NSF-DOE ベラ・C・ルービン天文台」(ルービン天文台)が稼働を開始し、8m級望遠鏡として世界最大の視野(満月約45個分)と32億画素の観測画像を初公開したと共同で発表した。
-

ルービン天文台が約7時間で撮像した678枚を用いた合成画像。いて座の方向にある2つの散光星雲「M20(NGC 6514)三裂星雲」(上)と「M8(NGC 6523)干潟星雲」。これまでかすかにしか見えなかったこれらの星雲を構成するガスと塵の雲などの細部が鮮明に見て取れる。(c) NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory(出所:ルービン天文台Webサイト)
大規模撮像探査プロジェクト「LSST」は2025年後半に始動予定
ルービン天文台は、米国国立科学財団(NSF)と米国エネルギー省科学局(DOE)の支援を受けて、南米チリ共和国のセロパチョン山に建設・運営されている。同天文台には、口径8.4m(有効口径6.7m)の光学赤外線望遠鏡「シモニー・サーベイ望遠鏡」と、約32億画素の世界最大のデジタルカメラ「LSST(Legacy Survey of Space and Time)カメラ」を搭載。これにより、満月約45個分もの広範囲を一度に観測可能としている。なお天文台の名称は、銀河観測からダークマターの存在を実証した女性天文学者のヴェラ・C・ルービン博士に由来する。
-

LSSTカメラを搭載したルービン天文台のシモニー・サーベイ望遠鏡。夜空に向けた初エンジニアリング観測が行われた2025年4月15日に撮影されたもの。(c) RubinObs/NSF/DOE/NOIRLab/SLAC/AURA/Hernan Stockebrand(出所:すばる望遠鏡Webサイト)
ルービン天文台は、LSSTカメラを用いた大規模撮像探査プロジェクト「LSST」を2025年後半に始動する予定。これは10年間で、南半球の空全体(約2万平方度)を可視光線から近赤外線波長で繰り返し撮像し、データを蓄積する計画だ。銀河や超新星、ダークマターなど、幅広い分野での新たな発見が期待され、太陽系においてその存在が取り沙汰されている新たな第9惑星の発見も視野に入る。
LSSTプロジェクトには、日本からも多数の研究者が参加する。具体的には、2013年に稼働を開始したすばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam」(HSC、約8億7000万画素、視野は満月9個分)を開発・運用してきた国立天文台からは、宮崎聡教授、古澤久徳准教授、内海洋輔准教授、小池美知太郎研究技師らが名を連ねる。また、2025年に本格稼働したすばる望遠鏡の最新観測機器で、約2400天体の分光を一度に行える超広視野多天体分光器「Prime Focus Spectrograph」(PFS)の開発を主導してきたKavli IPMUからは、安田直樹教授や高田昌広教授らが参加。名大 素粒子宇宙起源研究所からも、宮武広直准教授らがプロジェクトに参加する。
内海准教授は、「LSSTの観測開始は、超広域サーベイ天文学、時間領域天文学にとって画期的なマイルストーンです。私自身、15年以上前にHSCの開発に参加し、現在はLSSTの一員として携わって8年になります。20年以上にわたる技術的進展と、すばる望遠鏡およびアメリカを中心としたコミュニティによる国際的な協力の積み重ねが、この新たな人類の“目”を生み出したことに、深い敬意と誇りを感じています。今後、LSSTがもたらす新たな発見と科学の扉の広がりを楽しみにしています」とコメント。
Kavli IPMUの安田教授はLSSTの観測開始について、「東大 木曽観測所のシュミット望遠鏡による写真乾板での観測を皮切りに、木曽モザイクCCDカメラ、スローン・デジタル・スカイサーベイ、すばる望遠鏡のSuprime-CamやHSCによるサーベイ観測など、私はこれまで広視野撮像観測に携わってきました。そしていよいよ、究極の観測プロジェクトとも言える「LSST」が始動します。ハードウェアとソフトウェアの両面における技術の進歩の結晶として、これまでで最も広い視野、最も高い解像度、そして最も暗い天体まで、これまでにない精度で観測可能なデータが得られる時代が到来しようとしています。さらに、同じ領域を10年間にわたり繰り返し観測することによって、これまでにない数の変動天体が発見されると期待されています。未知の希少天体が見つかる可能性もあり、これまでのデータでは明らかにできなかった天体の統計的性質についても、新たな知見が得られるでしょう。しかし、宇宙の本質により深く迫るためには、PFSなどを用いた分光観測が不可欠です。すばる望遠鏡との連携を通じて、宇宙の謎を解き明かすことを楽しみにしています」とした。
名大の宮武准教授は、「LSSTの主要な目標の1つは、星や銀河の形成に欠かせないけれども正体不明のダークマター、宇宙の加速膨張を引き起こすダークエネルギーの謎を解明することです。そのために米国をはじめとする世界中の研究者と準備研究を進めてきました。また、PFSを用いた分光観測はLSSTにおけるデータ解析をより精密に行うために不可欠です。この膨大なデータを緻密に解析することで、人類の知識の地平線を広げることができると確信しています」と述べている。
今後、撮像探査に特化したルービン天文台と、PFSで広視野分光観測が可能なすばる望遠鏡との連携による、さらなる科学成果に期待が高まる。
-

ルービン天文台の初公開画像のうちの1枚。LSSTカメラが捉えたおとめ座銀河団のごく一部(視野の2%)。2つの目立った渦巻銀河(NGC 4411aとNGC 4411b)や、その上に見える合体中の銀河グループ(RSCG 55)、遠方の銀河群のほか、天の川銀河内の多数の恒星などが映し出されている。(c) NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory(出所:ルービン天文台Webサイト)
-

ルービン天文台の初公開画像のうちの1枚(天体名記載版)。おとめ座銀河団の全体を捉えたこの画像は、LSSTカメラの視野の約2.4倍に相当。約1000万個の銀河を含み、これはLSSTが今後10年で撮影する約200億個の銀河の約0.05%にあたる。(c) NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory(出所:ルービン天文台Webサイト)