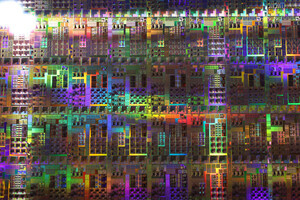経済、そして政治をも揺るがしている半導体。2025年が折り返し地点に差し掛かる中、上半期の米国における半導体業界の重要事項を月別に時系列で見ていこう。
1月:政権交代とDeepSeekによるAI業界への衝撃
1月6日、Anthropicの共同創設者兼CEOのDario Amodei氏が既存のAIチップ輸出規制を支持し、これが中国のAI市場が米国に遅れをとっている理由だと指摘する記事をWall Street Journalに寄稿した。当時、次期大統領に決まっていたDonald Trump(ドナルド・トランプ)氏にさらなる制限強化と抜け穴の封鎖を求めた。
1月13日、大統領退任が数日後に迫っていたJoe Biden(ジョー・バイデン)前大統領が、米国製AIチップの輸出に関する規制を提案。3段階の国別分類システム(制限なしのTier1、購入制限を設けるTier2、追加制限を設けるTier3)を導入するというもの。
1月27日、中国のAIスタートアップであるDeepSeekがオープンソースの推論モデル「R1」をリリース。これが米国、主としてシリコンバレーのAI・半導体業界に大きな衝撃を与えた。
2月:対中輸出規制強化を求める動き
2月3日、Elizabeth Warren上院議員らが、商務長官のHoward Lutnick氏にAIチップ輸出規制のさらなる強化を求める書簡を送付した。その中で、DeepSeekのR1モデル訓練に使用されたNVIDIAのAIチップ「H20」に言及した。
2月28日、Intel(インテル)が280億ドルを投じてオハイオ州に建設する初の半導体製造工場について、2度目の延期を発表。これにより、建設完了は2030年、開業は2031年までずれ込むことになった。
3月:インテルが新体制をスタート
3月12日にインテルのCEOにLip-Bu Tan(リップブー・タン)氏が就任すると発表。2024年12月に退任したPat Gelsinger(パット・ゲルシンガー)氏の穴を埋めることになった。同18日の就任時、Tan氏は「エンジニアリング重視の企業」にすると述べた。
4月:輸出規制強化、インテルの再編
4月1日、インテル CEOのタン氏が改革に着手。非コア事業の分離と、顧客向けカスタム半導体を含む新製品の投入を発表。
4月3日、インテルとTSMCが共同チップ製造事業の暫定合意に達したとThe Informationが報道。TSMCがインテルの製造施設を運営し、20%の株式を保有するという内容だが、2社ともにノーコメント。
4月9日、NVIDIA CEOのJensen Huang(ジェンスン・フアン)氏がトランプ大統領のMar-a-Lago邸宅での夕食会に出席とNPRが報道。フアン氏は米国内のAIデータセンターへの投資に合意することで、H20を輸出規制から除外するという交渉を行った可能性があるという。
4月15日、米証券取引委員会(SEC)の文書から、NVIDIAのH20が輸出ライセンス要件の対象となったことが明らかになった。要件に関連した費用として、同社は2026会計年度第1四半期に55億ドルを予想。TSMCとインテルも同様の費用が予想されることを報告した。
4月22日、インテルが2万1000人以上の人員削減計画を発表した。タンCEOが長年主張してきた経営陣の合理化と、エンジニアリング重視への回帰を目的としたものとなる。
4月30日、以前から輸出規制を支持していたAnthropicがTier 2諸国への制限強化や執行リソースの確保など、米国製チップ輸出規制の支持を表明した。これに対し、NVIDIAの広報担当者は「米国企業はイノベーションに焦点を当て、挑戦に立ち向かうべき」と反論。
5月:輸出規制の影響が表面化、中国政府は批判
5月7日、5月15日に施行予定だった「Framework for Artificial Intelligence Diffusion」(人工知能拡散フレームワーク)について、トランプ政権が独自の枠組みを検討しているとAxiosやBloombergが報道。規制の施行は見送られることになった。
5月13日、米商務省は「Framework for Artificial Intelligence Diffusion(AI拡散フレームワーク)」を正式に撤回。今後、新たな指針を発表するとした。同時に、HuaweiのAscend AIチップの使用は米国輸出規則に反することを強調した。
5月20日、インテルは非コア事業分離計画の一環として、ネットワーク・エッジ部門の売却を検討しているとReutersが報道。同部門は通信機器向けチップを製造する部門で、2024年の売上高は54億ドル。
5月21日、中国商務部は、米国が5月13日に発表した「世界のどこであってHuaweiのAIチップを使用することは米国の輸出規制違反」とする指針に対し、法的措置を示唆する声明を発表した。
5月28日、AMDはシリコンフォトニクスのスタートアップであるEnosemi買収を発表した。同日、NVIDIAはH20の輸出ライセンス要件により、第1四半期に45億ドルの費用が発生し、第2四半期には80億ドルの収益減を予想していると報告。
6月:インテルの組織再編が続く、AMDは買収戦略を進める
6月4日、AMDはAIソフトウェアを提供するスタートアップのBriumを買収。Briumは、NVIDIA向けに設計されたAIソフトウェアを他のハードウェアでも動作する技術を持つ。
6月6日、AMDはAI推論チップを開発するUntether AIのエンジニアチームを取得。
6月13日、NVIDIAのフアンCEOは、H20に対する新たな輸出ライセンス要件の影響を受け、今後の収益・利益予測から中国市場を除外すると発表した。
6月17日、インテルが7月よりIntel Foundry部門で大規模な人員削減を開始すると発表。15~20%にあたる従業員を削減するという。
6月18日、インテルが4人の新しい幹部を発表した。同社が目指す「エンジニアリング・ファースト企業」への転換を加速するため、最高収益責任者(CRO)にGreg Ernst氏、そのほか3人が新設のエンジニアリング職に就いた。
これら、米国半導体業界の2025年上半期の動きは6月19日付のTechCrunchが報じている。
対中投資規制の影響
半年という短期間にも関わらず、米国の半導体業界ではさまざまな動きがあった。2022年から開始された米国の中国に対する半導体輸出規制は、今年の1月から半導体、AI、量子分野における中国への投資を制限する対中投資規制が発効し、5月にはその影響が表面化するなど対立は続きそうだ。
ここ数年の落ち込みが目に付くインテルは、再建に向けたテコ入れに取り組んでいる。しかし、現状を打破するようなインパクトのあるニュースは乏しく、オハイオ州に建設する初の半導体製造工場は稼働時期がずれ込むほか、事業売却や昨年に引き続き4月、6月と立て続けに人員削減を発表するなどネガティブなものが目立つ。一方、こうした思い切った組織・事業再編を進めていくことで、エンジニアリング・ファースト企業への転換を急ぐ心理も理解できないわけではない。
NVIDIAは輸出ライセンス要件の影響を受けている。5月末に発表された2026年度第一四半期の決算は売上高が前年同期比69%増の441億ドル、営業利益は同2%増の216億ドル、純利益は同26%増の188億ドル。H20の輸出規制の影響で引当金などの費用がかさみ、営業利益・純利益ともに過去最高は更新できなかった。また、CEOのフアン氏は「中国市場の重要性を過小評価することはできない。中国は世界最大のAI研究者がいる」などとし、暗に米国は対中AI規制を見直しする必要があると主張している。
その反面、AMDは対NVIDIAとしてシリコンフォトニクス、AIソフトウェアのスタートアップを次々と買収するなど、競争に向けた準備を進めているようだ。先日、米国で行われた自社イベント「Advancing AI 2025」において、3nmプロセスを採用したHPC(スパコン)向けGPU「Instinct MI350」を発表するなど、攻勢を仕掛けている。