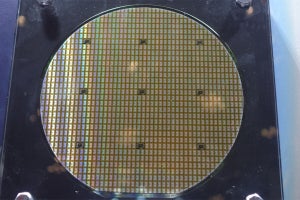STMicroelectronics(STマイクロエレクトロニクス)は4月10日、グローバルな製造拠点の再構築に向けたプログラムの詳細を発表した。
競争力の強化に向けて製造拠点の役割を再編
この取り組みは、競争力のさらなる向上、世界的な半導体リーダーとしての地位の強化、技術研究開発・設計・量産にわたる戦略的資産のグローバルな活用によるIDMとしての長期的な持続可能性の確保を目指したもの。具体的には、300mmシリコンウェハ工場および200mm SiCウェハ工場などの将来に備えたインフラへの計画的投資を優先し、それらが重要な規模に達することが1つ目の目的として掲げられている。
2つ目の目的としては、レガシーの150mmウェハによる製造能力と成熟した200mmウェハでの製造能力の生産性と効率を最大化することとしている。
同社では既存のすべての拠点を引き続き活用すると同時に、一部の拠点には長期的な成功をサポートするための再定義されたミッションを与えるとしており、持続可能性に継続的に焦点を当てながら、技術研究開発、製造、信頼性、および認定プロセスのさらなる効率化のためにAIや自動化を導入し、事業全体で使用される技術のアップグレードに向けて投資を進めていく予定だと説明している。
アナログとパワーを推進する役割を担うイタリア拠点群
2025年~2027年の3年間にわたる製造フットプリントの再構築では、フランスではデジタル技術、イタリアではアナログ技術とパワー技術、シンガポールでは成熟した技術といったSTの補完的な製造エコシステムを設計・強化していく方針。これらの事業の最適化は、製造能力をフルに活用し、グローバルな競争に打ち勝つための技術的差別化を推進することを目的としたもので、イタリアのアグラテ工場では、300mmウェハ向上を同社のスマート・パワーおよびミクスド・シグナル技術の主力量産工場化に向けて、継続して規模の拡大が図られていく予定。同社の計画では、2027年までに現在のウェハ製造能力を週あたり4000枚まで倍増させ、市況に応じて、モジュール式拡張により週あたり1万4000枚まで増加させる予定だという。また、300mmウェハに重点を置くことに伴って、同工場にある200mmウェハ製造施設はMEMS製造へと転換されることとなるという。
また、同じくイタリアのカターニャ工場は、パワーおよびワイドバンドギャップ半導体の中核拠点としての役割を担う。現在進められている新しいSiCキャンパスの開発は計画通りとのことで、200mm SiCウェハの生産は2025年第4四半期より開始される予定だという。また、同工場における現在の150mmウェハおよび、電気ウェハ・ソーティング(EWS)をサポートするリソースは、GaN-on-Siを含む、200mmのSiC/Siパワー半導体への製造に向けられる予定だという。
ロジックの進化を支える役割を担うフランス拠点群
一方、同社のデジタル製品エコシステムの中核である仏クロル工場の300mmウェハ製造施設は、計画としては2027年までにウェハ製造能力を週あたり1万4000枚まで増加させ、市況に応じて、モジュール式拡張により週あたり2万枚まで増加させる予定だという。また、大規模なEWSと先端パッケージング技術をサポートすることを目的に、同工場の200mmウェハ製造施設を転換することで、現在、欧州には存在しない光学センシングやシリコンフォトニクスを含む、次世代の先進技術にフォーカスした活動を進めるとしている。
さらに、仏ルッセ工場は、引き続き200mmウェハの製造を担当し、その他拠点からの追加生産量を再配分することで、既存の製造能力をフル活用し、効率を最適化していくほか、仏ツール工場も、特定技術に向けた200mmシリコンウェハの製造を継続する一方、レガシーの150mmウェハの製造については他拠点に移管するが、GaNのエピタキシャル成長に関するコンピテンスセンターとしての機能は継続するとしている。また、ツール工場では、チップレットの主要な実現技術の1つであるパネルレベル・パッケージングといった新たな活動も開始する予定だという。
このほか、シンガポールのアン・モ・キョ工場も引き続き200mmシリコンウェハでの製造に注力することに加え、150mmシリコンウェハの製造能力が集約される拠点となるとするほか、マルタのキルコップ工場にある大規模テストおよびパッケージング工場は、次世代製品をサポートするための重要な先進自動化技術を追加するアップグレードが行われる予定だとする。
グローバルでの人員減を予測
なお、同社ではこうした今後3年間での製造フットプリントの再構築に際し、労働力の規模や必要なスキルは進化していくとの見通しを示しており、例えば先進的な製造業では、反復的な手作業を伴う従来の工程から、工程管理、自動化および設計といった役割に重点が移行していくことから、各国で適用される規制に従うとともに、従業員代表との建設的な対話と交渉を継続的に行い、自主的な手段を通じてこの移行を進めていくと説明。2025年4月10日時点では、同プログラムによって同社の従業員数は通常の減少に加えて、全世界で最大2800名の自主的な退職が見込まれているとのことで、これらの変化は主に2026年および2027年に発生することが予想されるとしている。