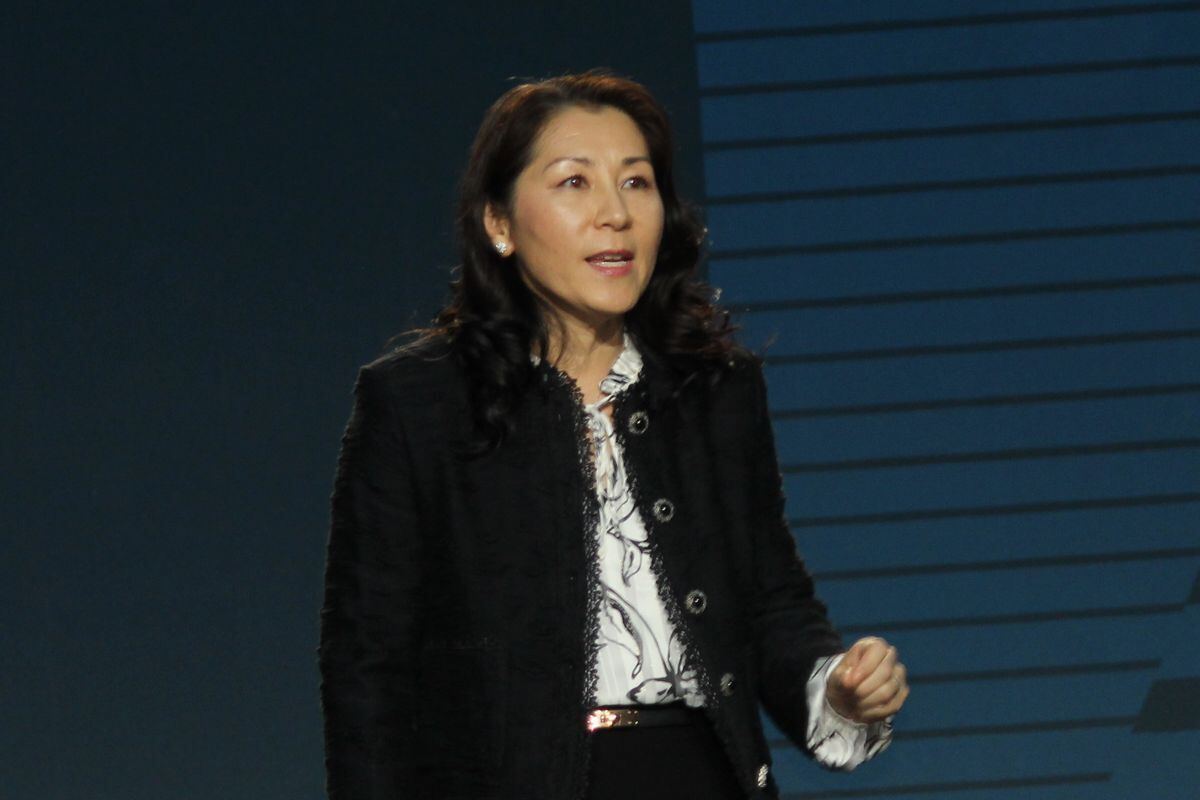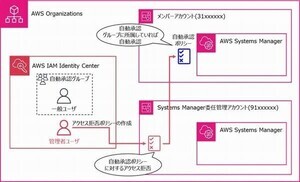日本オラクルは2月13日、年次イベント「Oracle CloudWorld Tour Tokyo」を開催した。オープニング基調講演は「AIがもたらすビジネス価値」というタイトルと題して行われた。
米オラクル 最高情報責任者(CIO) エグゼクティブ・バイスプレジデントのジェイ・エバンス氏は、「オラクルはAIを推進する絶好のポジションにいる。なぜなら、オラクルの顧客はAIの活用により測定可能な価値を見出しているから」と話を切り出し、同社のAI戦略について語った。
エバンス氏は、「AIは有意義で測定可能なROI、イノベーションを生み出すことが期待されている。魔法の杖はないが、高度に統合されたプラットフォームにより、コンプライアンスが確保された形でAIを導入できたら実現できる」と述べた。
そして、「われわれはミッションクリティカルなシステムにふさわしい完全なプラットフォームを提供できる。オラクルのAIアプローチはインフラからデータモデル、アプリまですべてにAIを導入していること。複雑なタスクに対応できるAIエージェントをリリースしたが、これにより、複雑なタスクも短時間で処理できる。これが、オラクルが競合に対し大きくみずをあけている点」と、エバンス氏は同社の優位性を強調した。
最後発だから、最先端のテクノロジーで構築できたOCI
取締役 執行役 社長の三澤智光氏は、「OCI(Oracle Cloud Infrastructure)は最後発であるぶん、最先端のテクノロジーでつくられており、他社とは異なる特徴を持ったクラウドを提供している」と述べ、同社のクラウドサービスを活用している野村総合研究所(NRI)、富士通、本田技研工業(ホンダ)の取り組みを紹介した。
NRIは同日、東京と大阪のデータセンターに導入した「Oracle Alloy」を活用し、高度なガバナンスやセキュリティ、データ主権要件に対応するセキュリティサービスおよびAIプラットフォームを提供することを発表した。
富士通は昨年に「Oracle Alloy」を導入し、国内のデータセンターの透明性を確保した安心・安全なデータ管理を支援する「Fujitsu Uvance」の「Hybrid IT」のクラウドサービスとして、運用コンサルティングサービスを提供することを発表。
ホンダはOracle Fusion Cloud Procurementを導入して、4社11拠点にわたる間接材の購買プロセスを統合、その結果、年間バイヤー20名程度のコスト削減を実現し、データドリブンで意思決定できるようになったという。
NRIの取り組みは別の機会に取り上げるとして、以下、富士通とホンダの取り組みを紹介する。
Oracle Alloyを導入してソブリンクラウドを提供する富士通
富士通と米オラクルは2024年4月18日、日本の企業・団体のデータ主権要件に対応するソブリンクラウドの提供に向け、戦略的な協業を発表した。この協業の下、富士通は同社のデータセンターに「Oracle Alloy」を導入し、ソブリンクラウドを提供する。
富士通 執行役員SEVP システムプラットフォームビジネスグループ長 古賀一司氏は、ソブリンクラウドについて、「4月から提供が始まるが、すでに150社から引き合いがあり、初の受注ももらった」と、日本企業においてソブリンクラウドに対する注目が高まっている実態を明らかにした。
古賀氏は、ソブリンクラウドが求められる企業やシステムとして、「データの秘匿性を必要としている企業」「クラウドでは対応できないミッションクリティカルなシステム」「パブリッククラウドに移行したが、トラブルで困っている企業」を挙げた。
また、今年3月からは、運用コンサルティングサービスや「Fujitsu Cloud Managed Service」を「Oracle Alloy」によるクラウドサービス向けにも提供する。
古賀氏は、「ミッションクリティカルなシステムのコンサルティングは、責任を分解した考えではうまくいかない。われわれは業務とインフラを意識して設計する」と説明した。
「Fujitsu Uvanceでは、顧客の業務がわかるSEとクラウドがわかるエンジニアが一緒にコンサルティングを行う。オンプレミスと同等のサポートを提供し、ミッションクリティカルなシステムの富士通のソブリンクラウドへの移行を支援する」(古賀氏)
古賀氏は今後の展望として、「当社のクラウドにオンプレミスと同様の分散環境を構築したい。当社のソブリンクラウドでは、マルチクラウドからオンプレミスまでサポートする」と語った。
間接材の購買業務のプロフィットセンターへの変革目指すホンダ
本田技研工業(ホンダ)サプライチェーン購買本部 本部付 サプライチェーン改革 LCA/RC調達領域責任者 大澤裕一氏は、「現場目線で購買業務の改革に取り組んでいる」として説明を行った。
現在、自動車業界ではソフトウェアデファインドビークル(Software Defined Vehicle:SDV)の実現に向けて変革が進められている。SDVは開発プロセスにおいて、ソフトウェアを定義したうえでハードウェアを決めていくクルマづくりを指し、同社は「ソフトウェア・デファインド・モビリティ(SDM)」と呼んでいる。
大澤氏は「ソフトウェアデファインドによって、車の作り方がまったく変わる。われわれは、今を第二の創業期と呼んでいる」と語り、全社を挙げて変革に取り組んでいることをアピールした。
同社の購買は直接材と間接材の2種類に分けられるが、大澤氏は間接材の購買の変革を紹介した。間接材にはファシリティ、消耗品、サービス、物流、人材派遣の費用などが含まれるが、当初、グループ全体で間接材の購買を担う専門組織がなく、プロセスがバラバラだったという。
間接材の購買を行っている4社のデータを集計したところ、7000億円を支出していることがわかり、コンサルタントからは100億円から200億円の削減が可能という指摘を受けたそうだ。
これより、HONDAは間接材の購買の改善を経営課題ととらえ、5年前に改革プロジェクトを立ち上げた。「バイヤーは100人おり、1時間に5件程度処理していたことになる」と大澤氏。
そこで、業務の可視化・標準化・効率化を図るため、Oracle Fusion Cloud Procurementを導入した。その結果、「誰が何を買っているかがすぐにわかるようになり、データドリブンで意思決定できるようになった」と、大澤氏は述べた。
具体的には、eコマースを連携して可能な限り通販で購入するようにし、年間20名分程度のコスト削減を実現したという。
「購買は事務作業が中心であり、バイヤー1人につき2000万円程度かかっているので、このコストを削減することで、効率よく経営に貢献できる。購買をコストセンターからプロフィットセンターに変革することを目指している」(大澤氏)
ちなみに、購買の業務を変革する中で、4社11拠点のプロセスを統合したが、システムを合わせる点で苦労したそうだ。
大澤氏は今後、「データの揺らぎに対してAIを活用することで、分析できるデータを整備したい」と述べた。また、同氏はOracle Fusion Cloud Procurementのユーザー会の幹事を担っており、「ユーザー会で、ベストプラクティスなどを共有できるようになったら、日本企業の競争力が高まるのではないかと期待している」とも語っていた。