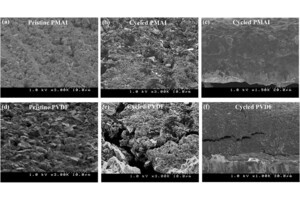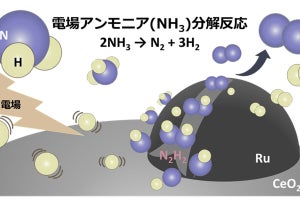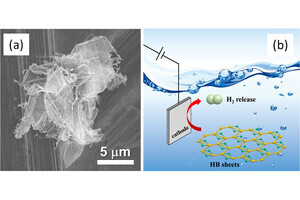東北大学と東京理科大学(理科大)の両者は12月11日、原子レベルでの構造制御により、ファラデー効率(加えた電流が、目的の生成物を作るために実際に使われた割合)が約44%という高い選択率でメタノールを製造できる触媒の開発に成功したと共同で発表した。
同成果は、東北大 多元物質科学研究所の根岸雄一教授、理科大の川脇徳久講師、同・Sourav Biswas助教、同・田中智也大学院生(研究当時)、同・新行内大和大学院生、同・神山真帆学部生らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、ナノサイエンス/テクノロジーに関する全般を扱う学術誌「Small Science」に掲載された。
環境問題の観点から、二酸化炭素(CO2)を常温常圧下にて有用な炭化水素化合物に変換できる電気化学的CO2還元触媒の開発が強く望まれている。中でも、需要や付加価値が高いことから、メタノールを製造する触媒の開発が注目されている。
CO2を還元し、さまざまな炭化水素化合物を生成する触媒用の金属として知られるのが銅だ。銅触媒の中では、配位子により保護され、1原子単位で精密合成可能な銅ナノクラスター「Cu NC」が最近注目を集めている。Cu NCは特殊な電子・幾何構造を持つため、主たるCO2還元生成物やその選択率を制御することが可能だ。その一方で、表面における欠陥部位がCO2還元生成物に与える影響については未解明となっている。そこで研究チームは今回、原子レベルでの構造設計により、Cu NCの欠陥部位の制御を試みたという。
今回の研究では、従来の銅ナノクラスター「Cu58 NC」([Cu58H20(SPr)36(PPh3)8]2+、SPrは1-propanethiolateの略、PPh3はtriphenylphosphineの略)の合成法から還元方法を変化させることで、配位子の「トリフェニルホスフィン」が1つ少なく、欠陥部位を持つ「Cu58-I NC」([Cu58H20(SPr)36(PPh3)7]2+)の合成に成功したとする。その結晶構造が解析された結果、Cu58-I NCにおいては、単純に配位子が欠落しているだけでなく、配位子シェルなどにゆがみが生じていることも明らかにされた。
こうした欠陥部位の存在は、触媒活性に影響を与えることが期待されるという。そこで、それぞれのCu NCをカーボンブラック上に担持させ、CO2流通下にて定電位電解が行われ、生成物のファラデー効率が求められた。その結果、Cu58-I NCは、Cu58 NCでは生成しないメタノールを約44%の高い選択率で生成することが判明(メタノール合成に使われなかった残りの電流は、主に水溶液中の陽子を水素に変換したり、一酸化炭素(CO)を生成するのに消費されていると考えられる)。
また、Cu58-I NCを触媒として用いた場合には、Cu58 NCを用いた場合に高い選択率で生成するCOの選択率が大きく減少していることもわかったとした。メタノールを製造する従来の水蒸気メタン改質法や乾式改質法は、高圧および高温条件下で温室効果ガスを排出する原因となることが課題だ。また研究チームは今回の成果に対し、メタノールは重要な基礎化学品原料の1つであるが、それを常温常圧下にて電気化学CO2還元にて作ることは大変困難なため、驚くべきこととしている。
主たる生成物に差が生じる理由について、密度汎関数理論(DFT)計算による検討が行われたところ、Cu58-I NCの方がCOOHとCOの生成に優位であることが確認された。続く反応については、Cu58 NCではCHOの生成よりもCOの脱離が容易に生じるのに対し、Cu58-I NCではCHOの生成がCOの脱離と競合することが突き止められた。これらの結果から、Cu58-I NCはCu58 NCと比べてCOやCHOが強く吸着するため、メタノールが生成し易いと解釈されたという。Cu58 NCでは、COの吸着が弱く、生成したCOが容易に脱離してしまうため、生成物にはCOしか含まれていないことが考えられるとした。Cu58-I NCにはCOが強く吸着する理由については、欠陥部位が存在することで構造にゆがみが生じ、これによりCuの電子密度が変化することに由来していることが突き止められた。
なお、他の構成原子数のCu NCについても、欠陥部位を作り出すことが可能とのこと。研究チームは、原子レベルでの精密な構造制御を行うことで、メタンなどのより有用な炭化水素化合物を高効率的で生成し得る新たな機能性材料の創出により、脱炭素社会の実現にさらに一歩近づくことが期待されるとしている。