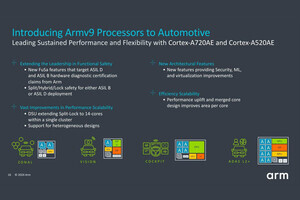パナソニックグループで車載機器の製品・技術開発を手がけるパナソニック オートモーティブシステムズ(PAS)が11月12日、長野・松本市にある松本工場を報道陣に初公開。あわせて生産リードタイムの半減など、新たな取り組みを紹介した。
-

松本工場では、車載機器の製品・技術開発が行われている。左上から時計回りに、同工場でつくられている車載インフォテインメント機器(IVI)、ストラーダシリーズのカーナビ展示デモ、工場内でパーツなどを積んで走るAGV(Automatic Guided Vehicle:無人搬送車)、松本工場のフロントの様子
松本工場は、パナソニックグループの車載モノづくりをけん引する“グローバルトップランナー”工場と位置づける、同社最大の国内生産拠点。敷地面積は東京ドーム1.5個分に相当する69,000平方メートル、建屋面積は27,400平方メートルにもなる大規模工場だ。
1974年4月の操業開始から今年(2024年)で50周年を迎えたことを機に、同工場で報道関係者向けに見学会を開催。松本工場長の粟澤学氏が、現在の事業内容や取り組みの詳細などを説明した。
同工場では主に、カーメーカー向けのIVI(In-Vehicle Infotainment:車載インフォテインメント機器)の多品種少量生産に対応するとともに、カーナビやディスプレイオーディオ、運転席用のフルディスプレイメーターやHUD(Head Up Display)、PND(Portable Navigation Device)、電子ミラー、後部座席向けのRSE(Rear Seat Entertainment)といったさまざまな車載機器の生産を手がけている。
IVIとは、ソフトウェア化が著しい昨今のクルマの車両情報や、エンタテインメント関連の機能をまとめて制御する装置のことを指す略語だ。ユーザーがふだん目にすることは画面上の表示くらいで、いわば“クルマの縁の下の力持ち”的な存在だが、カーナビや通信機能、車載情報連携、スマホ連携機能などを備え、車室内に置けるインフォメーションとエンタテインメントをつかさどる機器なので、開発・生産の規模も大きなものになる。そこで、PASの主力工場である松本工場がその生産を担っている、というわけだ。
ちなみにPASは8月1日、三重・松阪にも新拠点をつくり、日本市場向けのカーナビ生産を皮切りに、今後さらなる高効率な車載機器の生産拠点をめざして稼働中。サプライチェーンリードタイムの短縮化を追求した立地で、人と機械のハイブリッド生産方式によって約25%の省人化を実現しているという。
IVIのような車載機器も含めて、自動車業界は今、“100年に一度の変革期”を迎えている。走る・曲がる・止まるといった基本機能に加え、移動空間の快適性も追求し、スマートフォンのように“ソフトによってクルマが進化する時代”になってきているのだ。
ソフトウェア化が進む車載コックピット領域では、異業種からの参加など競争も激化。PASのIVI事業はその中でも“グローバルトップクラスのシェアを握っている”とアピールしている。一例としてグローバル市場での数量シェアは、ディスプレイオーディオは世界1位(28%)、IVIシステムは世界2位(22%)になるとのこと(いずれも富士キメラ総研調べ、2022年度実績)。
そうした車載事業を支えるために、モノづくりの現場はそれまでの大量生産から「超多品種・少量生産」へと変化。工場長の粟澤氏によれば「数年前はひとつの車両に対して2〜3機種のナビを搭載できるようにしていたのが、昨今では消費者ニーズの多様化などもあり、10〜20機種以上のバリエーションへと増えてきている」とのこと。
バリエーションが増える理由は、ディスプレイサイズやハンドルの左右位置が市場ごとに異なっていたり、IVI本体に実装する基板(CPUやオーディオ、インタフェース、スイッチなど)についても、実装工程における新種が増えていく……といった事情があることも挙げていた。
こうした需要に応えるため、松本工場で生産するIVIは700品番ほどに膨れ上がり、生産ロットは100台以下が7割、生産ラインにおける機種切り替えは3,000以上と「グローバル拠点の中でも切り替え頻度が一番高い」(粟澤氏)という状況にあるそうだ。
ただ、新機種の立ち上げや切り替え多発が起こると、生産ラインが止まって稼働率が低下し、生産能力が落ちることが懸念される。
粟澤氏はこうした課題について、「松本工場ではこれも逆にビジネスチャンスと捉え、変種変量にジャストインタイムで対応する追従力と、高効率生産を実現。経営的にもキャッシュを創出していく。これもモノづくりに求められる価値として取り組んでいきたい」と述べ、設計・製造の連携や生産計画などのデジタル化によってさまざまな対応を進めていることを明らかにした。
そのひとつが「製造リードタイムの実測による可視化」。生産現場にあるデータのうちタイムスタンプを活用し、工程間のどこにボトルネックがあるのか、どこに手を打ってその効果をどう確認するか、といった現場の可視化の仕組みをつくり、削減しにくいリードタイムを削って中間在庫の抑制をめざすというものだ。
また、需要と連動した生産計画として「後補充生産方式」を2023年から導入したのも新しい取り組みのひとつだという。
生産計画は従来、顧客から週一回受け取る内示情報をもとに作っており、現場の変動ができるだけ起きないよう15日先の1週間の生産計画を毎週作っていた(いわゆる“3週ロック”)が、生産にあたって急ブレーキがかかるようなことが起きた場合、結果的に完成品在庫を過剰に持ってしまうという問題があった。
そこで、同工場では後補充生産方式を新たに導入。完成品倉庫の販売実績をもとに毎日8日先の1日分の生産計画を確定させるというもので、急な減産に対して急ブレーキ、つまり生産調整が行えるようになり、完成品在庫の抑制ができるようになったという。
顧客視点からみても、今までは注文してから工場での生産開始まで15日かかっていたのが、8日前の注文でも材料や在庫次第で生産可能になるメリットがあるということで、サプライチェーンリードタイムが半減した効果は大きいようだ。
ほかにも、顧客と生産現場で直接やりとりを交わしてつながりを強化し、現場にもフィードバックしていく“カイゼン”活動を実施。さらに工場内の人とモノの動線を最適化し、作業の後戻りをなくすといったことを事前に検証するツールを活用するなど、製品設計と工程設計を同時に進めることで開発・生産のリードタイム短縮をめざすといった取り組みも進めているとのこと。
松本工場ではこのほか、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量・吸収量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの取り組みも進行中。2022年からは毎年、前年比3%ずつ省エネ効果によるエネルギー削減を進めており、さらに2025年からは再生可能エネルギーを自社でまかなう割合を10%とし、2050年にはその再エネ率を自社100%まで引き上げる目標を掲げている。
取り組みの一例としては、カーポートタイプの太陽光発電による再エネ稼働を2024年7月から開始しており、同年8月の再エネ率実績は2.87%になったとのこと。また、敷地内に4つある棟のうち、ひとつの屋根にオンサイトPPAを導入し、2025年度から稼働予定。これによる再エネ率は5.9%となることを見込んでいる。