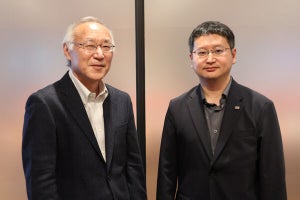非鉄金属等の基礎素材から、超硬工具・加工ソリューション、電子・半導体関連部品・材料、資源リサイクル、再生可能エネルギー発電など、多角的に事業を展開している三菱マテリアル。
同社は2020年にスタートした中期経営戦略において、デジタル化戦略「MMDX(三菱マテリアル デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション)」を立ち上げ、DXに取り組んできた。「MMDX」の取り組みの一つにデータ基盤の構築がある。
DX推進部CDO・DX推進部長を務める端山敦久氏が、Snowflakeの年次カンファレンス「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2024」で、データ基盤の整備をはじめとする「MMDX」の活動について講演を行ったので、そのポイントをお届けしよう。
DX推進に向けデータ基盤を整備
端山氏は、MMDXについて「ビジネスをどれだけ変革させるかが大事。だから、あえてビジネスという言葉を入れて発信している」と語った。「MMDX」では、データとデジタル技術を活用し、ビジネス付加価値の向上、オペレーション競争力の向上、経営スピードの向上を3つの柱に据えている。
2020年度から2022年度にかけては、「実行初期段階」として、まずは他社に追い付くための施策を講じ、追い越すための基盤を作ってきた。これら3本柱を実現するための基盤として、「データ基盤の整備」と「変革を支える人材強化、風土改革」に取り組んでいる。
ただ、MMDXが開始から2年以上経つ中、ものづくりの強化と従来テーマの着実な実行を実現するため、テーマの再編成や体制強化を実施し、「MMDX2.0」として、新たなフェーズへジャンプアップした。
「MMDX2.0」では、「事業系DX」「ものづくり計DX」「研究開発DX」「全社共通DX」「基幹業務刷新」を柱としている。端山氏は、「当社は製造業なので、顧客接点の強化にばかり取り組んでいると、製造の人が他人事になってしまう。だから、2.0では研究開発にもフォーカスしている」と述べた。
「全社共通DX」として、取り組んでいるのが「データ利活用基盤」「業務効率化」「人材育成・風土改革」だ。
旧データベースの性能・運用の課題を解決するためSnowflakeを選択
データ基盤は、「つなぐ」をコンセプトとして、同社の価値創造への貢献を目指し構築された。当初利用していたデータベースが性能と運用面に課題を抱えていたことから、その解決策として、データクラウド「Snowflake」が採用された。
元のデータベースは、性能面で「全社からの同時アクセス・集中への対応」「複雑なクエリ処理などの高負荷が及ぼす影響」といった課題を抱えていたという。こうした課題に対し、Snowflakeは高負荷に耐えうるアーキテクチャを備えており、リソースの自動スケールによって同時並列の実行性を上げることで、対処できる。
端山氏は、Snowflakeの運用面でのメリットとして、「ニアゼロメンテナンスによる運用負荷の軽減」「アカウント分離による課金・コントロール分離」を挙げた。
そして、データを集めるために体制を構築するとともに、複数の手段を試行錯誤し、現在はETL、データ連携、エッジを活用して社内外のデータを収集している。「各工場からエッジやIoTのデータを収集して、新しいことにチャレンジしている」と端山氏。
集めたデータは事業カンパニーと共創できるよう、活用しやすいような形で整備している。具体的には、全社データウェアハウス(DWH)に加えて、カンパニー専用のSnowflakeデータマートを構築することで、カンパニー独自のルールや課金体系の下、スピード感のある運用が可能になった。
さらに、Snowflakeのデータ共有機能を利用することで、全社DWHのデータをリアルタイムかつ低コストで利用できるようになった。
次々と生まれる、業務に役立つ多様なデータ活用
こうした環境の下、データ活用基盤を利用した多様なユースケースが創出し始めているという。端山氏はその例として、「金属資源データの集約と活用」と「工場IoTデータの活用」を紹介した。
金属資源データの集約と活用
同社は金属資源の買い入れを行っているが、金属の含有率において、顧客が申告した値と実際の値で乖離があるという。乖離が大きいと分析作業に時間がかかるうえ、含有率が下がると簿価にも影響が出る。
そこで、分散していた金融資源の受入・買鉱データを集約して、これらから算出した見込み量を活用して、分析の結果の差を減らし、在庫管理の精度を向上しているという。
工場IoTデータの活用
また同社では、工場の設備に関するIoTデータが月間50億件も発生していたとのことで、使わない手はない。もともと、ローカルでデータを収集して活用としていたが、データ量が多くて取り出す手間もかかるため、今は半自動でIoTデータをSnowflakeに流し込んでいる。
端山氏は、「本来は、クレンジングしてからデータを格納したほうがよいのだが、工場が多いのでそれでは大変。まずはシームレスにデータを流し込んでいる」と説明した。
Snowpipeを使って非構造データを取り込むとともに、柔軟性を確保しているほか、データ共有機能を活用してDWHとデータマートの構造分離とリアルタイム性を両立しているという。
こうした仕組みを整えたことで、あるエリアの収益性が数カ月低下しているのでアクションを打つなど、工場で発生したデータを業務に生かせるようになった。
全社データ基盤構築における3つのポイント
端山氏は、異なる事業、異なるモノづくりの現場から多様なデータを集め、つなぎ、生かすことを実現するためのデータ基盤を構築するポイントとして、以下の3つを挙げた。
- 人の力、体制を整える
- 関係者を巻き込み、共に創り上げる
- データをためて使って当たり前という機運をつくる
人材育成においては、「共通デジタルリテラシー教育(共通教育)」を全社に展開済みであるほか、2030年度までに2500名規模のデジタル専門人材の育成を目指している。
端山氏は、「会社の風土や意識を変えて行かないと、DXは経営が求めている領域まで達しないと考えている。データを使える場所を広げて、社員のマインドを変える取り組みも行っていきたい」と語った。
今後は、データで価値を創造する「モノづくり企業」を目指す、データの収集と全社的効果創出のための環境整備を進める計画だ。端山氏は、データのセレクトに用いるなど、AIの活用についても意欲を示していた。