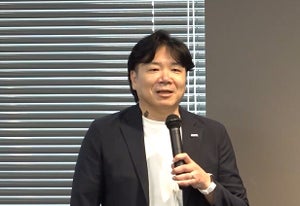パナソニック ホールディングス(HD)で業務プロセス変革と生成AI活用が進んでいる。同社が取り組む全社DX(デジタルトランスフォーメーション)プロジェクト「PX(パナソニックトランスフォーメーション)」は2024年7月で3年目を迎えた。同社は9月17日、PXに関する合同取材会を開き、執行役員 グループCIO(最高情報責任者)の玉置肇氏が、PXのこれまでの実績や今後の展望について説明した。
パナソニックのDXプロジェクト「PX」とは?
PXプロジェクトは「各事業のDX支援とグループ全体のIT経営基盤の底上げ」を目的に2021年7月に始動した。情報システムだけでなく、全社の業務プロセスや商慣習、そして組織風土を変革することを目指している。2023年3月には最高意思決定会議である「グループ経営会議」のメンバーによって、PXにまつわる「7つの原則」が策定された。
玉置氏は「情報システムを変えるだけではDXは失敗する。システムが関わる業務プロセス、社内の慣習、契約形態の在り方の変革を、すべての層で実施している」と同プロジェクトの狙いを説明した。
米ネバダ州のEV電池工場、DXで設備補修50%削減
PXの成果は出ている。業務プロセスの変革の観点でいえば、製造現場でのERP(統合基幹業務システム)導入による業務の見直しや標準化が進んでいる。中国では3年間で13拠点に独SAPのERP「SAP S4/HANA」を標準機能で展開し、ある拠点では年間の間接業務簡素化で8400万円、製造ロス削減で7200万円の削減を実現し、出荷リードタイムは3日間の短縮に成功している。
調達業務におけるプロセスの見直しも進んでいる。設計工程にて「汎用部品の推奨・誘導」を実装することで、非推奨部品の採用を21%削減し、設計の手戻りロスを50億円削減できた。
同社が戦略事業に位置づけるEV(電気自動車)向け電池を生産する米ネバダ州の主力工場もDX改革を掲げる拠点の一つだ。材料手配から保守まで幅広くスマート工場化を進めており、生産設備の故障や不具合の発生を延べ約500万件防ぎ、補修業務の作業数を2021年比で50%削減した。「デジタルを積極的に活用して、業務やサービス、取引先との仕事の在り方を変えている」(玉置氏)
生成AI活用の現在地、約18万人まで展開
パナソニックHD全社における生成AIの積極的な活用も注目に値するだろう。同社は2023年4月に、他社に先駆け米OpenAIの「ChatGPT」を活用した生成AI「PX-AI」を国内従業員約9万人に一斉に導入した。同年10月までに中国を除く海外従業員を含めた約18万人まで展開し、2024年8月現在、最新モデル「GPT-4o mini」へアップグレードさせ、テキストだけでなく画像・音声生成の利活用まで広げている。
同社は現在、事業部門全14部門から寄せられた71テーマの要望に応えるため、LLM(大規模言語モデル)の社内活用で重視されるRAG(検索拡張生成)の精度向上や商品・サービス実装に取り組んでいるところだ。
また、同社専用のLLMの開発も進めている。AI開発のストックマークと協業し、性能の指標となるパラメータ数で1000億のモデルを今秋までに構築することを目指している。多くの企業が利用する汎用型モデルや、70~130億パラメータの小型モデルとの差別化を図る。玉置氏は「多様な生成AIサービスを活用し、業務効率化につなげていく」と強調していた。
玉置氏はこれまでの取り組みを振り返り、「取り組み自体は及第点をとったと思うが、成果に関しては、厳しく採点すれば10点くらいだ。事業部ごとに成果の濃淡が存在し、まじめに取り組んでいるところもあれば、まだまだ変革できていないところもある。生成AIといった技術を活用しながら、理想の社会の実現を阻む課題に向き合っていく」と語った。