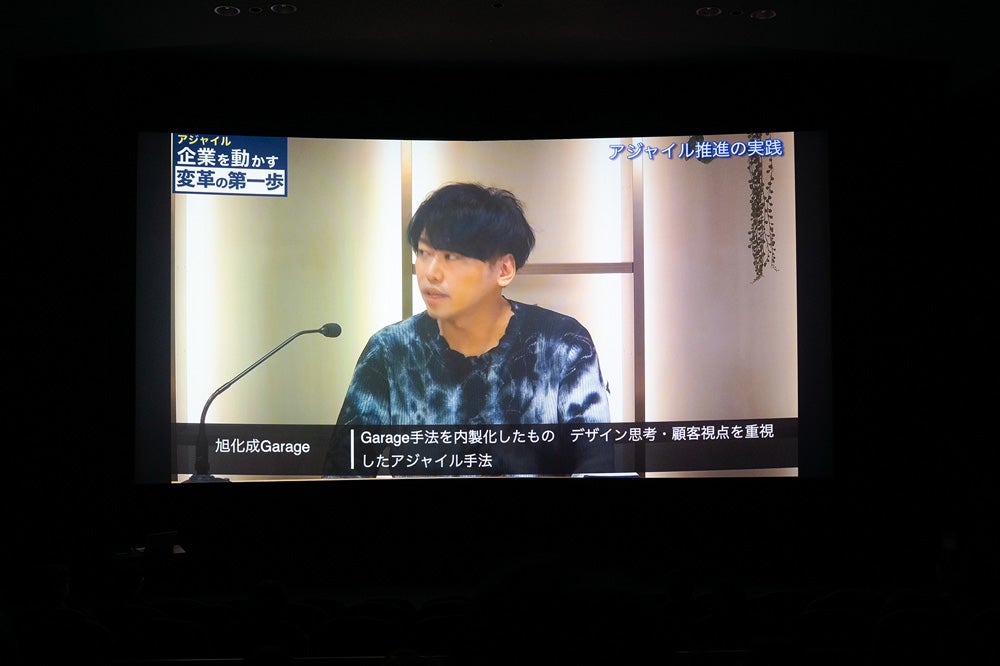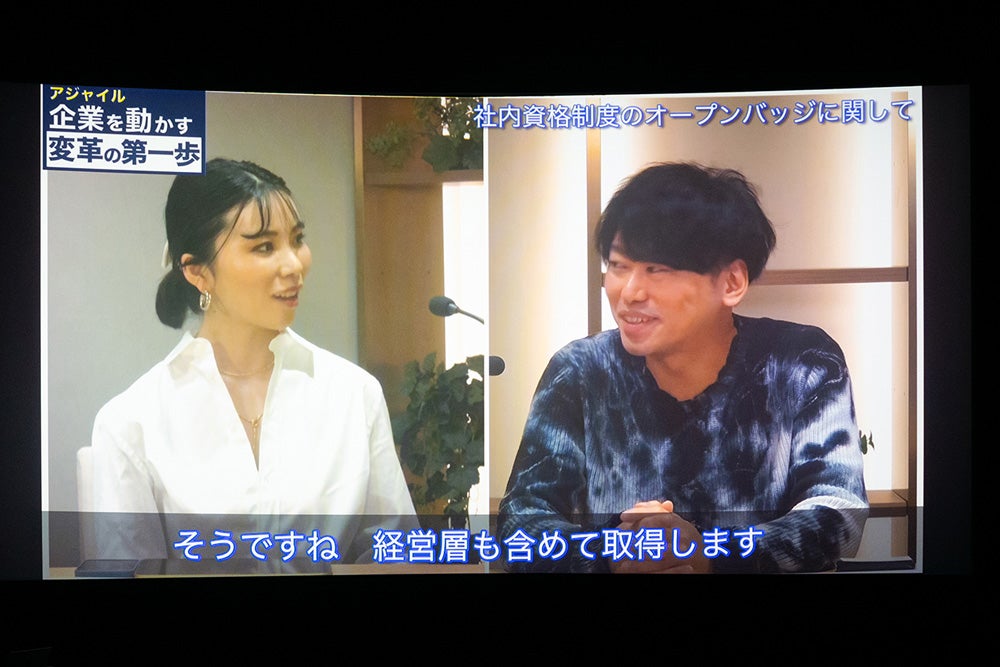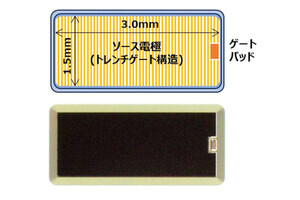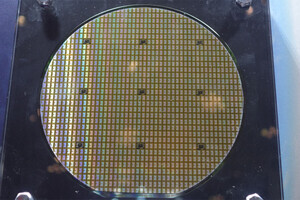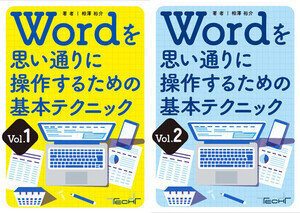アジャイル ビジネス インスティテュートは7月25日、アジャイル開発を成功させている企業の事例を紹介するイベント「アジャパーシアター」を開催した。同イベントのユニークな点は、複合映画館「ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場」のスクリーン7を利用し、「突撃!隣のアジャイル現場」と題したインタビュー映像が3本上映されたことだ。
映像には、旭化成、ソフトバンク、ソニーグローバルソリューションズが登場。アジャイル開発導入の具体的な取り組みや、成果、課題点などが語られた。その中から本稿では、旭化成 デジタル共創本部 エキスパート 西野大介氏が登場したインタビュー映像と、上映前に会場にて行われた西野氏へのリアルインタビューの模様をレポートする。
アジャイル、その手応えは?
今回のアジャパー・シアターでは、スクリーンでインタビュー映像が上映される前に、アジャイルビジネスインスティテュート 代表取締役社長 板倉美帆氏による西野氏へのリアルインタビューがさながら舞台挨拶のごとく行われた。
西野氏は旭化成全社のデジタル推進を担当しており、主にアジャイル推進や新規事業開発の推進、アジャイル人材の育成などに携わっている。
板倉氏からアジャイル活動の成功例について質問された西野氏は、「成功は過程の1つであって、積み重ねていく必要がある」と述べた上で、「最近は自分たちのチームだけでなく、いろいろなところを巻き込んでスクラムや変革できていることに手応えを感じている」と話す。
西野氏が言うスクラムとは、アジャイル開発のフレームワークの1つであり、少人数のチームを組んで計画から実装、改善までを短期間で実行するサイクルを繰り返す手法だ。もちろん、事業部のメンバーはもともとスクラムのプロというわけではない。だからこそ、西野氏をはじめとするデジタルプロ人材と共に取り組むことで、スクラムに対して好印象を持ってもらいたいという狙いがあるのだという。
「事業部のメンバーが主体的にアジャイル開発について学ぶ流れができています。旭化成ではデジタルプロ人材の育成にオープンバッジ制度を利用していますが、スクラムの価値を理解してくれた事業部メンバーが自らオープンバッジのコンテンツを受講するケースも出てきています」(西野氏)
この流れがさらに進むと、デジタル部門のメンバーではなく事業部メンバーが主体となってスクラムを回していくことも可能になるのでは、と西野氏は期待を寄せる。
こうした旭化成のエピソードを聞いた板倉氏は、称賛した上で「多くの会社はそこに至る最初の一歩がなかなか踏み出せない。どうやって巻き込んでいるのか」と問い掛けた。
これに対し、西野氏は「事業部のメンバーに対してあまり難しい言葉を使わず、スクラムのエッセンスを引き出しながら巻き込んでいく」と回答。「事業部としては専門ではないので、どうしてもIT部門にお任せという発想になりがちだが、一つ一つ丁寧に説明して共同作業することにより、面白さが伝わってスキルも向上していく」と説明した。
失敗したからこそ得られた知識
西野氏曰く、アジャイル開発は「ウォーターフォール開発の課題を解決しようとしている仕組み」なのだという。
「例えば、ウォーターフォールには『プロジェクトマネージャー』という絶対的な存在がいますが、それを解体するのがスクラムというフレームワークです。また、ウォーターフォールは構造的に人が入れ替わっても大丈夫なようになっていますが、スクラムではあまり人を入れ替えてはいけません。一人一人の個性を引き出し、精度を高めて成果を上げようとするのがアジャイルなんです」(西野氏)
とはいえ、西野氏もアジャイルに取り組み始めた当初は失敗した経験があるという。あまりにもウォーターフォールのやり方になじんでいたため、スクラムをやろうとしても結局はウォーターフォールから切り出したやり方を当てはめただけになっていたというのだ。
「ただ、そうやってウォーターフォールの知識を基にやってみたことで、お仕着せではなく自分の知識として解釈できるようになりました。ウォーターフォールで学んだことをスクラムで再解釈できたことで、失敗の経験はむしろ大成功だったと思っています」(西野氏)
旭化成のアジャイル開発に迫る
リアルインタビューに続いては、同じく板野氏がインタビュアーを務めるかたちで事前に撮影された西野氏のインタビュー映像の上映が行われた。映像では、旭化成におけるアジャイル開発について、より掘り下げた内容が語られるという趣向だ。
まず言及されたのが、旭化成がDXのためのアプローチとして用いている「旭化成Garage」である。これは、デザイン思考とアジャイル手法のかけ合わせた手法で、社内外と共創しながら新たな価値創造に挑戦するというものだ。
この取り組みの中心となっているのが、デジタル共創本部の共創戦略推進部に所属する約20名のメンバー。そこにプロジェクトごとに事業部メンバーも参加し、さまざまな施策や活動を行っている。共創戦略推進部は事業部を横断して旭化成Garageを推進する立場であり、スクラムマスターとして事業を推進したり、アジャイルコーチとして後方支援に回ったりと、状況に応じて柔軟に立ち回る。
必然的にプロジェクトの掛け持ちが発生するが、メンバーの割り振りについてはプロジェクトのステージごとに検討するという。
ここで言うステージとは「アイデアの検証」「課題の質を上げる」「ソリューションの検討」「人が欲しがるものを作る」「スケールするための変革」の5つである。これは、日米で5社を起業した経験を持つ田所雅之氏の著書『起業の科学』(発行:日経BP社)の手法だ。
プロジェクトをステージごとに分類したら、適切なメンバーの割り振りを行う。それでもプロジェクトの速度が上がらないなどの課題が発生した場合は、先に述べたように状況に応じてスクラムマスターやアジャイルコーチなど共創戦略本部メンバーの関わり方を変えていくわけだ。
アジャイルを本格導入したことで、「無駄がなくなった」と西野氏は話す。どうしても“転ばぬ先の杖”になりがちなウォーターフォールと違い、早く失敗することで早く価値を生み出せるわけだ。それが生産性の向上やコストの削減にもつながるのだという。
「もうアジャイルやスクラムを使わないプロジェクトは避けたいと思うくらい、自分の中では重要になっています」(西野氏)
全従業員をデジタル人材に育成
DX人材の育成については、先述したようにオープンバッジ制度を活用している。オープンバッジとは、世界共通の技術標準規格に沿って発行される、知識やスキル、経験のデジタル証明だ。欧米を中心に大学や資格認定団体、グローバルIT企業が多くのオープンバッジを発行している。旭化成では、オープンバッジ制度を管理する組織をデジタル共創本部内に設置。講師を担当するメンバーやコンテンツを作成するメンバーは組織のさまざまな場所にいて、それぞれの得意分野を担当しているという。
旭化成ではレベル1〜5までのオープンバッジを用意。レベル1と2が入門編であり、レベル3が活用編。レベル4以降がプロフェッショナル人材の育成向けとなる。同社では全従業員がレベル3までの取得を目指しており、本社だけでなく工場などの現場メンバーや海外勤務のメンバーも含めたグループ全体が対象となっている。
オープンバッジ制度に参加するのは若手メンバーだけではない。リーダー層や経営層も含めて全員が取得するという。これに板倉氏は「同じ目線、同じ言葉で会話できるようになるということですね」と感心。西野氏も「同じ目線というのはすごくいいキーワード」とうなずき、「管理職とメンバーで役割は分かれているものの、目線はかなり一致しているのが当社の特徴。なぜかと言うと、当社には管理職へのキャリアパスだけでなく、高度専門職といって技術職のまま上がっていく道もあるので」と説明した。
メンバーの意欲をいかに高めるか
旭化成はDXの段階を「導入期」「展開期」「創造期」「ノーマル期」の4つのフェーズに分類している。導入期は実課題をデジタル技術で解決する段階、展開期は事業や地域、職域に横串をさしてデジタルを展開する段階、創造期は新しいビジネスモデルや新事業を創造する段階、ノーマル期は全社員がデジタルを活用するのが当たり前になっている段階だ。このノーマル期を2024年で達成するのが旭化成のDXロードマップである。
しかし、「全従業員がデジタル人材になる」というと聞こえは良いが、中には意欲がわかないメンバーもいるのではないか。この質問に西野氏は「我々もまだ理想的な状況ではないが」と前置きした上で、「もともと製造業のバックグラウンドがあり、日常的に学ぶ文化があった」ことを成功要因として挙げる。また、社内勉強会を定期的に開催して、スキルを提供しあう機会をつくったり、日常的に学習内容について話し合ったりすることで「勉強しなければついていけなくなる」という感覚を醸成しているのだという。
「デジタルの分野は学んだことがすぐに役立つので、フィードバックを受けやすい。だからこそ自然と学ばなければという気持ちにもなりますし、学習のサイクルが回りやすいのだと思います」(西野氏)
アジャイル開発を成功に導くポイントは?
最後に西野氏は、これからアジャイルに取り組む企業へのアドバイスとして「ファーストステップを間違えるとボタンの掛け違いが発生してしまう。デジタルありき、アジャイルありきだけでやるとうまくいかないと思っている」とコメント。
「最初の着想は流行っているからでもいいと思いますが、その次は自分たちの課題や目指すべきところがどこなのか、そこに対してアジャイルが有効なのかを見極めて、ビジョンを描くことが大事です。特に管理職が明確に旗を立てて、そこに到達してほしいというメッセージを掲げることが重要だと思います」(西野氏)
アジャイル導入で大きな成果を上げた旭化成。一方で、デジタル共創本部の設置やオープンバッジ制度の採用、リーダー層や経営層の積極的なコミットなど、成功の背景には多くの変革が必要だったことも事実だ。これからアジャイル導入を検討するのであれば、旭化成の事例も参考に、自社に合ったやり方を十分に考えるべきだろう。