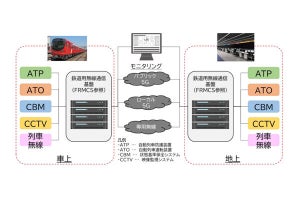ネットワンシステムズは8月6日、明治電機工業、オムロンとの共創プロジェクトのデモンストレーションを披露した。会場となったのは、ネットワンのイノベーションセンター「netone valley」だ。
同施設は昨年にオープンし、顧客やベンダーとディスカッションをして、さまざまな可能性を生み出す共創の場と位置付けられている。そのため、検証が行える空間や設備、機器が用意されている。
ネットワン・明治電機・オムロンの共創プロジェクトの意義
3社の共創プロジェクトは、次世代無線技術を活用したスマートファクトリーの実現に挑戦することを目的としたもの。ネットワンシステムズ 中部事業本部 第1営業部長の田中寿弥氏は、「次世代の製造現場に貢献するプロジェクトであり、3社の強みを生かしたデモ環境を構築した」と説明した。
ネットワンはITインフラ構築と先端テクノロジーに関するノウハウを持っており、今回は産業用ワイヤレスを提供している。明治電機は工場の自動化システムの設計・構築に関するノウハウがあり、また、オムロンは工場のニーズに適した制御機器とFA機器を製造しており、今回はAMR(Autonomous Mobile Robo:自律走行搬送ロボット)を提供している。
さらに、田中氏は、「無線をテーマとしているのは、3社が顧客と接する中、無線のニーズが高まっていると感じているから。特に移動体の活用が注目されている」と述べた。製造業においては、「ニーズの多様化」「多能工化」「生産ライン変更のコストと時間」「多品種少量生産」といった課題があるが、田中氏は、無線技術を活用することで、これらを解決したいと述べた。
工場で求められる無線技術
オムロンは産業用ロボット、協調ロボット、モバイルロボットを製造しているが、今回モバイルロボットを提供している。オムロン インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー ロボット事業部 事業企画室 室長 吉田健一氏は、「モバイルロボット事業では主に搬送の自動化を目指している」と語った。
また、FA市場では自動化がトレンドであり、その実現のカギとして、吉田氏は「設備の進化」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」「生産性の拡大」を挙げた。「変種変量生産が求められる中、レイアウトを柔軟に対応できることが求められている。DXとしては、ERPやMESと連動してデータを共有して、生産性の向上につなげる」と同氏。工場に無線を導入することで、これらの実現を目指す。
また、明治電機工業 第1営業本部 第1営業部 部長 阿部功氏は、工場では現在、HMI、PLC、IPCが至る所に設置されており、次のようなさまざまな課題が発生していると指摘した。
- アセット管理
- 制御・表示機器のバリュエーションの増加、ライフサイクルの短縮
- エネルギー需要の変動
- 保守作業の属人化
- IoTによるデータ収集量の増加
阿部氏は、PLCを仮想化することでこうした課題を解決できると指摘した。同氏は、ライン生産制御を仮想化するには無線インフラの普及が必要であることから、今回のプロジェクトに参加したと述べた。
AMRの自動走行でWi-Fi通信とローカル5G通信の質を実証
今回のデモは、人手不足や自動化のニーズから移動体のニーズが高まっているAMRに、Wi-Fiとローカル5Gを搭載して検証を行うもの。田中氏は、製造現場では用途によって許容される遅延が異なることから、適用領域を見極めて、段階的に無線化を検討することが大切と語った。
WiーFiは日常生活でも利用されているが、免許不要で利用が可能であり、導入コストが安い。一方、ローカル5Gは安定した通信性能を発揮するが、免許を取得する必要があり、対応デバイスも限られている。
田中氏は、ローカル5Gの優位性として「高出力による広いカバレッジ」「安定したパフォーマンス」「移動体への対応」を挙げた。デモでは、Wi-Fiとローカル5Gを搭載したオムロンのAMRが走行中に、Wi-Fi経由で送信した画像とローカル5G経由で送信した画像を比較することで、この優位性が示された。
netone valleyには、Wi-Fi 6/6Eのアクセスポイントとローカル5Gの基地局が各所に設置されている。AMRは走行しながら、これらアクセスポイントと基地局と通信してハンドオーバーを行う。
Wi-Fiによる通信時、アクセスポイントの切り替え時にわずかに画面が途切れたが、ローカル5Gによる通信時はハンドオーバーがどこで起きたのか、わからなかった。また、AMRが送信した画像もWi-Fi通信時よりもローカル5G通信時のほうがクリアで、文字がはっきりと見えた。
-

左から、Wi-Fi通信を介して送られた画像、ローカル5G通信を介して送られた画像。左の画像はアクセスポイントの切り替えが発生し画像が乱れている。左よりも右の画像のほうがクリアであることをおわかりいただけるだろうか
さらにデモでは、無線空間におけるPLCデータリンク通信が紹介された。PLC間のデータ同期を実現するタグデータリンク通信を無線経由で実行した。阿部氏によると、工場ではPLCデータリンク通信が行われているという。デモの結果、Wi-Fi通信ではたびたび通信が止まっていたが、ローカル5G通信では止まることはなかった。
なお、多少画像の乱れなどはあったものの、Wi-Fiによる通信はローカル5Gによる通信と比べて、それほど劣化を感じなかった。ここまでクオリティに引き上げるために、試行錯誤してかなりのチューニングを行ったそうだ。安価な分、手間がかかるというわけだ。ローカル5Gは導入に手間とコストはかかるが、安定した通信は魅力だ。やはり、Wi-Fiとローカル5Gを用途に応じて使い分けることが重要なのだろう。