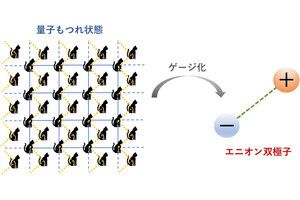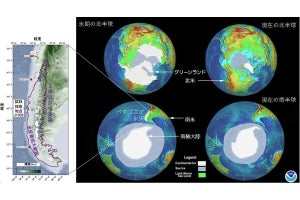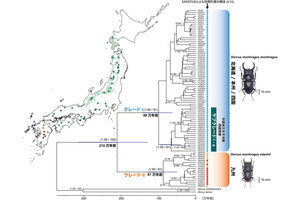慶應義塾大学(慶大)は6月24日、氷の表面に存在する液体様の膜(薄い水の層)である「擬似液体層」において、分子動力学シミュレーションと機械学習によりその分子的特徴を明らかにした結果、動きやすい運動と動きにくい運動が頻繁に切り替わるような性質があることを突き止めたと発表した。
また、動きやすい運動をする分子が集まりやすい性質があり、空間的に分子運動が不均一であることも明らかにしたと併せて発表された。
同成果は、慶大大学院 理工学研究科の安田一希大学院生、同・遠藤克浩大学院生(研究当時)、同・大学 理工学部の荒井規允准教授、同・泰岡顕治教授らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の化学全般を扱う学術誌「Communications Chemistry」に掲載された。
氷の表面は滑りやすく、手でつかもうとしてもつるんと逃げられてしまうのは知っての通り、首都圏のような雪に慣れていない地域では、年に1~2度の大雪などによって路面が凍結すると、滑って転倒し入院する人のほか、車のスリップ事故などが多発するなど、その摩擦係数の低さは侮れない。
こうした氷の滑りやすさは、氷の一部が融けてできた水が氷の表面で薄い膜となっていることが理由と考えられており、その薄い水の膜は擬似液体層と呼ばれている。なお、氷の表面では、水分子が十分な数の結合を作れずに結晶構造を保てないため、この薄い水の膜は不規則な構造を持つという。
擬似液体層の研究は、長い年月にわたって数多くがなされてきた。そうした中、近年のシミュレーション研究においては、グラスに水と氷を入れると分離するように、擬似液体層は原子レベルでは氷のような構造と水のような構造に分かれているという考えが提案されている。しかし、擬似液体層の分子的な特性については未解明な部分もまだ多く残っているという。
そこで研究チームは今回、大規模な全原子分子動力学計算(運動方程式にしたがって原子の振る舞いをシミュレーションする手法)と、分子運動を解析する機械学習(今回の場合は、擬似液体層の分子運動データが氷内部での分子運動に類似しているのかを評価するのに利用された)を用いて、擬似液体層に含まれる分子の運動を解析することにしたとする。
その結果、氷と水を入れたグラスで見られるように氷と水の部分が明確に分かれているのではなく、動きやすい運動と動きにくい運動が頻繁に切り替わるような性質があることが突き止められたとした。また、動きやすい運動をする分子が集まりやすい性質があり、空間的に分子運動が不均一であることも明らかにされた。さらに、異なる結晶面を表面にした場合についても計算が行われ、その不均一性が結晶面に応じて異なることも示したという。
氷の擬似液体層は、表面の滑りやすさの他にも、隕石や彗星などで見られる化学反応といったさまざまな現象にも影響を与えているとする。今回の研究成果は、氷が示す特異的な性質の理解を深める上での重要な一歩となり、物理学、化学、材料科学などの分野において、貢献を果たすことが期待されるとしている。