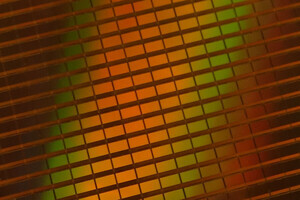4月19日に、神奈川県の磯子にあるJMU(ジャパンマリンユナイテッド)の横浜事業所で、海洋研究開発機構(JAMSTEC)向けに建造している北極域研究船「みらいII」の建造現場が報道関係者向けに公開された。以下、「みらいII」とはどのような船なのか、紹介していこう。
「みらいII」は「北極域研究船プロジェクト」の船
「みらいII」は、JAMSTECの「北極域研究船プロジェクト」で使用する研究船だ。総建造費は339億円とのこと。JAMSTECでは、「白鳳丸」以外の船の運航を民間の船社に委託しており、これは「みらいII」も同様。担当は商船三井(MOL)だ。
海面が氷で覆われているために、普通の船では立ち入れない北極海において、海底地形や生物資源の調査、海洋物理・化学・生物学分野のデータ収集、堆積物の採取、海水の温度・塩分濃度などに関する調査、気象観測などの作業を実施する。また、氷海を航行したときに船体にかかる負荷や、船体への影響を調べる任も負う。
JAMSTECでは、この「みらいII」で実施する研究船プロジェクトについて、「海外の研究者とも連携することで、国際プラットフォームとして運用」「我が国のプレゼンス向上にも寄与」との考えを持っている。その一環として、2023年11月に北極域研究船国際ワークショップを開催した。
2024年1月から船殼ブロックの製作を始めており、9月から建造ドックでブロック同士を接合する組み立て工程に入る。進水予定は2025年3月で、その後で艤装工程に移り、2026年11月頃の竣工・引き渡しを予定している。竣工後は乗組員のための慣熟航海を行い、2027年の夏に最初の観測航海を行いたいとしている。
遠隔操作式の無人潜水艇(ROV)の搭載・運用を考慮
全長は128m、全幅は23m、吃水は8m、国際総トン数は13,000t。定員97名のうち、研究者や技術者が63名を占める。調査で使用するさまざまな機材を搭載するが、遠隔操作式の無人潜水艇(ROV)の搭載・運用を考慮に入れて設計しているのも「みらいII」の特徴。
「みらいII」や、海上自衛隊の砕氷艦「しらせ」をはじめとして、砕氷船・砕氷艦ではスクリューをモーターで回す、電気推進を使用する事例が多い。これは、砕氷時の航行速度が低く、かつ強い推進力が求められることから、低回転で大きなトルクを発生する電動機の方が向いているため。
その電動機を駆動する電力は、IHI原動機製のディーゼル発電機(約5,600kW×3)と、IHI原動機製のデュアル燃料ディーゼル発電機(約2,600kW×1)から供給する。つまりディーゼル・エレクトリック推進で、推進用電動機は2基ある。
デュアルフューエルとは、液化天然ガス(LNG)と石油燃料の両方に対応するという意味。これを砕氷研究船に搭載するのは世界で初めてではないかという。
舶用ディーゼル機関の燃料は安価なC重油を用いることが多いが、それに代わるのがMGO(Marine Gas Oil)。船舶用ディーゼル油(MDO : Marine Diesel Oil)やA重油と同様に、MGOもC重油より高品質で環境に優しいとされる。
船はこのようにして作られる
昔は、船の建造というと最初に船底中央を前後に通る竜骨(キール)を据えて、そこから左右に横方向の骨組み(フレーム)を立てて外板を鋲打ちで取り付けていた。しかし1940年代あたりから、一つの船を複数のブロックに分割して個別に製作・接合する、いわゆるブロック建造法が広く用いられるようになった。
JMUの磯子工場では、艦船の建造に使用する鋼材を船で搬入している。それが最初に送り込まれるのが内業工場。鋼材を搬入するクレーンは、鉤に吊るす代わりに磁石で鋼材を吸着して運ぶところが面白い。
内業工場は3列構成で、西から東に向けて工程が進む。小さく切断した鋼材を組み合わせて部材を形作る、いわゆる小組み立てを行うのが中央の列。その左右に、平らな部分の部材を扱うラインと、曲げ加工が必要な部材を扱うラインがある。だから後者にだけ、曲げ加工のための機械や、曲げた部材に沿って支えるための設備がある。
搬入した鋼材は、最初に機械でマーキングを行い、加工の目印となる線の罫書や、文字のマーキングを施す。次に、NCプラズマ切断機で所定の形状に切断したり、切り抜いたりする。もちろん、ここで無駄になる部材が少ない方が経済的だ。
切断や曲げといった加工を行った後、溶接によって組み立てを進める。そして、中央のラインで作った小組み立ての完成品を左右のラインに流して、溶接によって組み立てる。これで「船殼ブロックの、そのまた一部」が順次出来上がるので、それを屋外のストックヤードに出す。
こうして部分品を構成する子ブロックが出そろったら、それを溶接で接合して大きなブロックにする。「みらいII」の場合、まず250個ぐらいの子ブロックを組んで、それを85個のブロックにまとめる。この85個はそれぞれ、重量200t未満で収まるようにしている。理由は、建造ドックで使用するクレーンの力量に合わせるため。
この辺の事情は造船所によって違うため、同型の艦船を異なる造船所で作らせると、造船所によってブロックの分割方法や製造工程が異なる。完成してしまえば同型になるのだが。
建造ドックの北側がブロックを扱うエリアで、南側は配線・配管を扱うエリア。船殼ブロックを製作する過程で、その内部に電気配線を通すための樋や水や油の配管などを、先行艤装することもある。
普通、配線・配管・機器類は艤装工程で取り付ける。しかし、船殼ブロックをすべて組み上げてから取り付けるよりも、先に取り付けておく方が効率が良い場合には先行艤装が行われる。
また、先行艤装の利点として反転艤装がある。つまり、天井に何かを取り付けるときに、対象となるブロックをひっくり返して作業を行う。下向きの姿勢で作業を行えるので作業性が良いし、結果として品質の向上にも寄与する。
ついでに書くと、船の船体みたいに大きな鋼材の塊は、温度変化によって伸縮する。だから作業の内容によっては、外気温と船体温度の差が少ない夜間に行う場面がある。