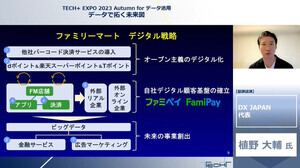マーケティングアナリストで芝浦工業大学デザイン工学部教授の原田曜平氏は、若者の消費行動について日々トレンドを追っている。同氏が生み出した「さとり世代」「マイルドヤンキー」など数々の造語は、ユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされたこともあり、ご存じの方も多いだろう。
そんな原田氏が注目するのが「Z世代」だ。同氏の著書『Z世代 若者はなぜインスタ・TikTokにハマるのか?』(発行:光文社)でも取り上げられたZ世代は、おおよそ1990年代中盤〜2000年代序盤以降に生まれた世代を総称する概念として米国から発信され、昨今では関心を寄せる企業も多い。
では、Z世代とはどんな特徴を持った人々なのか。そして、なぜ注目を集めているのだろうか。
11月10日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」に、原田氏が登壇。Z世代の特徴や流行を紹介しながら、企業はマーケティング活動において、どのようにZ世代と向き合えば良いのかを解説した。
「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」その他の講演レポートはこちら
世代別に振り返る日本人の価値観の変遷
原田氏はZ世代の説明に入る前に、日本の各世代について、それぞれの呼称やその特徴を説明した。
まず現在73~77歳にあたるのが「団塊世代」で、2025年には全員が後期高齢者になるため「介護市場は大変なことになる」と原田氏は危惧する。
64~72歳は「シラケ世代」と呼ばれ、マーケティングの世界では「ポパイ・JJ世代」と呼ばれることもある。団塊世代からテレビ文化が始まったのに対し、雑誌文化を広めた世代だ。
59~63歳は「新人類世代」。代表する著名人はダウンタウンやとんねるずで、かつてはアグレッシブな若者として注目を集めた世代だが、この世代のビジネスパーソンもすでに退職年齢にさしかかっている。
53~58歳は就職活動の時期にバブル景気の時代を迎えた「バブル世代」だ。この次に来るのがバブル崩壊後に就職期を迎えた世代で、ここを境に日本人の価値観が大きく変わったと原田氏は言う。
「ロスジェネ世代」とも呼ばれるのが、49~52歳の団塊ジュニア世代と、48~37歳のポスト団塊ジュニア世代だ。原田氏は、堀江貴文氏やひろゆき氏、SMAPや安室奈美恵氏などを例に挙げ、「団塊世代に次いで人口が多いため競争力の高い人が芸能界でも生き残っている」と言う。ただし、勝ち組がいる一方で、就職氷河期の世代であるため非正規雇用の人も多く、格差が広がった世代でもある。
27~36歳は「ゆとり世代」。人口はそれ以前から減少傾向だったが、この世代になって団塊ジュニアの半分近くに減り、急に少子化が問題視され始めた。生まれた時から景気が悪いので苦労人が多かったという。原田氏は独自にこの世代を「さとり世代」と名付けた。
「さとり世代より前の世代の若者は若いときに景気が良く、消費も恋愛も盛んで、いわば“煩悩まみれ”でした。一方のさとり世代は、高価なものを欲しがらず、煩悩を捨てて悟ったように見える世代です」(原田氏)
世界的に共通の価値観を持つZ世代
そして「脱ゆとり世代」とも呼ばれる26歳以下が、Z世代だ。この呼称は、米国で10代半ばから20代を「GenerationZ」と呼んでいることに由来する。とはいっても、ただ同年代を指しているだけではない。
原田氏は「現在の若者は米国をはじめ、全世界的に価値観やライフスタイルが似ている」と語る。
「TikTokやYouTube、Instagramなど、Z世代は情報を得る媒体が世界的に共通しています。それより上の世代は世界的な共通項が少なかったのですが、Z世代になって初めて、米国など他国における同世代の価値観を日本でも取り入れやすくなりました。そのため、海外の情報をなくしては日本のZ世代の理解は進められません」(原田氏)
米国ではZ世代の人口が多く、消費者、有権者として魅力的な層と位置付けられている。そのため、10年以上前から企業の注目を集めてきた。
一方、日本の企業ではこの数年で、急激にZ世代への注目・関心が高まっている。その最大の理由は、人手不足だ。
地方の企業では人材が集まらず、大学ですらも学生集めに苦労している。昨今のコロナ禍では、感染症の影響だけではなく人手不足が理由で倒産する企業が多かったという。そのため、今後囲い込むべき人材としてZ世代への注目が集まったそうだ。
また、SNSを利用している人口が多いのも、Z世代が注目されている理由だと原田氏は話す。同氏はサイバーエージェント次世代生活研究所が2022年に行った調査のデータを引用し、ゆとり世代に比べてZ世代のSNS活用率の高さを示した。企業から見ると、情報拡散役を期待できることに加え、社会人年齢になり始めたZ世代への注目度が高まっているのだ。
Chill、スマホ、SNS……Z世代の特徴を解説
Z世代の特徴を考える上でまずポイントになるのは、超人手不足が顕在化している時代を生きていることだ。原田氏は「(人手不足だからこそ)不景気と言われていながらも、Z世代の就職率は高くキープし続けられている」と説明する。就職も転職もしやすいため、普通に生活するには困らないという考えが根付いているそうだ。
そこで脚光を浴びたのが、「Chill」だ。これは、「リラックスしてマイペースで生きる」という考え方を指す。リラクゼーションドリンクやシーシャ、オシャレなピクニック、サウナなどがZ世代に流行っているのは、象徴的な例だと言える。
スマホと共に生きてきたことも、Z世代ならではの特徴だ。時代的に、Z世代は「初めて持った携帯電話はスマホ」というケースがほとんどだろう。Z世代のスマホ所有率は中学生で8割近く、高校生ではほぼ全員が持っている。こうした背景も相まって、ゆとり世代と比べると、ほぼ全てのSNSでZ世代の利用率が高い。つまりSNSにおいてはZ世代が圧倒的な影響力を持っているのだ。そしてスマホやSNSばかり使う影響で、自己承認欲求が高いのも特徴だという。
また、Z世代が上の世代と異なるのは、SNSで海外の情報もダイレクトに入手していることである。特に影響力が強いのが米国で、次いで韓国、中国、台湾の影響があるという。日本のZ世代の心をつかむには、諸外国のトレンドなども知っておくべきだろう。
Z世代がハマる“7つのこと”から消費行動を理解する
特定の世代の消費行動を理解するためには、その世代の人々の間で何が流行っているかを知ることが有効だ。原田氏は、「Z世代の消費ニーズ」として、ここ数年のZ世代の流行を表すキーワードを紹介した。それはChill、ミー、親子消費、海外疑似体験、絆確認、推し活、レトロブームの7つだ。
前述の通り、シーシャバーやリラクゼーションドリンクが流行ったのはChillによるものだ。そして「ミー」は自己承認欲求を満たすことを意味し、匂わせ投稿や親自慢といった間接自慢、容姿などを良くみせるための“盛り”などがその例として挙げられる。
またZ世代は親子の仲がとても良いことも特徴で、親子で推し活を楽しんだり、仲の良い様子をSNSに投稿したりすることもある。「企業から見れば、親子をセットで巻き込んだマーケティングが有効になる」(原田氏)というわけだ。
コロナ禍でニーズが高まったものとしては、海外疑似体験と絆確認がある。コンビニで韓国コスメが売れたり、韓国雑貨ばかりを置くショップが流行ったりと、コロナ禍で実際に訪れることができない海外を、日本にいながら疑似体験できるような商品/サービスが人気だ。
また、リップや香水などを作れるような“モノ作りカフェ”の人気も高いが、これは「友人との絆を深める商品だからだ」と原田氏は話す。絆を構築できるような場所や商品が、Z世代に高い体験価値を提供できるそうだ。
「推し活」は、以前は一部の熱狂的なオタクがやることだと思われていたが、それより労力や金をかけないライトな活動で推すのがZ世代流だ。つまり、以前に比べて推し活の市場は広がったと考えられる。また、昔の若者は自分が生まれる以前の古いモノ・コトなどは嫌いがちだったが、今の若者はむしろ好む傾向にある。
最近では平成昭和のレトロではなく、実際はレトロではないがレトロテイストのあるポップなデザインである「ニュートロ(ニューレトロ)」に人気があるという。歌舞伎町タワーや渋谷横丁など、最近できた施設の多くはニュートロがデザインコンセプトになっているそうだ。
原田氏は「Z世代に流行るものはおおむねこの7つのどこかに入る」と力強く語り、次のようにアドバイスを送った。
「Z世代をターゲットにする商品を出す場合、ここに含まれていないとヒットする可能性が低いことになります。逆に、この7つから発想してアイデアを考えるのも良い方法かもしれません」(原田氏)