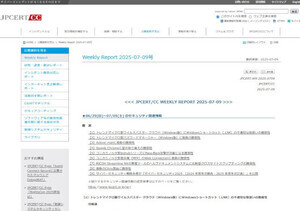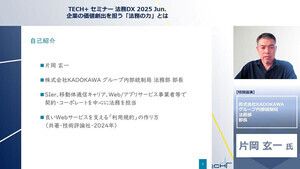企業が変革の必要性を感じ、DXを推進したとしても、それが思うように進まないこともある。その原因はどこにあり、どう対策すべきなのか。経営トップ向けにDXのアドバイザリーを行うDX JAPAN 代表の植野大輔氏は「DXには立ちふさがる壁が4つあり、それを打ち破るための4つの型もある」と話す。
11月6日~17日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」に同氏が登壇。Massive Transformative Purpose (MTP、野心的な革新目標)やチェンジマネジメントの考え方を中心に、DXを進めるためにすべきことを解説した。
「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」その他の講演レポートはこちら
DXの壁を打ち破る4つの型
講演冒頭で植野氏は、自身がデジタル統括責任者としてDXに取り組んだファミリーマートの事例を紹介した。ファミリーマートは2019年にアプリサービス「ファミペイ」を立ち上げたが、その際にはファミペイという自社によるデジタルの基盤を確立することを根幹としながら、ここで得たデータを活用して金融や広告マーケティングといった小売業以外の事業創出も目指していたという。その後実際に金融サービスを提供するファミマデジタルワンや広告マーケティングのDATA ONEを立ち上げ、ファミペイのデータや店舗の購買データを活用する広告マーケティングサービスの展開につなげている。
植野氏がファミリーマートでの経験を基に、企業のDX支援を行う際、大事にしているのがDXの4つの型だ。同氏は、DXには立ちふさがる4つの壁があり、それを打ち破るための4つの型があると言う。その壁とは、掛け声だけで構想が見えないこと、計画にDXを盛り込んでも具体的にすべきことがわからないこと、推進力が弱く進まないこと、トップがDXを叫んでも社員が変わろうとしないことの4つである。そして壁を破るための4つの型とは、30年先を見越したMTPを持つこと、計画ではなくロードマップをつくること、変革に特化した推進マネジメント組織をつくること、組織の企業文化を変えるチェンジマネジメントだ。
「この中で特に重要なのがMTPとチェンジマネジメント」だと植野氏は語る。戦略やロードマップの策定は外部の戦略コンサルタントに任せても良いが、企業の世界観やビジョンを描くことは自分たちでしなければならない。企業文化や各々の社員の気持ちを正しい方向に導くといったことも自力ですべきで、これをしなければ、いくらデータやAIを活用しても、企業は変わらないのだ。
“チェンジモンスター”を放置してはいけない
DXを推進し、企業を変革しようとする場合、デジタル人材が重視される傾向がある。しかし、デジタルのスキルは誰もが高めるべきものであり、必ずしもデジタル人材が変革を推し進めるわけではない。企業にとって重要なのは、誰が変革のリーダーになるかを見極めて、その手助けをすることだ。そのために「注意すべきなのが抵抗勢力」だと同氏は言う。
組織には、自ら変革を実行する変革人材、そこに加わる賛同者、後から協力する追随者のほかに、最後まで加わらない抵抗者が必ずいる。植野氏も在籍経験のあるボストンコンサルティンググループでは、変革の妨げになる抵抗者を“チェンジモンスター”と名付け、妖怪のようなキャラクターとして発表している。例えば、閉じこもって他とのつながりを持とうとしない“タコツボドン”や、かつての経営トップが手掛けた事業はどんなに業績が悪くても撤退を議論できない“カコボウレイ”などが日本企業には存在するという。こうした抵抗者を放置していては、DXは進まない。
-

ボストンコンサルティンググループが示したチェンジモンスターの例、出典:ボストンコンサルティンググループ 『展望』Vol.146
「変革には必ず痛みが伴う」と植野氏は断言する。抵抗勢力に対応するのは骨が折れることかもしれないが、何かを変えるにはそれなりのスイッチングコストも必要になるのだ。
「変わろうとする社員の意識をケアしつつ、チェンジモンスターに立ち向かい、痛みの谷をいかに飛び越えて、変革効果を生み出すかが重要なのです」(植野氏)