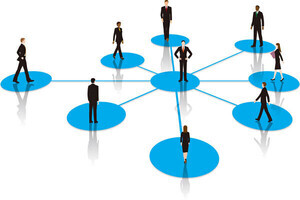日本発のグローバル楽器メーカーであるヤマハは、工場のスマートファクトリー化を推進している。熟練技術者のスキルや経験に基づく勘が求められる楽器製造の世界にデジタルを浸透させようとしているのだ。ともすれば相反するような試みだが、着実に効果を上げていると同社 楽器・音響生産本部 生産企画統括部企画推進部 スマートファクトリー推進グループの宮田智史氏は言う。
11月6日~17日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」に同氏が登壇。サックスとギターの製造過程で進めているデータ活用とデジタルツイン、そしてピアノの製造過程において行っているAIによる“匠の技”の形式知化の試みについて解説した。
「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」その他の講演レポートはこちら
「製造DX1.0」構想の実現に向け、デジタルツインを推進
宮田氏は講演冒頭で、ヤマハが中期経営計画「MAKE WAVES 2.0」を掲げ、ポストコロナの新たな社会で持続的な成長を目指していることを紹介した。重点テーマの中には「生産技術開発」と「DX」がある。その実現のため、スマートファクトリー化とデジタルツインの推進を担当しているのが、同氏の所属するスマートファクトリー推進グループだ。
同グループの組成は2018年からだが、同社ではそれ以前から工場のIT化、IoT化が進められてきた。生産スケジューラーや実績収集を行うためにタブレットを導入し、生産進捗やクオリティ、コストなどが可視化されたダッシュボードや、設備稼働ダッシュボードなどを用いたデータ活用も推進してきた。
現在は同グループにより掲げられた構想「製造DX1.0」の実現に向けて、デジタルツインのシステム開発が進められている。来年からはこれを中国やインドネシアの拠点にも展開し、さらなるコストダウンと、生産性、品質の向上を目指しているという。
サックスの組立にビーコンを導入し、作業を可視化
管楽器を製造するヤマハミュージックマニュファクチュアリング 豊岡工場では、サックスの組立をターゲットに、データを活用し工程を改善するシステムを導入した。具体的には、作業進捗のリアルタイム管理である。
各作業台にビーコンを設置し、製品に取り付けたタグからの発信を秒単位で受信することで、製造中の製品の位置や時間を計測。これによって製品が今どの作業台にあるか、そこでどのくらいの時間作業したかがわかる。
実際の作業台のレイアウトを表したマップ上に製品の流れが表示できるので、出来高や作業時間はもちろん、どの場所に製品が溜まっているかという在庫状態も把握できるし、作業者ごとの1台の作業工数も可視化される。
工場内では作業者の頭上のディスプレイに作業者ごとの作業ペースを表示し、自分の作業パフォーマンスを可視化したほか、タクトタイムを音で通知するなどして、作業者が自身で自律的に作業ペースを調整できるようにした。一方、現場管理者の側では、ダッシュボードでリアルタイムにパフォーマンスを把握することができる。
ライン全体の平均サイクルタイムやラインアウト数をグラフで表示することで、ボトルネックもすぐに発見できるようにした。作業の様子は常時撮影してデータとの紐付けを行っており、集まったデータをドリルダウンすると、ボトルネックになっていた部分の動画が流れるため、速やかに原因が確認できる。実際の改善効果も確認できている。導入から約6カ月で生産能率が16%、ラインバランスが20%向上したと宮田氏は示した。
「DXの根幹である、データに基づいた現場改善や、異常検知の仕組みも確立できました」(宮田氏)
ギター製造工場ではデジタルツインを導入
一方、ヤマハミュージックマニュファクチュアリングでギターの製造を行っている掛川と飯田の工場では、PoCでデジタルツインを導入した。飯田工場で木工、塗装を行い、掛川工場に輸送して組立を行っているが、その各工程においてIoTデバイスやQRコード、RFID(Radio Frequency Identification、無線周波数識別)、ビーコンを使って、作業時間やモノの投入履歴といった6つの基本実績データを収集している。
具体的には、製品の作り方をデータ化したBOP(Bill of Process)と、生産資源をデータ化したBOR(Bill of Resource)を構築し、「ヤマハ製造モデル」としてデータを標準化する。それをIoT、MES、ERPの3層で構成されるデータ統合基盤に入れ、デジタル空間に実際の工場を再現している。ここで特に重視したのはモニタリングと分析で、これによってしかるべき意思決定ができるかどうかを検証することに注力したそうだ。
実際の工程においては、木材に取り付けたQRコードで作業の着完を読み取り、作業者の名札やモノにRFIDをつけることで作業者情報や加工時間を自動取得する。ビーコンは現品票に添付して製品を自動検出できるようにしたほか、台車に載せた複数のギターにつけたビーコンも一度に読み取れるようにし、作業者の手間を省いている。また、工場内のモニターにはリアルタイムの進捗を表示。個々の作業者向けには作業時間や台数といったパフォーマンスも表示して、作業者それぞれが自分でペースメイクできる環境を整えた。
熟練技術者の技能をAIで伝承するために
楽器の製作においては、熟練技術者のスキルや勘といった特別な技能が重要な要素になることがある。そこでヤマハではデータを活用することで、それを伝承するための実証実験も進めている。ここでは、ピアノ製作における整音技能をAIによって形式知化する取り組みが紹介された。
ピアノは、鍵盤を押すとハンマーが弦を叩くことで音が出る仕組みだ。そのため、ハンマーの出来は音色を左右する重要な要素になる。整音は、ピアノを打鍵して音を聴きながら、ハンマーの硬さや弾力を調整し、音色や響きのバランスを整える工程だ。ここでは、弦との接触が均一になるようにハンマーの表面を削ったり、ハンマーに針を刺して弾力を調整したりすることで音を整える。従来この工程は熟練技術者に頼っていたのだが、これをAIで形式知化しようとしているのだ。
整音工程は2段階に分かれており、第一整音では人が音を聴いて針刺しの回数を考え、それを自動機に入力して針刺しを行う。第二整音では、より繊細な調整を人が行う。今回の試みは第一整音の部分で行われている。自動打鍵機で打鍵した音を録音し、録音データからAIが針刺し回数を推論するという仕組みだ。AIにはこれまでに人が行った整音の結果のデータを学習させているが、さらに録音データが増えるたびに学習し、推論精度が向上していく。
AIは必要なところだけ使い、“匠の技”を大切に
従来、針刺しの回数は人間の感性で判断していたが、再現性が低いことが課題だったと宮田氏は言う。しかしAIを導入し、その完成形を形式知化したことで、誰が作業しても熟練の技術者と類似の結果が出せるようになってきた。ただし、同社は音を扱う企業であるため、熟練技術者による作業には大きな価値があると考えているそうだ。
「全てをAIに任せるのではなく、必要なところだけ使う、あるいは技術者が引退するとその技能が残らないものについて、デジタルのアプローチでその技能を伝承していきたいのです」(宮田氏)
「ヤマハの強みは技術と感性」だと同氏は強調する。したがって、ほとんどの仕事が暗黙知の集合体になっているのだ。その中で、変えても良いものは最新テクノロジーを活用して自動化していくが、付加価値となる、匠の技と呼ばれるクラフトマンシップは変えずに残す工夫をしていきたい考えだ。
「そういった住み分けをすることで、極限まで合理化をしながら、匠の技を後世に継承する時間を使えるような工場にしていきます」(宮田氏)