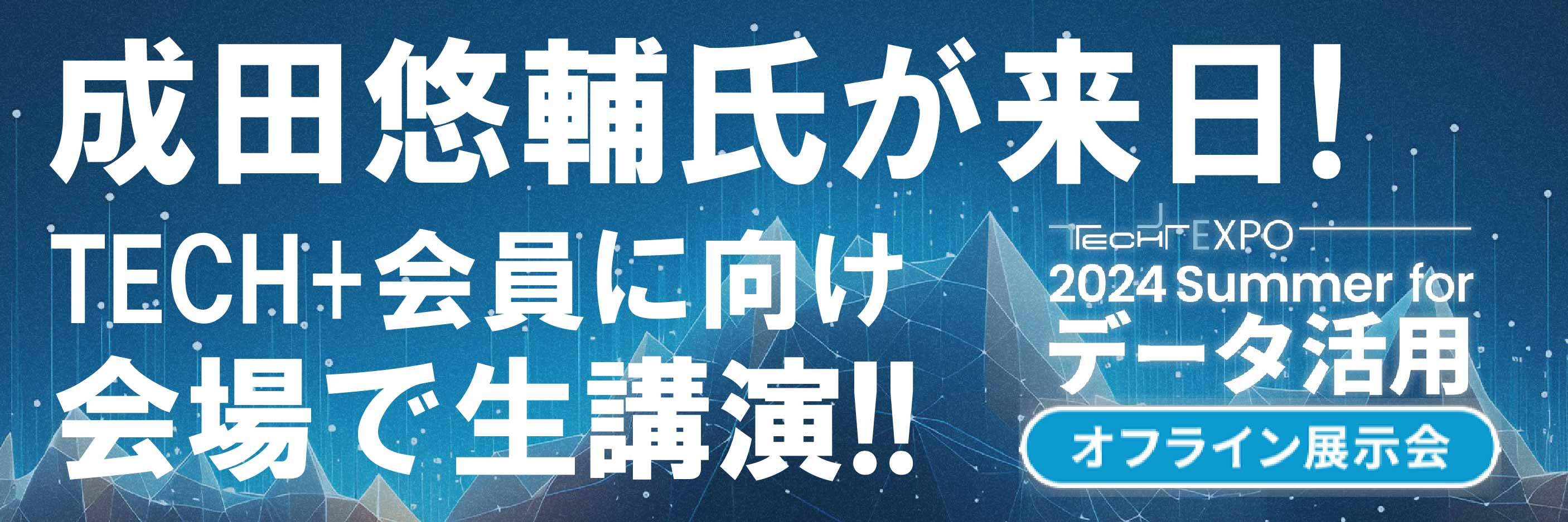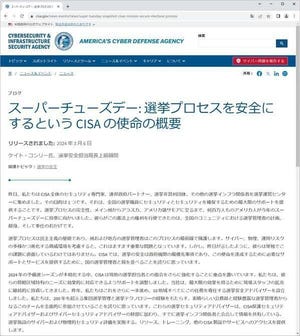Splunkは10月3日、都内でプライベートイベント「.conf Go Tokyo」を開催。同イベントにおいて、au PAYの残高管理システム開発チームが「au PAYを支えるシステム基盤の運用高度化とビジネス貢献 ~ Splunkとリアルタイムデータの力」と題して講演を行った。
講演を行ったのは、KDDI 技術統括本部 情報システム本部 基幹システム1部 開発2G 高垣湧成氏と、技術統括本部 情報システム本部 基幹システム1部 開発2G 鈴木萌那氏。両氏は、au PAYのインフラ構築および残高管理システムの開発を行っている。
同社は、2022年から2024年にかけての中期経営戦略において、5G通信事業を核として、金融、DX(デジタルトランスフォーメーション)、LX(ライフトランスフォーメーション)、エネルギー、地域共創の5つの重力領域の事業拡大を図っていく「サテライトグロース戦略」を掲げている。
5つの重点領域のうち金融に大きく関わっているのが、キャッシュレス決済サービスの「au PAY」だ。同社はau PAYを金融事業への入り口となる重要な接点として位置づけ、グループ各社と連携を取りながら事業拡大を図っている。
au PAYの2023年8月時点の会員数は3,300万人超。同サービスは、2014年にスタートしたau WALLET プリペイドカードが始まりで、2017年にはApple Payを開始し、QUICPayでの非接触決済がiPhoneで利用可能となった。そして、2019年にau PAYというサービス名でコード決済のサービスを開始した。