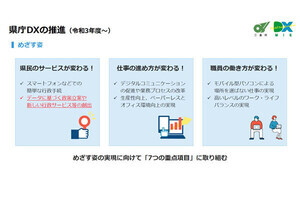公務員の特性の一つに横並び主義があります。しかし2021年に、副市長がDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を宣言したことで激震が走り、潮目が変わりました――こう話すのは、横須賀市 経営企画部次長 兼 デジタル・ガバメント推進室長の寒川孝之氏だ。
一般企業よりDXが遅れているといわれている自治体だが、横須賀市はどのような形でDXに取り組み、どんな成果を得ているのだろうか。
今回、横須賀市のDXについて、寒川氏と経営企画部 デジタル・ガバメント推進室 課長補佐 太田耕平氏に話を聞いた。
3年かけて、業務プロセスの変革を実現
寒川氏は、横須賀市がDXに取り組む背景について、次のように説明した。
「日本は人口減少が進んでおり、労働人口が減ると言われていますが、当市も同じです。将来的に、課題は減らないにもかかわらず、現在の半分の人員で運営していかなくてはならないことが予想されます。こうした事態に対処するには変革が必要です」
とはいえ、他の企業・組織と同様、横須賀市においてもDXがすぐに進んだわけではなく、試行錯誤を重ねながら進めてきたという。2020年は、「“なぜDXをやらなければならないのか”といったムードもありました」と、寒川氏は当時を振り返る。
横須賀市のDX推進策の一つに、電子決裁システムの利用がある。同市は20年以上前に電子決裁システムを構築したものの、実際には、簡易な決裁は紙で決裁が行われていた。その背景には、行政文書は管理規定によって処理が決まっており、そこで紙での決裁が認められていたことがあったという。
「せっかく電子決裁システムがあるのに、使わないのはおかしいでしょう。私はずっとそう言っていました。そこで、3年かけて業務プロセスの変革に取り組みました」と寒川氏。総務課のメンバーに啓蒙を図り、規則を改正し、電子決裁システムの利用に漕ぎつけた。
「紙ベースのワークフローでは、紙文書を探して、それを監査の時に渡さなければなりません。電子決裁システムを使えば、このフローを省けます。電子決裁を使えばだれもがラクになるのに、なぜ使わないのか疑問でした。何十年前に作られた条例に縛られて市民に負担をかけているのはおかしな話です。われわれは市役所文化を破壊します」と、寒川氏は笑顔で話す。
インパクトが大きかった「書かない窓口」
もう一つ、横須賀市のDXにインパクトを与えた取り組みが「書かない窓口」だ。テレビや新聞で取り上げられたので、ご存じの人もいるだろう。「書かない窓口」は、市役所窓口における住民異動手続きなどの簡素化を目指すサービスだ。
「書かない窓口」では、住民異動手続きにおいて、ホームページ上で簡単な質問に順番に答えていくだけで必要な手続きを調べられ、かつ、それらの手続きに必要な届出書類等を電子で一括して作成できる。
コロナ禍の2021年に「書かない窓口」は導入され、繁忙期である3~4月の最大待ち時間を100分から38分に短縮したという。その導入効果が評価され、政府主催の「夏のDigi田(デン) 甲子園」実装部門ベスト4に選ばれた。
また、寒川氏はデジタル化の具体例として、新型コロナウイルスの対応業務を挙げた。新型コロナウイルス第7波の到来により、保健所がパンクしたことから、RPAを導入した。
「国が新型コロナウイルスの患者の情報を入力するシステムとしてHERSYSを立ち上げましたが、神奈川県ではそこからデータを抽出して独自の受付リストを作っていました。第7波が来たことで、保健所の担当者が4、5人で1000件近くのデータを処理しなければならなくなり、事態を収拾すべく、われわれが飛び込んでいきました」
寒川氏のチームが業務プロセスを見直し、RPAを活用してデータの入力を自動化する仕組みを構築したという。
「書かない窓口」や新型コロナウイルスのRPA導入について、メディアで報道されたことで、職員がDXの取り組みを知る機会が増えた。加えて、「書かない窓口」、新型コロナウイルスのRPA導入が成果を出したことで、市議会が評価してくれ、予算の取り方も変わってきた。
さらに、全部局長が集まる会議体において、副市長がDXについて、「いつまでに、何をやるかを可視化する」ことを宣言した。ここで、部長クラスで「本気でDXをやらないといけない」という機運が生まれたとのことだ。「2021年が大きな転機となりました」と、寒川氏は話す。