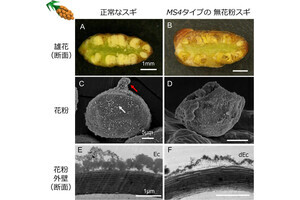東京大学(東大)と科学技術振興機構(JST)の両者は9月6日、植物に定着する「内生糸状菌」(カビ)が有する1つの菌二次代謝物生合成遺伝子クラスターが、共生から寄生への多彩かつ連続的な菌の感染戦略を支えていることを明らかにしたと発表した。
同成果は、東大大学院 総合文化研究科の晝間敬准教授、同・大学院 新領域創成科学研究科の岩崎渉教授、同・大学院 農学生命研究科の田野井慶太朗教授、同・大森良弘准教授、北海道大学大学院 理学研究院の南篤志准教授、理化学研究所 環境資源科学研究センターの岡本昌憲チームリーダー、薬用植物資源研究センターの佐藤豊三客員研究員、奈良先端科学技術大学院大学の西條雄介教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のオンライン学術誌「Nature Communications」に掲載された。
植物と共存する微生物には、有益な共生菌と、有害な寄生菌があり、それらはこれまで大きく異なる存在とされてきた。しかし近年になって、1つの菌が、周囲の環境条件や植物の状態に応じて共生から寄生へと連続的に変化しうることが示唆されるようになたという。
その一方で、その共生と寄生の違いや、共生から寄生へと連続的に変化していく際に必要な菌の分子的基盤は、未解明だったとする。そこで研究チームは今回、糸状菌の同種菌株(Colletotrichum tofieldiae、以下「Ct」)を世界中から入手し、最初にそれらが植物に与える影響を調査したという。
調査の結果、同種菌株の大半は、可溶性リンが枯渇した環境下で植物成長を促し、仮に単離された場所や植物が異なっていても、植物成長促進機構はCt株中に保存された性質であることが考えられたとする。一方で、調査されたCt株の1つはほかの共生型とは異なり、モデル植物のシロイヌナズナやコマツナの成長を著しく阻害する寄生菌として振る舞うことが確認された。
続いて、共生性と寄生性を分かつ分子基盤の同定のため、それらに感染した植物のトランスクリプトームの比較解析が実施された。すると、寄生型Ctへの感染時にのみ植物の「アブシシン酸」(ABA)応答経路の関連因子が活性化し、同経路が寄生型の植物成長阻害効果に必要であることが判明したとする。
次に、なぜ寄生型感染時にのみABA応答が活性化するのかを調べるため、菌側のトランスクリプトーム解析が行われた。その結果、ABA(もしくはその前駆物質や類縁化合物)とbotrydialの二次代謝物の生合成を行うと予測された生合成遺伝子群が、寄生型の1つのゲノム領域にまとまってクラスター化(ABA-BOTクラスター)しており、寄生型が植物根に感染中に活性化することが見出されたとのことだ。
なお、共生型も同様のクラスターを有しているが感染中に誘導されなかったことから、寄生型Ct株によるABA応答の活性化や植物成長阻害に関連していることが示唆されたとする。そこで、同クラスターに座乗するABA合成酵素やbotrydial合成酵素を欠損した菌遺伝子欠損体株を作出し、植物への接種を行ったところ、ABA応答の活性化が認められなくなったという。