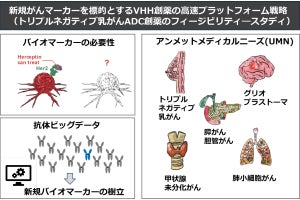京都大学(京大)は8月29日、がん患者の苦痛のうち、痛みや呼吸困難などの自覚症状を評価する方法を、機械学習を用いて評価する方法を開発したことを発表した。
同成果は、京大 医学部付属病院 緩和医療科・緩和ケアセンターの恒藤暁教授、同 嶋田和貴特定講師らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
日本では、主にがん医療に焦点を当てた政策の一環として、緩和ケアが発展してきた。がん治療の発展と共にがん患者の平均余命が延長した昨今では、緩和ケア専門の作業者の人手不足なども影響し、がん患者への緩和ケアの主な提供者が一般の医療従事者に移行しつつあるという。しかし一般診療では、緩和ケア以外の幅広い業務も行う必要があるため、詳細かつ適切な評価を行う時間が十分に確保できないことがあるとする。
しかし一方で、予測や判別に優れた機械学習を診療支援に応用する試みが、世界的な潮流になりつつある。そこで研究チームは、機械学習をがん患者の症状評価に活用できれば、スマートフォンやタブレット端末などを介したアプリケーション形式で一般医療従事者を支援し、最終的にはがん患者の利益につながると考えたとのこと。そして、2015年8月から2016年8月にかけて自ら診療したがん患者213人の診療情報を対象として、後方視的研究を実施したとしている。
今回の研究では、一般の医療従事者、中でも若手の医師や看護師、介護士が最終的なアプリケーションを使用することを当初から想定。そのため、誰でも観察で評価できる他覚症状を機械学習の入力系として利用することを試み、症状のうち観察で評価できる客観的要素の多い症状を「目に見える症状」(以下「可視症状」)として抽出して、残りの主観的要素の多い症状を「目に見えない症状」(以下「不可視症状」)とした。研究チームによれば、この分類が今回の研究における最大のポイントだという。
そして分類をもとに、患者背景と可視症状の情報から、患者の不可視症状を予測する系を作成。機械学習としてはポピュラーな手法の1つである決定木分析により、不可視症状(痛み、呼吸困難、疲労、眠気、不安、せん妄、不十分なインフォームド・コンセント、スピリチュアルな問題など)を予測したところ、精度、感度、特異度の最高値/最低値はそれぞれ、88.0%/55.5%、84.9%/3.3%、96.7%/24.1%だったとする。
これらの結果について研究チームは、成人のがん患者のみを対象にしている点や外来患者数が対象に少ない点などを考慮し、さらなる研究が必要だとしたうえで、これらの結果に基づくアプリケーションが、一般の医療従事者と同程度に症状評価ができる可能性を示したとしている。そして、この成果が、がん患者における症状のより良い評価を介して、QOLの改善に寄与しうるものだと結論付けている。