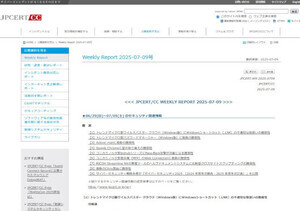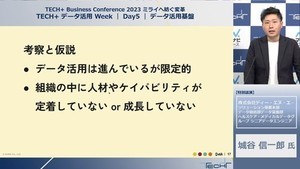ファナティクス・ジャパンは2018年の日本市場参入以降、日本のスポーツマーチャンダイジングやライセンス事業で多くのスポーツチームと連携。「ファン至上主義」を掲げ、グッズの企画・販売からECサイトの運営まで広く手掛けてきた。中でも昨年、読売巨人軍との長期パートナーシップ契約を締結し、大きな話題となったことは記憶に新しい。同社はなぜ、次々にチームの信頼を獲得し、ビジネスを伸長できているのか。
ファナティクス・ジャパン代表の川名正憲氏に、同社が重視する「ファンとの関係性」を切り口に、マーケティングの考え方について詳しく伺った。
目指すは「世界最大のスポーツデジタルプラットフォーム」
――初めに、ファナティクス・ジャパンについて簡単に教えていただけますか。
本社が米国にあり、日本へは参入から今年で6年目を迎えます。元々はスポーツのグッズを取り扱うライセンスビジネスをやってきた企業ですが、ここ数年は事業領域を拡大し、世界最大のスポーツデジタルプラットフォームを目指しています。
我々は、ファナティクスの語源となっている「fanatic(熱狂的、狂信的)」にもあるように、ファンの熱狂を大切に考えています。いわば「ファンのために存在している」会社なんです。そんなスポーツファンに対してのナンバーワンブランドになることが、グローバルで大事にしているビジョンですね。
――日本市場で特に注力している領域はどこですか?
当社では複数の事業領域を持っていますが、日本ではコマース事業が中心です。ファナティクス・ジャパンではスポーツファンが求めているものを、タイムリーに企画・製造・販売まで行えるようなサプライチェーンを構築しています。企画から製造のスピード感や、販売後にストレスなく購入いただけるビジネスモデルが我々の強みですね。
――ファナティクス・ジャパン独自のサプライチェーンについて、特徴的な部分を教えてください。
スポーツファンの需要は、特定のタイミングに一点集中するケースも少なくありません。試合が終わる時間帯や、優勝した瞬間などのタイミングでも耐えられるようなサーバーの構築により、サイトの回遊スピードを落とさないようにすることを大事にしています。システムインフラについてはグローバルで年間数百億円規模の投資を行っているので、その時のトレンドに即した整備を行える点が特徴ですね。
「ファン至上主義」を貫くための注力ポイント
――日本のスポーツファンについて、どのように分析していらっしゃいますか。
日本におけるファンとスポーツの関係には、米国や欧州と比べると独特な雰囲気があります。例えば、米国では住民の方々が地元チームのウェアを着て街を歩いている光景が当たり前に見られるほど、スポーツが「地域に密着した日常のカルチャー」になっています。
一方で、日本ではスポーツを「非日常体験」と捉えるカルチャーが根強いと感じます。アリーナで応援歌を歌ったり、仲間と盛り上がったりする”濃い”関係性を築いているのは、それが非日常的な体験だからでしょう。これは、我々の商品開発でも意識していることで、非日常体験を楽しむ応援グッズの重要性を感じていますね。
――では、そんな日本のスポーツファンとより良い関係性を作るために意識していることはありますか?
ファン至上主義をうたっている我々にとって、「ファンが今何を求めているのか」はとても重要な観点です。ユニフォームやタオルなどの定番品を大事にしつつ、選手がその時々で作った記録やパフォーマンスにもアンテナを張っています。
-

同社がリリースした「ペッパーミルTシャツ」は大きな話題を呼んだ
――タイムリーに盛り上がりを形にしていくには、チームとの連携も欠かせませんよね。
そうですね。間違いなく大事なポイントです。我々はただのグッズ委託業者ではなく、マーチャンダイズパートナーとしてチームと連携しています。ファナティクス・ジャパンが企画した商品はもちろん、チームから発案された商品も多いです。今はSNS上の声もタイムリーに拾うことができるので、いろいろな情報を駆使しながら商品企画を進めていますね。
読売巨人軍とナイキをつなげたビッグプロジェクトの裏側
――直近では、読売巨人軍との長期パートナーシップ締結を発表されました。締結までの経緯を教えてください。
私自身、6年前に日本で事業を始めたときから読売巨人軍のパートナーになることが一つの目標でした。ただ、読売巨人軍は歴史のある球団なので、我々のような新しい会社と組んでもらえるのだろうかと思っていたんです。
手応えを感じ始めたのは、2019年に福岡ソフトバンクホークスと提携して徐々に結果が出てきた辺りです。その前後にも日米野球やメジャーリーグの開幕戦で、東京ドームでの興行が成功するなど成果を積み上げていました。次のステップとして巨人軍への提案を模索する中で生まれたのが、ファナティクス・ジャパン、読売巨人軍、ナイキによる「3社パートナーシップ」という座組です。
当時、巨人軍はちょうど新たなユニフォームサプライヤーを探している最中でした。一方で、ナイキは日本の野球チームの支援にしばらく手を挙げていない時期が続いていました。そこで、我々とナイキがNFL(アメリカンフットボール)やMLB(メジャーリーグ)とグローバル単位で行っている3社パートナーシップの方式を巨人軍にも提案できないかと考えたのです。
――3社パートナーシップとは、どのような座組なのでしょうか。
ナイキが自分たちで商品を作るのではなく、ファナティクスが入ることで相乗効果を生み出せる取り組みです。具体的には、ナイキ側はマーケティングやスポンサーシップの部分にフォーカスして、ファナティクスがナイキブランドのライセンスを使って商品化や製造を行います。かねてから我々は日本の球団とのビジネス経験があり、またMLBでの実績も持っています。そういったこれまでの成功パターンを読売巨人軍でも再現しようと考えて、3社パートナーシップを提案し、締結に至りました。
――プロ野球のシーズンも開幕して、春先の売上や傾向も見えてきたと思います。
1月にオンラインストアをオープンし、その後WBCを経て東京ドームの実店舗をオープンしました。売れ行きは我々が想像していた以上です。試合当日の売上だけではなく、試合がない日でも観光でいらっしゃった方がグッズを購入してくださっています。
選手のグッズでは、岡本和真選手などWBCに出場していたメンバーをはじめ、ベテラン勢の長野久義選手、松田宣浩選手のグッズも手に取っていただくことが多いですね。ベテランから新加入のメンバーまで幅広く売れているところが日本のマーケットの特徴だと感じています。
――読売巨人軍と、今後取り組んでいきたい施策があれば教えてください。
3社パートナーシップだからこそ実現できる商品の開発や販売をより進めていきたいです。巨人軍とナイキのブランドを掛け合わせると、ライフスタイルの中に溶け込める違和感のないデザインになると思っています。このブランドをかっこいいなと思ってくれる人が増えるような世界観を作っていきたいですね。
ファナティクス・ジャパンが見据える“次”の領域
――最後にファナティクス・ジャパンとしての今後の展望を教えてください。
昨年のFIFAワールドカップや、今年のWBCの盛り上がりを見ると、今後グローバルなスポーツイベントが日本で開催されるケースも増えてくるかなと思います。コマース事業としては、こういったグローバルなイベントのコンテンツの価値を最大限高められるパートナーとなりたいです。
長期でパートナーシップを結んでいるチームの方々については、ファンの方により良い購買体験を提供できるようにしたいと考えています。「また同じ感じだね」と思われないように、新たな商品の開発や店舗づくりを進めていきたいですね。
また、ファナティクス・ジャパンとして、スポーツベッティングなどの新たな領域への参入も目指したいですね。CRMも活用して、あらゆるお客さまの情報を生かしたビジネスを進めていきたいと思います。また、現在グローバルではコレクタブル事業やゲーミング事業への参入を進めています。新たな領域を含め、あらゆるファン情報を生かして「世界最大のスポーツデジタルプラットフォーム」を目指していきます。