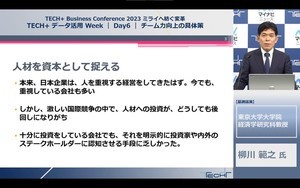日本の国際競争力は決して高いとは言えない。IMD (International Institute for Management Development、国際経営開発研究所)が作成した2022年版の「世界競争力年鑑」における国際競争力ランキングでは63か国中34位であり、特に「ビジネスの効率性」では51位と今ひとつ振るわない。その原因の1つとも考えられるのがDXの遅れである。2020年にIMDが発表した「世界デジタル競争力ランキング」では、日本は63か国中27位と、上位に食い込めていないのが現状なのだ。
このような状況を打破するには、積極的なDXで生産性を高め、働き方を改革していく必要がある。だが、歴史や伝統がある、あるいは大きな規模の企業ほど、改革が一筋縄ではいかないのも事実だ。
そうした中、いち早くDXを推進したのが安川電機である。5月15日~26日に開催された「TECH+ Business Conference 2023 ミライへ紡ぐ変革」の「Day1 ものづくりとサービス」に同社 代表取締役会長の小笠原浩氏が登壇。自社のDXの取り組みとそこから得た学びについて話した。
大規模なシステム導入には“覚悟”が必要
安川電機は1915年に創業した老舗企業だ。「メカトロニクス」という言葉を提唱した企業としても知られており、現在はサーボ・コントローラやインバータといったモーションコントロール事業、ロボット事業、システムエンジニアリング事業などを展開。グループ企業は68社、連結売上収益は5,500億円に達しており、売上における海外比率は70%に上るというグローバルカンパニーでもある。
長い歴史を持つ大規模な企業はどうしても改革が遅れがちになるが、安川電機には以前から「積極的に新しいデジタルテクノロジーを導入する文化が根付いていた」と小笠原氏は振り返る。もちろん、デジタル化が根付いているというだけでDXが上手くいくとは限らない。では、同社はいかにしてDXに取り組み、成功させているのだろうか。
その背景を探るには、安川電機におけるデジタルテクノロジー導入の流れを知る必要がある。
同社が業務プロセスにデジタルテクノロジーを導入したのは1970年代後半にさかのぼる。部品の調達をEDI(Electronic Data Interchange、電子データ交換)化し、80年代前半にはCAD情報から設計・製造・試験までを一貫管理するシステムを構築した。さらに、96年からはペーパーレス化を推進、4,000台のPCを連携したシステムを構築し、社内の決裁印を廃止するなど、当時としては非常に先進的な取り組みを行っていた。
だが、全ての取り組みが順調に進んだわけではない。
「2000年に生産システムにERPを導入したときには、大混乱が起きたのです。3年をかけて安定稼働までこぎつけ、先行していた米国のシステムノウハウも生かしながらグローバル展開をしましたが、こういったシステムを導入する際には“覚悟”が必要であることを学びました」(小笠原氏)
ただ、そのERP中心のシステムも今となっては古い構成と言わざるを得ず、システム毎にデータが分散したり、セキュリティが十分でなかったりと、さまざまな課題が見えてきたという。
そこで同社は2018年、社長がDX推進部門の長も兼務し、システムの統合とグローバルデータの一元化、セキュリティ対応を進めることを決定。この動きが、安川電機における“DX前夜”とも言えるものになった。
データの統合がDXへの第一歩
ここからは具体的な安川電機のDX推進の取り組みについて見ていこう。
同社のDXにおけるビジョンは「データを世界の共通言語に」である。具体的にはデータ化とデータの統合により、生産や製品・サービスなどの事業管理、そして経営管理をも行い、最終的に「デジタル経営」を実現することを目的としている。
その際、注意しなければならないのは「1データ=1コードの原則」だと小笠原氏は言う。つまり、同じデータに対して複数の定義付けをしてはならず、同社の場合、勘定項目や品目コード、取引先コードなどをグローバル68社で完全に統一する必要があるのだ。
非常に困難な挑戦ではあるが、「システム的にも、実際に統一できるまでには30年かかることを覚悟している。これだけは部門長を交代させてでもやらないと進まない」と小笠原氏は決意を口にする。なぜデータ化と統合化にこだわるのか。それは、データを統合できなければ、DXを最終的に成功させられないからだと同氏は続けた。
攻めと守り、両輪のDXを進める変革
では、安川電機が考えるDXとはどのようなものなのだろうか。
小笠原氏はDXには「守りのDX」と「攻めのDX」の2つがあると説明する。
守りのDXとは業務改革を目的としたDXのことだ。データ化と統一化はそのためのファーストステップであり、そのデータを基に経営状況のリアルタイムでの可視化や、働き方改革を行っている。
小笠原氏は、経営状況が可視化されたことにより、連結決算データがこれまでよりも圧倒的に早くまとめられるようになるなど、すでに業務効率化の効果が出ていることも明かした。
また、同社は働き方改革の推進に向けて「働きやすい会社を目指すのではなく、やり甲斐のある会社を目指す」をスローガンにしている。実際に、仕事の成果をデジタルで管理して、公平な社員評価を行う「デジタル評価」の制度もあるそうだ。
攻めのDXとは、社外の顧客やサプライチェーンとのデータ連携、またデジタルツインの実現による顧客価値の創出といったビジネスモデル自体の変革である。
こうした守りと攻めのDXを両輪で進めていく上で重要なのは「トップダウンと現場の連携」だと同氏は話す。
「現場に任せきりにせず、トップが参加することが大事です。また、現場との連携も必要です。時に、ITリテラシーや過去の成功体験が邪魔をして、経験豊富な現場の部課長層が最大の壁になってしまうこともあります」(小笠原氏)
コンサルやベンダーを活用する際に気を付けることとは
このような新たな取り組みに挑戦する際、企業が頼りがちなのがコンサルティングサービスだ。しかし、コンサルの活用にも注意が必要だと小笠原氏は指摘する。
「コンサルやベンダーの利害が自社と必ずしも一致しない場合もあります。(中略)コンサルは時期や範囲を絞って活用することが重要だと私は考えています。また、BtoBのニッチビジネスはDXの成功モデルがないので、DIY(内製化)を徹底することも心掛けましょう」(小笠原氏)
実際に安川電機がDXを進める上でさまざまな学びがあったと同氏は語る。
例えば、反省点としてコンサルを使うタイミングが早すぎたことがあるという。現場は最初からコンサルを使いたがるが、その結果コンサルと現場のレベル感が合わなかったそうだ。小笠原氏は「コンサルは煮詰まった状態で使うべき」だと聴講者へアドバイスを送った。
また、DX推進以前から活用しているソフトウエアを否定するのではなく、むしろそのまま使い倒すことも推奨した。
「ソフトウエアは腐るものではないのですから、使えるものは使いましょう」(小笠原氏)
先行している同業他社があるなら、積極的に情報を得ることも重要だ。特に、表には出て来ないような苦労話に大きな価値があるという。一般的にコンサルやベンダーに対する評価などは表には出にくいものの、これからDXを推進する企業にとって貴重な情報となるそうだ。 このように小笠原氏は、聴講者へ自身の経験から学んだことを伝え、講演を締めくくった。
* * *
小笠原氏が講演で語ったように、グローバルに展開する大企業のDX推進の道のりは平坦ではない。創業以来、積極的にテクノロジーを導入し、改革を行ってきたカルチャーを持つ同社ですら、DX推進を軌道に乗せるまでには多くの苦労があった。
もっとも、これからDXに取り組もうと考えている企業にとっては、本公演で小笠原氏が語った経験談が大いに参考になるに違いない。そうして日本企業全体のDXが加速すれば、日本の国際競争力向上が期待できるだろう。