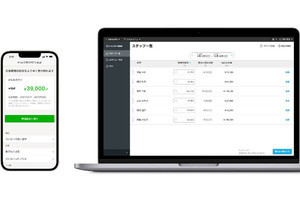リクルートワークス研究所は6月8日、全国約5万人の就業実態を調査する「全国就業実態パネル調査」を実施し、これに基づきまとめた指標「Works Index」について、2022年の働き方を総括し、コロナ禍が続く日本の働き方はどういう状況になっているのか発表した。
本稿では、この発表に伴い行われた報道関係者向けの説明会の一部始終を紹介する。今回の会見には、リクルートワークス研究所の研究員兼アナリストの孫亜文氏、小前和智氏が登壇した。
5つの項目からなる「Works Index」
「Works Indexは、日本における個人の働き方を可視化し、そのうえで状態を評価することを目的とし、個人が生き生きと働き続けられる状況を理想に作られた指標のことで、5つの項目からなっています」(孫氏)
ここで語られた項目は、「就業の安定(安定性)」「生計の自立(経済性)」「ワークライフバランス(継続性)」「学習・訓練(発展性)」「ディーセントワーク(健全性)」の5つだ。
この5つには順にIndexⅠ~Ⅴが振られており、それぞれのIndexには「Indicator」と呼ばれるそのIndexの評価ポイントの構成要素が存在する。
それぞれのIndexにおいて、構成要素からIndexの得点を算出しており、0~100ptの間の値の中で100ptをとれば、理想的な状態になっていることを示しているのだという。
それぞれのIndexにおけるIndicatorは以下の通り。
就業の安定(IndexⅠ)
就業の安定は、正規雇用者・非正規雇用者といった就業形態ではなく、実際に就業が安定しているか、または安定する可能性を示したIndexである。働く意欲があったとしても働けない状況や、仮に働いていたとしても、契約満了などの会社都合により退職に追い込まれる状況にないことが好ましい。
生計の自立(IndexⅡ)
生計の自立は、個人の労働所得がどの程度自分の生活を成り立たせているかを示すIndexである。個人の労働所得に重きを置いており、家計単位ではなく個人で評価をしている。自身の労働所得で自分の生活を成り立たせている状況が望ましい。
ワークライフバランス(IndexⅢ)
ワークライフバランスは、適切な労働時間や休暇などがあり、無理なく働くことができるかを示すIndexである。残業時間が長い、休暇がとれない、労働時間を自分で調整できない状況は望ましくない。残業がなく、休暇も十分にとることができ、勤務時間や勤務場所を個人が選べる環境であることが望ましい。
学習・訓練(Index Ⅳ)
学習・訓練は、自己啓発・企業内訓練や仕事を通じて本人が成長することで、今後の就業にもつながるのかを示したIndexである。OJTやOffJTといった企業内での研修や成長機会があり、自分でも自己啓発をし、仕事を通じて成長している状態が望ましい。
ディーセントワーク(IndexⅤ)
ディーセントワークは、最低限保証されるべき就業条件が満たされているかを示すIndexである。仕事量や負荷が適切であり、処遇が公平であり、ハラスメントがなく、安全衛生上問題がない状態が望ましい。
2022年は「残業時間は増えず、有給休暇取得率は高まった」1年
それぞれのIndexの得点から、日本における働き方を5つの側面から可視化したところ、2022年は「継続的な就業も、新たな就業機会も増えてきた一年」「自身や配偶者の収入だけでは生活費を十分にまかなえない層がゆるやかに増加」「残業時間は増えず、有給休暇取得率は高まる」「勤務時間・場所の自由度は、コロナ禍前の水準を上回る」「仕事に関する学び機会は回復傾向」という特徴を持った1年だったことが分かったという。
「Works IndexⅠ『就業の安定』による分析結果から、『継続的な就業も、新たな就業機会も増えてきた一年』という特徴を持つ1年であったことが分かりました。『就業の安定』の項目は、2022年には66.3ptを記録していますが、前年の2021年は65.9ptだったことから、0.5pt上昇していることが分かります。また、Indicatorの内訳をみると、すべてのIndicatorの水準が上昇していることも分かっています」(孫氏)
またIndicator I-1「2022年12月時点で就業しているもしくは就業意欲が高い(就業・就業意欲が高い)」に関して詳しく見てみると、2021年の69.0ptから2022年の69.3ptへと0.4pt上昇した。
JPSED(全国就業実態パネル調査)を用いて、同一の個人について、就業と非就業間の移動状況をみると、2021年時点の就業者の多くが2022年も就業継続したことが分かるのに加えて、2021年時点の非就業者(失業者、非労働力)では、2022年に就業するようになった層も増えていたという。
またWorks Index Ⅲの「ワークライフバランス」による分析によるとIndicatorⅢ-2「休暇が取得できている(休暇取得)」とIndicatorⅢ-4「勤務時間や場所の自由度が高い(勤務時間・場所自由度)」の上昇が大きいことが分かったという。
反対に、IndicatorⅢ-1「残業時間がない・短い(残業がない・短い)」に関しては、前年からほぼ横ばいで推移している。
「総務省の『労働力調査』を用いて、2022年の年間就業時間をみると、1818時間と前年の1817時間からあまり変化していないことが分かります。週60時間以上の長時間労働の割合も、就業者では5.6%、雇用者では5.1%と、前年からほぼ横ばい推移となっています」(孫氏)
このような結果からIndexⅢからは「残業時間は増えず、有給休暇取得率は高まる」という特徴が挙げられるようだ。