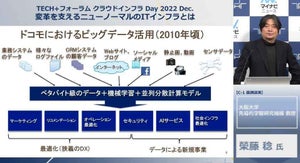ガートナージャパンは4月4日から4月6日、「ガートナー データ&アナリティクス サミット」を開催した。4月5日の基調講演には同社シニア ディレクター、アナリストの一志達也氏が登壇。「志を持ち、意を決して、内側からの変革をリードせよ」と題して、変革を進めるリーダーが持つべき意識とデータアナリティクスの正しい使い方を語った。
-

シニア ディレクター、アナリストの一志達也氏
分析者次第でデータの見え方は変わる
一志氏は講演の冒頭、日本経済の現在地について述べた。アメリカ、中国、インド、韓国と比較したデータを引用し「(4カ国と比較して)日本は遅れていると聞くが、私はそうではないと思う」と提言。その裏付けとして一志氏が強調したポイントは下記の3つである。
- 日本の人口は中国、インド、米国に比べて少ない
- GDPはインドよりも上位の3位で微妙に増加している
- 1人当たりのGDPは2番目。人口がはるかに多いインドに対して成長している
グラフを見ると、日本は世界経済のトップ3を走っていて、人口爆発や経済成長をしているインドや隣国の韓国を上回っている。一見、状況は楽観的なように見えるが、実際は世界のGDPにおける第4位はインドではなくドイツ、第5位は韓国ではなくイギリスだ。つまり、比較する範囲を広げればデータの見え方は変わってくる。
-

一志氏が参照したGDPの比較データ/出典:ガートナー(2023年4月)
日本と比較された4カ国はあくまで一志氏がこの講演のために独自に選んだ国々であり、うのみにすれば確証バイアスを起こしかねない。データは分析者や見え方次第で読み取れる意味が大きく変わるからだ。人は、こういった「誰かの言葉」によるデータを見てしまうと先入観を与えられることになり、判断を誤る可能性がある。
データを可視化して語ることはデータ活用の基本だが、偏見や思い込みが付きまとって正しい結果を導き出せないリスクもはらんでいるのだ。「データのスペシャリストには、人間の確証バイアスを理解して、一般の方々が(データを)正しく読み解けるようにする役割を担ってほしい」と一志氏は話す。
正しいデータであっても、そのデータをいかに分析・解読したかによって人に与える印象は大きく変わっていく。だからこそ、分析者はデータリテラシーを身に付ける必要があるのだ。
日本企業を救うデータアナリティクスの重要性
話題は日本の現状に戻る。GDPの低下や少子高齢化問題など、日本経済の衰退を危ぶむ声は少なくない。しかし、一志氏はそうしたピンチを踏まえた上で「日本は悪いところばかりではない」と断言。WBCでの世界一、フランスで行われた洋菓子大会で日本チームが優勝したことを一例に「ほかの国が生み出したものを柔軟に日本文化に取り入れてグレードアップする力がある」と日本人の強さを説いた。
他の国と比べたマクロ視点で見ることも大事な一方、企業やチーム、社会を構成しているのは個人の力だ。個人が状況を見極めていくためには、正しい判断を下せるリーダーが周囲を導く必要がある。その判断の一助になるのがデータであり、一志氏は「広くデータを収集、分析した上で活動につなげていかなくてはいけない」とデータアナリティクスの重要性を説明する。データやAIの活用が当たり前となった今、企業はデータドリブンでビジネスを進めていく必要があるのだ。これを成功させ、日本がピンチを脱するためには「進化」が求められると一志氏は語る。 では、日本企業はどのように進化を遂げれば、変革へと進めるのだろうか。
変革を実現する「フェニックス戦略」と「リーダーの役割」
一志氏は、日本企業が「進化」し、変革へと進んだ事例として、USENと鎌倉紅谷を挙げた。いずれも、旧来のビジネスモデルを環境に合わせて変革した企業たちだ。
店舗での有線放送で知られるUSEN-NEXT GROUPは、インターネットの普及をきっかけに動画配信事業「U-NEXT」をローンチ。また、有線配信で培った既存顧客のネットワークを生かした店舗DXサービスもU-NEXTと並ぶ事業の二本柱となっている。
一方、鎌倉紅谷は創業70年を超える老舗和菓子メーカーだが、新社長の就任を分岐点に創業以来守ってきた商品パッケージを一新。その後は5年で販売額を2倍に伸ばし、今や社長が就任した当初の13倍の売上にまで成長しているそうだ。
-

鎌倉紅谷がデザインしたパッケージ/出典:ガートナー(2023年4月)
一志氏はこの2社のような変革を実現する戦略を「フェニックス戦略」と名付けた。窮地に立たされた鳥が火の中に飛び込んで若返るように、企業が再起するには火の中に飛び込むほどのインパクトが必要というわけだ。そしてこのフェニックス戦略において、リーダーの役割は、その先に待ち受けている未来を示し、皆を率いていくことである。
「データアナリティクスは事実や“事実に見えるようなこと”を示してくれますが、革新的なアイデアまでは生み出せません。事業の背景や資金調達などのビジネスシーンを描くのはリーダーの仕事です」(一志氏)
AIにどう向き合うべきか?
ここで一志氏は、データアナリティクスには欠かせないAIを活用した意思決定についても言及した。
ビジネスにおいて多くの示唆を与えてくれるAIだが、より精度を上げていくためには人間がこれまで積み重ねてきた意思決定内容をデータとして与える必要がある。「AIは良質なデータをえさに賢くなる」と一志氏が話すように、人間の意思決定データを基に、AIは成長していくのだ。
一志氏は、「AIの活動範囲は今後さらに広がる」とした上で、「AIを恐れるのではなく、自分たちにどんな価値をもたらすかを考えなければならない。AIを有効活用して、競争力に繋げていく方法を社内の誰かが考え、広く会社中の人たちに示して率いていく必要がある」と強調した。
まずは一歩踏み出す。リーダーが持っておきたい”Jump”の心意気
講演の終盤、一志氏が「外部に全てを依存していては進化ができず、データドリブンな組織になれない。データドリブンなビジネスを実現するために生まれ変わろう」と力強く語ると、会場にはヴァン・ヘイレンの名曲『Jump』が流れた。
一志氏曰く、ヴァン・ヘイレンは「Jump」の意味を「まず誰かとつながる行為」と定義しており、この曲自体が「君のつらい気持ちはわかるけど、それでも一歩前に踏み出そう、ジャンプしよう」という内容なのだという。
同氏は曲の一節を引用し、「やってみなければわからない時に勇気を出して挑戦するのがリーダーの役割。進化して生まれ変わった組織になるために力を合わせよう」と聴衆に呼びかけ、講演を締めくくった。