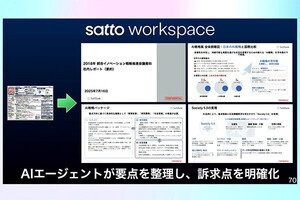原宿駅の改札を出てから竹下通りの入り口を横目に通り過ぎると、原宿外苑中学校(東京都 渋谷区)が見えてくる。卒業式を終えたばかりで少し寂しさの残る校舎では、体育館に1年生約90人が集まっていた。
同区に本社を置くMIXIは「課題解決型学習(Project Based Learning)」を支援するアプリケーションを開発し、同校の生徒に対し2月から4回の授業を実施してきた。3月20日にはその集大成となる5回目の授業が開かれた。
ゲーム開発に強みを持つMIXIが開発した教育アプリ
プログラミング教育の必修化に伴って、MIXIをはじめ東急、サイバーエージェント、DeNA、GMOインターネットグループら渋谷に拠点を構える5社が、区と連携して「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト」を展開している。
その中でも、唯一MIXIは中学校を対象とした支援を手掛けており、このほど、教材アプリケーション「MIXIブロックアイランド」と、問題解決手法として知られるデザイン思考を組み合わせた授業を開発した。今回はその試験的な導入の場として原宿外苑中学校が選ばれ、1年生が「街づくり」の授業の一環として授業に取り組んだという。
デザイン思考とは、課題解決を支援するアプローチの一つであり、このフレームワークに沿って課題の対象を理解し、問題を定義し、仮説を立て、検証を繰り返すことで、自分で情報を得る能力やチームで意見を出し合う能力などが身に付くと期待される。
今回同社が開発したアプリケーションは、街づくりと社会環境全体を簡略化したシミュレーション空間を構築するものだ。プログラミング言語に関する知識を持たなくてもノーコードで操作でき、工場や農地、住宅などをフィールドマップ上に設置すると、「電力供給」「水質保全」「健康・福祉」といった指標が変動する仕組みである。また、これらの各指標に伴ってSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)に示される17のゴールの達成スコアも変化する。
生徒らはこれまでの4回の授業の中で、適切な街づくりを進めるための課題解決型のカリキュラムに取り組んできた。解決すべき課題や理想の地域について各人が考え、それを6人ほどのグループで共有してから、どのような解決策が考えられるかをMIXIブロックアイランドを操作しながら検証を繰り返す流れだ。
例えば、「十分な地球温暖化対策」を実現するために、「クリーンエネルギーへのシフトや二酸化炭素の削減」が必要だから、「緑地を増やして」から指標を確認するといった具合だ。これを各グループで繰り返す。
シミュレーション結果は数値として確認できるだけでなく、csvファイルで出力できるため、表計算ソフトでのグラフ化やフィルタ検索も可能だ。
「テクノロジーを活用した課題解決は今後の必須スキルに」
これまで4回の授業に参加した生徒は、5回目となる今回の授業でグループごとに仮説とその検証結果を発表した。
自動車の排気ガスや温室効果ガスの排出を課題と感じたグループは、緑地の多い街づくりを目指して牧場を増やした結果をシミュレーションしたという。その結果、環境が改善され人口が増えるという結果が出たようだ。
またあるグループは、地域住民が住みやすい街を目指して住宅や店舗を増やし、ごみ焼却場も近隣に設置した結果をシミュレーションして、住民の快適さを追求していた。
授業に参加した駒崎彰一校長は「テクノロジーを活用して課題を解決するための力は、これから生きていくために必須の能力になるはず。非常に挑戦的な授業ではあるが、生徒たちにはそうした能力を身に付けてほしい。来年以降も、また新たにバージョンアップした課題解決型の授業を提供してきたい」とコメントしていた。
講師を務めたMIXI 開発本部CTO室の田那辺輝氏に話を聞くと、以下のように語っていた。
「今回はトライアル的な授業なので全5回の進行スケジュールを考えるのが難しかったが、時には生徒の背中を押しながらようやく今日の発表まで達成できた。今回の授業にとどまらず、今後もMIXIブロックアイランドを活用したいと思っていたので、アプリ開発の段階で、生徒が操作できる項目はなるべく増やすように工夫した。多くの生徒が授業を通じてSDGsについて知っている中で、17項目の目標まで落とし込んで具体的な施策を考えてもらえていたら嬉しい」