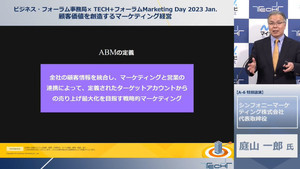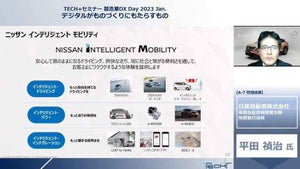経済産業省が2018年に公表したDXレポートで「2025年の崖」問題を提示し、日本企業におけるDXの必要性を強調したことは周知の通りだ。だが、日本の基幹産業である製造業のDXは、いまだ十分な進捗状況にあるとは言えず、海外に比べても遅れを取っているのは否めない。
では、なぜ日本の製造業はDXが遅れたのか。そして、その根本的な問題はどこにあり、どうすれば解決できるのか。
ビジネスエンジニアリングが2月16日に開催した年次カンファレンス「BE:YOND 2023」では、基調講演にビジネスエンジニアリング 取締役社長 羽田雅一氏、慶応義塾大学 商学部 准教授 博士(経営学)岩尾俊兵氏が登壇。「デジタル時代の日本(式)経営 ~逆襲の一手~」と題し、日本の製造業DXが海外に遅れをとった理由を説明すると共に、これからのグローバル市場で日本の製造業が優位に立っていくために必要なことについて講演を行った。
日本の製造業のDXが遅れた「決定的な理由」
日本の製造業になかなかDXが浸透しなかった原因として、羽田氏が挙げるのは「日本の製造業にはそもそもDXが必要なかった」点である。
かつて日本の製造業は、高い技術と確かな品質、そして現場主体の“カイゼン”による自律的な課題解決という強みを持っていた。そうした「現場力」こそが、日本の製造業の最大の長所だったと言える。
しかし、それは同じ文化的背景を持つ日本国内だけがマーケットだった時代の話だ。ビジネスがグローバル化し、サプライチェーンが複雑に絡み合う現在では、かつての日本企業が持っていた強みは十分に発揮されない。例えば、海外の工場に勤務する現地スタッフは日本とは異なる文化的背景を持っており、日本の製造現場の暗黙知は通用しないのだ。
そうした中で必要になるのが、きちんとしたルールやシステムだ。海外企業は早くからこのような多様化に伴う非効率性を克服するため、積極的なIT活用を進めてきた。一方の日本企業はクローズドな空間でのみ成り立つ効率性を追求してきたため、IT活用が遅れてしまったというわけだ。
日本的カルチャーの問題と経営の欧米化に対する違和感
羽田氏はさらに「個人的に根本的な問題になっていると思うもの」として基幹システムに言及した。
「ERPが日本に入ってきて30年以上経ち、機能も充足してきました。しかし、日本の製造業の多くが、会計ではERPを使えても、生産管理や販売管理で使いこなせていないのが現状です」(羽田氏)
ここでも原因となるのは日本的なカルチャーだ。欧米的な経営ツールであるERPを活用するには、できるだけ早く経営層に情報を届けることが重要だ。これまで現場力が最重要だった日本企業の多くは、この手法に抵抗感があり、そのせいで活用がなかなか進まなかったのだという。
一方で、羽田氏は昨今の日本企業における“経営の欧米化”に違和感を覚えるとも話す。
「最近流行りの経営理論に、ティール組織やマルチステークホルダーなどがあります。これらに既視感はないでしょうか。例えば、ティール組織とは“人を尊重する”こと。マルチステークホルダーとは“三方良し”の概念に似たものです。これらは、新しいようでいて、もともと私たち日本企業が持っていた良さと共通する部分があるのです」(羽田氏)
欧米のやり方を何でもかんでも取り入れるのではなく、日本企業が本来持っていた強みを認識することも重要なのではないか――羽田氏がそう考えるきっかけになったのが、慶應義塾大学商学部准教授の岩尾俊兵氏の著書『日本“式”経営の逆襲』(発行:日本経済新聞出版)だったという。
日本企業が抱える「2つの問題」、その原因は?
基調講演はここから、岩尾氏による動画講演に移った。
岩尾氏はまず、現在の日本企業が抱える問題として「経営者の孤立」と「従業員の困窮」を挙げた。経営者の孤立とは、人材の確保や育成、後継者の育成などに関する悩みであり、従業員の困窮とは、業務量や残業、人間関係などに関する悩みである。
これらは、どちらも経営層と現場層の関係に起因する問題だ。
「私は、中途半端な米国式経営の猿まねが、経営層と現場層の対立を激化させているのではないかと考えています」(岩尾氏)
岩尾氏はさらに、「これは決して懐古主義ではない」と続け、その根拠として世界のリーダーが日本の経営技術に注目している例を挙げる。
例えば、Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏だ。ベゾス氏はAmazonにて、「アンドン式システム開発」というシステム開発思想を実践したが、これは「システムに問題が生じたら、異常が発生した部分を切り離す権限を現場に与える」という手法であり、日本に古くからある、工場の生産ラインで異常が発生するとランプを点灯させる仕組み「アンドン」が源流になっているという。
「アンドン式システム開発はもともと、米国式経営ではありえないやり方でした。なぜなら、米国式経営では労働者と経営者は対立しているからです。そうした中で労働者に現場を止める権限を与えると無制限にストができてしまう。アンドン式システム開発は、経営者が現場を信頼していないとできないのです」(岩尾氏)
岩尾氏によると、この他にもティール組織や両利きの経営など、海外から輸入された経営技術の多くが、日本式の経営技術にヒントを得たり、概念がコンセプト化されて逆輸入されたりしたものなのだという。
では、こうした日本企業の「強み」の本質とは何だったのか。
日本企業が持つ「強み」の本質
岩尾氏は「イノベーションの民主化」という言葉で説明する。
「米国式のやり方とは、少数のエリートに深く経営教育を行い、その報酬もエリートが独占するという“イノベーションの独占化”です。一方、日本企業は多人数に浅く経営教育を行い、その結果得られる報酬は比較的平等に配分される“イノベーションの民主化”を実践してきました。両者の違いは報酬にも表れています。日本企業の経営者と新入社員の報酬差は7~8倍程度ですが、米国では1000倍にも達します」(岩尾氏)
イノベーションの民主化により、経営教育を多人数に浅く行うとどんなメリットがあるのか。
「経営教育によって成果が仮に1%得られるとします。仕事とは他人との協力で成り立つものだから、成果は“べき乗”で向上します。すると、10人なら約1.1倍になり、100人なら3倍近く、1000人なら20000倍になります」(岩尾氏)
たった1人のエリートを育成しても、常人の20000倍の力は発揮できない。それなら、薄く広く多人数に経営教育を行うべきというわけだ。
グローバル市場で日本企業が優位に立つには?
こうしたことを踏まえた上で、日本企業はこれからのグローバル競争で優位に立つ方法を考える必要がある。
岩尾氏は「米国から学びつつも、日本のいいところを残すべき」だと見解を示す。日本企業は製品自体や製品を生み出す組織能力には長けているものの、その組織能力を生み出す経営コンセプトが弱い。そこを補強するために海外から経営コンセプトを取り入れることが多いが、そうした“借り物”の経営技術に頼ってしまうことが最大の問題だと岩尾氏は言う。
例えば、経営者が海外から入ってきた流行りの経営技術を強引に導入し、現場がついていけず疲弊して不信感を募らせる――といった事態は多くの企業でありがちだ。
「どんな場所にも世界一のノウハウはあります。自社の強みを抽象化して把握しなければ、いじってはいけないものをいじってしまい、強みを自己破壊してしまうのです」(岩尾氏)
岩尾氏の講演を受け、羽田氏は「『イノベーションの民主化』という言葉が印象的だった」と述べた上で、「イノベーションの民主化のためには、データの民主化も重要になるのでは。そのためにもデジタルの力が必要」と力を込める。
「コロナ渦以降の不安定な社会状況では、デジタルの力がないと競争に勝てないことが浸透しつつあります。これまで標準化と効率化のツールだったERPが、今後は新たな価値を創造するプラットフォームになっていくでしょう」(羽田氏)
* * *
海外からもたらされる“新しい経営技術”を導入する日本企業は多い。一方で、そうした経営技術が本当に自社を強くできるものなのかは一考の余地があるだろう。もし、自社の経営に課題を感じているのであれば、まずは今一度、自社の強みに立ち返ってみると良いかもしれない。