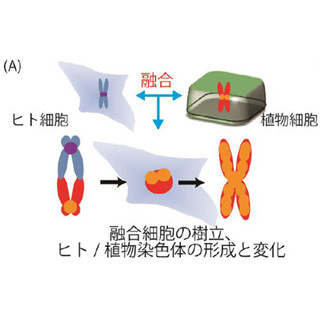京都府立医科大(京府医大)と東京医科歯科大学(TMDU)の両者は3月10日、イメージングフローサイトメトリー法とマルチプレックスFISH法を応用し、造血器悪性腫瘍「多発性骨髄腫」における複数の染色体転座を同時かつ迅速に検出できる新規診断法「ISM-FISH法」を開発したことを共同で発表した。
同成果は、京府医大大学院 医学研究科 血液内科学の塚本拓助教、同・黒田純也教授、TMDU リサーチコアセンターの稲澤譲治センター長兼特任教授(京府医大大学院 医学研究科 血液内科学 客員教授兼任)に加え、シスメックス、ビー・エム・エルの研究者も参加した共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のヒト遺伝学に関する全般を扱う学術誌「Journal of Human Genetics」に掲載された。
多発性骨髄腫は、骨髄中にある免疫担当細胞の一種「形質細胞」ががん化して増殖する疾患で、多数の遺伝子異常、染色体異常の蓄積により発症・進展するとされる。同疾患の発症初期のイベントとしては、「免疫グロブリン重鎖(IGH)遺伝子関連染色体転座」、または「高二倍体」が関与していると考えられている。IGH関連転座は複数種類の異常があるが、それらは予後因子としての意義だけでなく、適した治療法を選択する上でも重要な指標となるという。
また、これまで多発性骨髄腫の染色体転座診断に用いられてきたFISH法は、1回の検査で単一の染色体異常しか検出できず、個々の転座を評価するためには数百個の細胞を鏡検者が目視で診断する必要があった。こうした熟練と技能を要する煩雑な検査を繰り返すことは日常診療で大きな負担となっており、複数の染色体異常を、同時かつ迅速に検出可能な高精度診断技術の開発が強く求められていたとする。
そこで研究チームは今回、大量の細胞の状態を蛍光染色パターンと細胞の形で迅速に識別可能なイメージングフローサイトメトリー法と、複数の染色体異常を同時に異なる蛍光標識プローブで検討するマルチプレックスFISH法を組み合わせ、多発性骨髄腫の診療において重要な複数のIGH遺伝子関連転座を同時解析できる新たな検査法として、ISM-FISH法を開発したという。
具体的には、多発性骨髄腫由来の細胞株、および同疾患の患者由来の骨髄検体を、「CD138」と呼ばれる多発性骨髄腫に特徴的な表面抗原に対する蛍光標識抗体と、4種類の遺伝子座(IGH、FGFR3、CCND1、MAF遺伝子)を標識する蛍光標識DNAプローブにて処理し、イメージングフローサイトメトリー装置により解析。これにより、1細胞ごとに5種類の蛍光シグナルの解析や、10分間で約1万個もの細胞の解析が可能となったという。