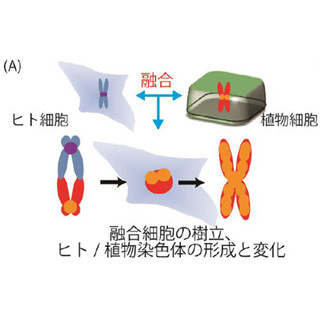患者由来の検体中には、骨髄腫細胞と非腫瘍細胞が混在しているが、ISM-FISH法では、CD138抗原陽性である腫瘍細胞のみを解析画面上で特定する。そして、新規開発の解析アルゴリズムを用いて、IGH遺伝子シグナルの座標と、転座相手のFGFR3、CCND1、MAF遺伝子のシグナルとの距離を算出することで、既定値を満たした場合にのみ「転座陽性」と判定する仕組みだ。
-

(A)ISM-FISHの解析フロー。(B)t(4;14)陽性多発性骨髄腫細胞のISM-FISHの代表的な画像。CD138陽性細胞(同図では骨髄腫細胞の割合は1%)において、二次元座標上の各FISHシグナル間の距離が計算され、規定値を下回る場合に「転座陽性」と判定する仕組みだ(出所:TMDU Webサイト)
これにより、多発性骨髄腫由来細胞株を用いて既知の各染色体転座を正確に検出できただけでなく、患者検体でも従来のFISH法と比較して、陽性適中率96.6%、陰性適中率98.8%という高い精度で診断可能なことが確認された。また、従来FISH法の検出感度は約1%とされるが、ISM-FISH法はその約10倍と考えられるという。
-

患者検体を用いられたISM-FISHの検査精度の検討。融合シグナル陽性細胞数(縦軸)のカットオフ値が図に示されている通りに設定され、ISM-FISH法の結果が判定された。従来、FISH法の結果(横軸)を基準とした陽性的中率は96.6%、陰性的中率は98.8%だった(出所:TMDU Webサイト)
現在、多発性骨髄腫においては新規治療法が続々と開発されている。それ故に、染色体異常などの分子細胞遺伝学的特徴によって、個々の患者に応じて治療法を最適化することが極めて重要だ。しかし、染色体異常の種類の多さ、検査オーダーの煩雑さなどが理由となり、臨床現場では施設ごと、患者ごとに染色体診断の実施法を均てん化することは必ずしも達成できていないとする。
それに対し、ISM-FISH法であれば、一度の検査で重要な3種の染色体異常について同時解析することができるため、より多くの患者に対し、より簡便かつ迅速に染色体異常データを提供できることが期待されるとした。研究チームは今後、同手法が臨床実装可能な診断法として日常的に利用可能となるよう、認可のための取り組み、検査法の標準化を目指した活動を展開していくとしている。
また、悪性リンパ腫などのほかの造血器腫瘍においても染色体異常が病型診断や治療方針決定に重要だが、多発性骨髄腫と同様に多種類の染色体異常が存在するため、これらを同時に解析できるようになることが望まれている。研究チームでは、IGH関連転座以外の染色体異常や、他疾患で認められる染色体異常の診断に応用する可能性も追求しているとした。