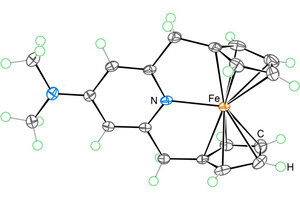TXアントレプレナーパートナーズ(TEP)は2月16日、成長が期待されるシード・アーリー期の技術系スタートアップを選出・表彰するイベント「第7回 J-TECH STARTUP SUMMIT」を開催した。
同イベントの招待講演では、ソニーの100%出資子会社で、米シリコンバレーに拠点を置くTakeoff Point 執行役社長の石川洋人氏が登壇し、ソニーの新規事業から生まれた製品を米国で販売するうえでの失敗談と、そこから得られた気付きを語った。
石川氏は、「売り上げは立たず、会社設立から1年以内に事業閉鎖を検討されるぐらい経営は散々なものだった。しかし、社会の課題やニーズに対して、『なぜ、Takeoff Pointが存在するのか?』を答えられるようになったことで事業が成り立つようになった」と明かした。
「Why」を通じて、社会に対してベストなことを考える
Takeoff Pointは2015年に、日本で生まれたソニーの新規事業を米国で展開するための販売会社として設立された。最初に扱った製品は、IoTブロックを使ってプログラミングやシステム構築を体験できる「MESH」だ。
製品販売のために同社はECサイトを立ち上げたり、教師向けのデモイベントを開いたりした。だが、米国では当時からすでにプログラミング教育の普及率が高く、競合商品が乱立していたこともあり、自社そのものや事業内容、プロダクトに対して関心を持ってもらえなかったという。
事業が成り立っていない中、同社は現地から撤退するか、新しい事業を作るかの選択を迫られた。石川氏はさまざまな起業家や投資家との面談で、「なぜ、自社の事業がうまくいかないのか?」と率直に質問していき、失敗の原因分析をした。
「必ず聞かれたのが、Whyから始まる質問だ。『なぜ、Takeoff Pointはその事業をするの?』と聞かれるが、答えられなかった。会社の辞令で社長をやっている私は、『会社から任されたミッションだから』と内心思っていた。だが、そうした質問に答えられない限り、経営や事業づくりはできないのではないかと考えた」と石川氏。
石川氏は同社のメンバーと話し合い、「撤退するにしても、どうせならやりたいことをやってからにしよう」と奮起。それまでの営業活動で気になっていた、「米国の学校に子供がいない」状況の改善に乗り出した。具体的には、さまざまな理由で学ぶことからドロップアウトしてしまい、教育や職業訓練を受けていない若年層(Disconnected Youth、ディスコネクティッド・ユース)の社会復帰を支援するため、MESHを利用したプログラミングの教育プログラムを無償で提供し始めたのだ。
営業相手だった学校の教員たちも、同社からの「ディスコネクティッド・ユースを減らすのに協力してほしい」という誘いには関心を示し、協力したそうだ。夏休み中の教師やリタイアした元教育関係者などと協力して教材を開発。プログラミングを体験する授業を開いたり、教師向けのトレーニングを行って公認インストラクターを増やしたりもした。
「そうした、社会とMESHが交わる仕組みを作っていったら、偶然ある下院議員から表彰を受け、記事にも取り上げられたことで活動が広まっていった。売り上げにつながらなくてもいいと始めてみたボランティアだが、MESHが無いと成り立たないため、段々とMESHも売れていき、ビジネスとして成り立つようになっていった」(石川氏)
米国で自社を売り込んでいく中で、石川氏はまず、「どんな会社で、何の事業をしているか?」を商談相手から聞かれたという。話が盛り上がれば、「どのように事業を成り立たせているか?」と、ビジネスモデルやコストなど具体的な質問が出る。そして、最後には「Why do you do that?(なぜそんな事業をするの?)」と聞かれていたが、これは悪いサインだ。商談相手は怪しんでいたり、サービスの価値に疑問を感じていたりするため、この質問をするという。
「会社に対して何が一番ベストか常に考えて動いてきたが、社会に対してベストなことを考える視点が欠けていたことが、社長として事業を作れなかった原因だった」と石川氏は振り返った。
小さく始めて、世の中に受け入れてもらえるか検証する
現在も同社は、「ディスコネクティッド・ユースを減らす」を事業目的にした社会課題解決事業を継続している。同事業ではこれまで、申請方法が異なる行政支援サービスの情報を統合したデジタルプラットフォームや、現役の大学生によるメンタリングなどを受けられる進学支援の情報提供プラットフォームといった、ソニーの技術を活用した新規プロダクトも開発・提供してきた。
また、事業化されていない特許や技術がフィットする市場を探すリサーチや、市場投入前の実証実験、事業化などの支援を電機・化学メーカー向けに行っているという。
加えて、自社のこれまでの経験を生かして、ソニーの顧客や日米のスタートアップにコンサルティングやテストマーケティング代行、人材育成などを支援する事業も展開している。
「Whyに人は動かされることが多く、そこから事業が進化することを身をもって体感できた。自社にとってのWhyを見つけるには、最初から完璧な計画を組み立てるより、新しい発見に対して柔軟に対応していくほうが重要だと思う」と石川氏。
また、企業として社会課題に働きかけていく際は、独りよがりにならないよう、「小さく初めて、受け入れてもらえるかどうかを検証」してから、本格的に展開したほうが成功しやすいという。
同社は今後、社会との繋がりが途切れてしまった若年層を支援する事業を、日本でも展開する計画だ。手始めに、日本の少年院の職業教育改革を法務省とともに進めていくという。