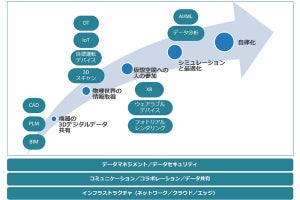日本デジタル空間経済連盟はこのほど、東京都内で「Digital Space Conference 2023」を開催した。同イベントはメタバースをはじめデジタル空間における課題を確認し、今後の展望と理解促進について議論することを目的としたもの。本稿では、KPMGジャパンによるデジタル空間のコミュニティ活用とWeb3時代の経済活動についての講演をレポートする。
メタバースビジネスには日本の強みを生かせ
近年さまざまな場面で活用が期待されるメタバースだが、まずはこのメタバースの特徴を整理しておこう。メタバースとは、多人数が同時に接続可能なインターネット上に構築される仮想の三次元空間で、ユーザーはアバターと呼ばれる分身を操作して他の参加者と交流可能だ。
2024年には7833憶ドルほどの市場規模になるとの試算もあるという。現在の主な収益源は、広告とメタバース内でのデジタルアイテムやリアル商品の売買だ。その他、クリエイターエコノミーやVR(Virtual Reality:仮想現実)デバイスなどのハードウェアなども市場を形成している。
メタバース市場に参加するプレイヤーを見ると、メタバースを利用する直接的なステークホルダーと、メタバースの構築を支援する間接的なステークホルダーが存在する。前者は消費者やサービス提供者、アプリケーションのプラットフォーマーなどだ。一方、後者にはIPホルダー、デバイスメーカー、インフラプラットフォーマーらが属する。
講演の中で、KPMGジャパンのシニアマネージャーである岩田理史氏はメタバースの普及に対する課題として、「ハードウェアの普及と進化」と「メタバースならではの体験価値の提供」の2点を挙げた。
VRゴーグルなどのハードウェアが使いやすく進化して体験価値を向上させるには課題があり、まだ時間がかかる。また、価格面などからもデバイスをパーソナルに所有するには依然としてハードルが高い。
メタバースならではの体験価値については、高解像度な体験ならではのメリットを打ち出す必要があるそうだ。現在のところ、高解像度ならではのメタバース活用で成功している領域はゲームのみとしている。
メタバースのビジネス活用について考えると、現在のところコンテンツを販売するビジネスモデルはゲームやライブエンターテイメント企業が主戦場だ。今後は、メタバースをわざわざ使ってまで「誰に」「どのような」価値を提供し収益化するのか、具体的なユースケースの登場が待たれる。
ここで、岩田理史氏は「メタバース領域で日本の強みを打ち出していくためには、メタバースでコアとなるコンテンツを制作するクリエイターエコノミーの創出が重要」だと述べた。
メタバース領域で発揮し得る日本の強みとは、ゲームなどメタバースになじみのある文化、コンテンツを生み出すクリエイティビティ人材の豊富さ、漫画やアニメなどのコンテンツIPの多さだ。二次創作以降のn次創作を促して、クリエイターエコノミーを創出するのが良いそうだ。また、異なるメタバース間をまたぐアイテム利用のニーズについて、技術面とビジネス面の両面から検討を進める必要があるとしている。
なぜメタバースでファンコミュニティを盛り上げるべきなのか
岩田理史氏は今後のメタバース活用について、コミュニティの活用が重要だと強調した。なぜ、コミュニティが今後のメタバースビジネスに重要なのだろうか。今後のメタバース活用の鍵となるZ世代(10代~20代前半)の消費行動から振り返ると、それがわかる。
Z世代が主に利用するメディアはテレビや新聞などの従来型メディアから、動画共有サービスやSNS(Social Networking Service)などインターネットへと移っている。また、これらのサービス内ではインフルエンサーなどを中心としたコミュニティを形成する傾向が見られる。
こうしたZ世代の特徴を考えると、購買行動は従来のマス広告で主流のモデルだったAIDA(Attention:注意、Interest:興味関心、Desire:欲求、Action:行動の4段階を経る購買行動モデル)から、5A理論(認知:Aware、訴求:Appeal、調査:Ask、行動:Act、奨励:Advocateの5段階を経る購買行動モデル)へと移行している。
企業と消費者の間には新たにインフルエンサーなどコミュニティリーダーが登場した。Z世代はブランドとのタッチポイントがインターネット上となっており、コミュニティの影響を受けて態度変容が惹起され、最終的には自らも推奨者となってSNSなどを通じて他者へと影響を与える。
そのため、これまでのように顧客維持率や再購入率で顧客ロイヤルティを見るのではなく、推奨者の数を指標とするのが望ましいそうだ。
さて、メタバースの活用に話を戻そう。地理的・時間的な制限を超越できるメタバースでは、そこに集まるユーザーがコミュニティを形成しやすい特徴がある。実際に、メタバースコミュニティを活用したマーケティングには成功事例も多いそうだ。
例えば、多くの自動車会社では、自社の自動車を試乗できる仮想空間を構築してアバター同士で試乗できるなどドライブの楽しさを打ち出している。仮想空間内で仲間と一緒にドライブを楽しんだ経験がリアルな世界での購入につながった事例もあるそうだ。
しかし、メタバースのコミュニティを活用したマーケティングは、多くの場合、ワンショットでの活用にとどまっているのが現状であり、コミュニティに対する継続的なコンテンツ提供が今後の課題となっている。
ブロックチェーン技術を利用してデータを分散型で管理するWeb3では、公平なインセンティブを付与する観点でもコミュニティの形成と相性が良い。NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)は会員権や限定コンテンツなどロイヤルティプログラムに活用できるほか、DAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自立組織)はトークンを用いた資金調達やコミュニティへの貢献度に応じた経済的インセンティブの付与も可能だ。
岩田理史氏は「将来的にはメタバース空間のみでコミュニティが完結するだろう」と予測する。ファンコミュニティを形成するために、コアなファンを育てながらライトファンを呼び込む施策が必要だそうだ。
コミュニティを拡大するためには、ロイヤルティプログラムや経済インセンティブを付与する仕組みが重要となる。さらに、コミュニティを継続するために定期的なコンテンツのアップデートも重要だ。
そうした意味でも、今後のメタバースのビジネス活用においては、コンテンツ力やコミュニティマネジメントのノウハウを持つゲーム業界が引き続き一歩リードするだろう。非コンテンツ企業からも既存の活用事例を打破する施策の登場が待たれる。