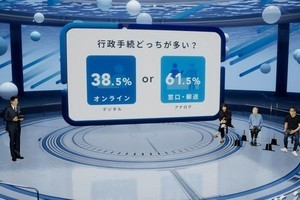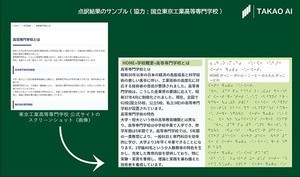電子書籍取次国内最大手のメディアドゥが提供している、視覚障害者向けの電子図書館サービス「アクセシブルライブラリー」が日本全国から注目を集めている。
同サービスは、メディアドゥが出版社から預かっている27万以上の電子書籍データのうち、著作権者、出版社から許諾を得たサービスに適したコンテンツを共通プラットフォームで各自治体に提供するもの。視覚障害者限定のサービスで、導入自治体に利用を申し込むと、ID・パスワード・QRコードが記載された利用者IDカードが発行される。カードに記載されているQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、Webサイト上で図書の検索や読書が楽しめるサービスだ。
2022年6月より提供を開始しているアクセシブルライブラリーは12月現在、東京都江戸川区や京都府宇治市、福岡県八女市など全国7区市町に導入されており、小説や趣味・ビジネス実用書など、1万4000点を超えるコンテンツを提供している(順次拡大中)。
また10月2日には、全国から355件の応募があったデジタル庁の「good digital award」において、全9部門中で最も優れた取り組みに贈られる「グランプリ」を受賞。さらに12月21日、日本電子出版協会(JEPA)が主催する「第16回 電子出版アワード2022」で大賞を受賞した。
なぜ、アクセシブルライブラリーはここまで注目されているのか。視聴障害者が抱えている“読書”にまつわる課題とは何か――同事業を担当しているメディアドゥ 出版ソリューション事業本部 出版事業開発推進部 電子図書館推進センター センター長の林剛史氏に話を聞いた。
株式会社メディアドゥ
出版ソリューション事業本部 出版事業開発推進部 電子図書館推進センター センター長 林剛史氏
2012年メディアドゥ入社。広告事業部で自社サイト広告を担当したのち、営業部で新規電子書店運営に従事。その後電子図書館「OverDrive Japan」事業立ち上げに携わり、現在は電子図書館推進センター センター長。
電子図書館サービスとは
メディアドゥが主に手掛けているのは、2200社以上の出版社と150店以上の電子書店の間で電子書籍の流通を支援する「電子書籍流通事業」だ。出版社と電子書店はメディアドゥを経由することで、一社一社と契約する必要がなくなり複雑な商流を簡素化することができる。同事業の2022年2月期の売上高は993億円で、事業全体の約95%を占めている。
流通事業を扱う同社がなぜ、電子図書館事業に挑戦しているのか。林氏はこう説明する。
「ひとつでも多くのコンテンツをひとりでも多くの人へ。弊社のビジョンであるこの一言に尽きます。日進月歩するテクノロジーを使って読書体験をフラットにしていくことは、出版業界やわれわれのような流通事業者が率先して取り組むべきことだと思っています」(林氏)
視覚障害者が抱える読書の課題とは
視覚障害者が図書館で利用できるのは、点字翻訳(点訳)と音声朗読(音訳)による図書がほとんど。しかし、各地の図書館における点訳・音訳ボランティア数には限りがあり、提供できる図書数がなかなか増えず絶対的量は少ないままだ。
「点訳・音訳はボランティアの方々の尽力で成り立っている側面が強く、全国の図書館で点字や音声の図書を共有しきれず点在していることもあって、ジャンルに偏りが出てしまっていることが多いです。例えば、若年層から人気の『異世界モノ』ライトノベルなどは、やはり音声化されにくいですね」と、林氏はリアルな現状を語る。
加えて、厚生労働省によると、2016年時点で国内に約30万人と推計される視覚障害者のうち、日常的に点字を使っているのは全体の約10%。つまり、点字図書では対応できない利用者が多く存在していることになる。
その一方で、2019年6月に「読書バリアフリー法」が施行された。これにより、アクセシブルな書籍、電子書籍などの量的拡充、質の向上を図ることが求められ、国や地方公共団体に対応の責務が発生した。施行から3年以上経過し、電子書籍を扱う電子図書館の数は増えているが、問題は少なくはないという。
まずコストの問題がある。財政が厳しい国や公共団体にとって同法律に対応するコストは大きく、予算が取りにくくなっている。また、「特に出版社にとっても過去作品まで遡って点字に対応させたり、自動音声読み上げに対応させたりするのは時間的にも金銭的にも負担がかかる」(林氏)という。
もう1つがセキュリティの問題だ。出版社や著作権者から同意を得ることが難しいということも、障壁の一部になっている。「出版社や著作権者にとって、テキストデータは命。そのデータがどのように使われるのかが明確でなければなりません」(林氏)
さらに、現状の電子図書館の仕組みでは、視覚障害者が独力でサービスを利用することが難しいとのこと。原因は図書館の利用カードにある。林氏は、「図書館によって利用カードの仕様がバラバラなんです。しかも平らなカードに利用情報が書かれているので、視覚障害者は誰かにお願いしないと、その情報が確認できません。サービスの入口に高い障壁があるのです」と説明した。
関係者すべてが受け入れられる事業構想を
いくつもの課題を抱える視覚障害者の図書館利用。メディアドゥはどのような切り口でこれらの問題を解決しているのだろうか。
「アクセシブルライブラリーは、視覚障害者と公共図書館、著者や出版社などの関係者すべてに受け入れていただけるように事業構想を掲げています」と、林氏は語る。
視覚障害者が独力で利用できるサービスに
視覚障害者に対しては、自動音声読み上げによる書籍を独力で利用できることを重要視しているという。例えば、図書館の利用カード。アクセシブルライブラリーの利用カードは、仕様が統一されており、QRコードを読み込むことでWebサービスとして利用できる仕組みになっている。カード右下に入れられた切り込みを手掛かりにして読み込めば、誰かにお願いして利用番号を確認する必要がないということだ。
-

アクセシブルライブラリーの利用カード。カード右下の切り込み(赤枠)を手掛かりにして読み込む
またWebサービスに関しても、使い勝手を追求している。
「視覚障害者に特化したUIを設計しています。視覚障害者のメンバーとともにサービス開発を行い、常に利用者の立場に立って開発を進めました。Webサイトは一見シンプルすぎるように思うかもしれませんが、スクリーンリーダー(コンピュータの画面読み上げソフトウェア)を使う視覚障害者にとっては理解しやすい構成になっているのです」(林氏)
-

アクセシブルライブラリーのWebサイト
利便性を高めるだけでなく、音声の質にもこだわっている。同サービスは最新の音声合成技術を採用しており、高速再生でもなめらかに自然に聞き取ることが可能。一般の人が目で読むのと同様の速度(1分間に約400~800文字)で本を聞くことができるという。
「視覚障害者の多くは、2~3倍速で自動読み上げ音声を楽しんでいます。そのため、高速の音声であっても高品質を保つ必要があります。不自然にならないために固有名詞や数値の読み上げでは速度を遅くするなど、さまざまな工夫をしています」(林氏)
また、電子書籍は点字図書とは異なり、場所を選ぶことなくどこでも読める。スマートフォン一つあれば、わざわざ図書館に足を運ばなくても本を読むことができる。メディアドゥが有する豊富なコンテンツのおかげで、新刊、既刊、ジャンルを問わず書籍を簡単に手にすることができる。新刊が順次追加されており、利用者は常に新しいコンテンツと出会うことができるサービスになっている。
「実際にアクセシブルライブラリーを導入した図書館に訪れた視覚障害者の方は『この日を待ちわびていた。生きる喜びが増えました』と感謝の言葉を述べてくれました」(林氏)
継続して利用できるサービスに
アクセシブルライブラリーは、利用者が抱える課題解決だけでなく、利用しやすいサービス体系を構築していることで、国・公共図書館が抱えるコスト面の課題解決にもアプローチしている。具体的には、予算措置が取りやすくするために、同サービスは自治体の人口に応じた階層による月額定額制(サブスクリプションモデル)で提供しており、システムの構築費やコンテンツの追加購入費はかからないようにしている。
「また、サービス対象を視覚障害者に限定するといった公共図書館の協力も必要不可欠です。図書館の窓口で視覚障害者であることをしっかりと確認し、サービス提供者の限定を徹底してもらうことが重要です」(林氏)
出版社や著作権者からの理解や協力も欠かせない。このサービスにおいて著作権者や出版社が最も懸念する事項が「著作物が自動読み上げによって意に反して誤読されるなどの、同一性保持についての心配」。電子書籍の音声自動読み上げは、とくに固有名詞などに対して完ぺきではないからだ。
「技術的には完璧な朗読を目的としたファイル制作も可能ですが、複数ファイルの制作や膨大な既刊の再製作をしようとすると膨大なコストがかかってしまいます」(林氏)
そこで、「視覚障害者の多くは完璧な読み上げ機能よりも提供作品の量を望んでいるということをしっかり伝え、各社にご理解いただいている」(林氏)という。加えて、もともと電子出版のためのものとして預かっていた電子書籍ファイルを利用する対価、著作権者との許諾交渉の対価として利用料を分配する仕組みにした。
同社は今後、導入先と提供作品数、協力出版社数を順次拡大していく考え。同時に音声のクオリティのさらなる向上も目指す。例えば、辞書登録機能を活用して、AIが「羽田空港」(はねだくうこう)を「はだくうこう」と読み間違えないようにする。
林氏は最後に、今後の大きな目標を語ってくれた。
「夢のような話に聞こえるかもしれませんが、いつか視覚障害者に『漫画を読む』という体験を届けたいですね。文芸書やビジネス本のような文字データで登録されている電子書籍は対応していますが、漫画は画像データなので自動音声読み上げに対応していません。将来的に漫画のセリフがすべて音声自動読み上げに対応すれば、視覚障害者の読書の幅が一気に広がるはずです」