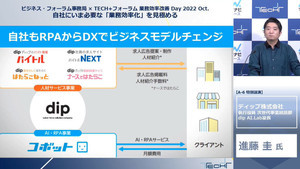ゼネコン大手の大林組は現在、BPR(業務プロセス変革)とBIM生産基盤への完全移行に取り組みながら、業務情報の一元化や領域を横断した情報活用によるデータドリブン経営の拡大を目指している。12月13日、14日に開催された「TECHフォーラム クラウドインフラ Day 2022 Dec. 変革を支えるニューノーマルのITインフラとは」に、同社 常務執行役員 DX本部長の岡野英一郎氏が登壇。「現在(いま)とあるべき未来をDXでつなぐ~大林グループのデータ戦略~」と題し、BPRとBIM(ビルディングインフォメーションモデリング)の活用を中心とする大林組および大林グループのDXへの取り組みについて解説した。
【あわせて読みたい】「TECHフォーラム クラウドインフラ Day 2022 Dec. 変革を支えるニューノーマルのITインフラとは」その他のレポートはこちら
建設事業の基盤強化に向けたDX本部の体制とデジタル戦略
まず岡野氏は、大林組のDX本部について「デジタルICT、BIM、BPRという3つの業務エリアの流れを汲むもの」だと紹介した。その守備範囲は、デジタル戦略立案、DX推進、システム開発統制、ICT基盤整備、施工ICT活用、業務プロセス変革(BPR)、BIM推進全般と多岐にわたり、デジタルに関わるものは全てDX本部が全社最適目線で評価し、実施の是非を協議しているという。ガバナンス体制については、情報子会社であるオーク情報システムと常に連携するかたちをとり、主要部門の部長クラスをDX本部の役職と兼任とさせることで、部門間の横連携と情報共有を図っている。
大林グループの「中期経営計画2022」では、2023年度までの2年間で建設事業の基盤強化に取り組むことが掲げられている。同期間のデジタル戦略は、業務のIT化であるデジタイゼーションと、プロセスのデジタル化を意味するデジタライゼーションに注力するとされている。そして、その後の3年間がデジタルによる企業変革、つまりDXによる変革実践の期間に設定されている。
2024年度から2026年度までの「デジタルによる企業変革」に必要なのが、収益の根幹となる生産DXだ。
「大林グループのデジタル戦略骨子は、大きく、収益の根幹を成す生産DX、生産DXを下支えする 全社的DX(バックオフィスDX)、そして全てのデジタル化とDXを担保する情報セキュリティの強化で構成されています」(岡野氏)
-

デジタル戦略の全体像
データ活用基盤の整備が重要
続いて、大林組が目指すデータドリブン経営に話は移る。岡野氏は、「外部環境の変化を見据えた変曲点を正しく把握し、グループの業績に影響を与えるリスク等への先見的な対応を怠らないことが非常に重要」だと力を込める。大林組は、社内外の情報の可視化と分析、複数の経営シナリオでの検証・示唆のデータが示すFACTに基づき経営判断を行うため、データ活用基盤を整備した。データ活用基盤の整備は、従来のアナログベースの業務プロセスで密結合となっていた多くのシステムを疎結合化でき、データの活用範囲を大幅に拡大できる。実際に、基幹情報として必要なデータは、情報をメタデータとしてリンクすることによりアナログ的な作業が一切不要となっており、これにより効率化、省力化を実現しているという。
「業務に関わる全ての人が同じデータを利用する、SSOT(Single Source of Truth)を実現しています」(岡野氏)
データドリブン経営のための基本となっているデータは、BI・AI技術の併用で有効に活用されている。例えば、原価・売上の分析や予測にBI・AI技術を活用することで、従来ここに使っていたマンパワーを新しい挑戦に向けることができていると岡野氏は説明する。また、こうした取り組みは、データドリブン事業運営にも必須となっていて、人事担当者がタレントマネジメントシステムによって要員配置の最適化を目指し、現場の場所、人員、稼働状況などの総括的な管理を実現するなど、省人化や業務効率化を大いに期待している。