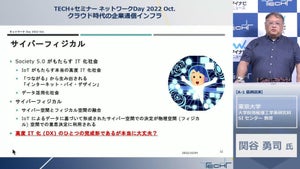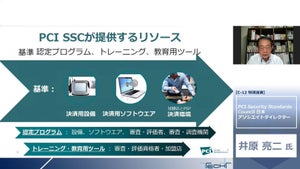東京、大阪など38都府県の事業エリアに約70万台もの自動販売機を稼働させているというコカ・コーラ ボトラーズジャパン。これらの自動販売機はIoTデバイスとしての機能も持ち、同社はここから膨大なデータを取得して活用している。
11月10日、11日に開催された「TECH+ EXPO 2022 Winter for データ活用 戦略的な意思決定を導く」には、同社のトレードマーケティング本部 データサイエンスグループマネージャである松田実法氏が登壇。「70万台の自動販売機から得られるデータをどう活用させたか」と題し、データ基盤をどのように構築したか、実際にどう活用しているのかなどを解説した。
【あわせて読みたい】「TECH+ EXPO 2022 Winter for データ活用 戦略的な意思決定を導く」その他のレポートはこちら
約70万台の自動販売機がIoTデバイスとしてデータを収集
冒頭、松田氏はコカ・コーラ ボトラーズジャパンのビジネスの特徴として、製造から物流、小売り、リサイクルまでをカバーし、自動販売機という日本特有のチャネルを数多く持っていることを挙げた。同社では事業エリアに約70万台の自動販売機を設置しているが、これらはIoTデバイスとしても機能するため、そこから日々膨大なデータを取得している。また、1万台を超える運送トラックからも、データを取得しているという。
同社の事業エリアに設置された自動販売機は、人口カバー率が高い。売上の情報だけでも数億レコード以上を取得していることから、同氏は「自動販売機のデータはまさに宝の山、データサイエンティストはそこからさまざまなことを見い出せる」と語る。ただし、「データ分析を通じてビジネスの意思決定をするためには、まずこれらのデータを分析できるプラットフォームを作ることが肝要である」と強調した。
分析プラットフォームを基幹システムの上の新レイヤーとして構築
松田氏は実際、これらのデータの分析プラットフォームを、基幹システムの上の新レイヤーとして構築したという。その理由としては、分析用データには基幹システムのマスターデータほどの精度は必要ではないこと、基幹システムに手を加えて分析用に変更するには期間とコストが必要となること、基幹システムのデータはそもそも分析用ではないため加工の必要があることの3点が挙げられる。中でも特に「時間がかかると環境も変化するし、ビジネスのアウトプット速度と相反してしまう」(松田氏)ため、スピード感が重要だと力を込めた。
また、データ部門に必要なこととして同氏が挙げたのがスケーラビリティとアジリティだ。これは状況に応じて規模を柔軟に拡大、縮小することと、それを迅速に行うことを指している。データ部門に関わるビジネス要件は日々変わっており、必要なデータも変化しているため、それに追従できるケイパビリティが必要になるためだ。
「PoCで成功したときにすぐロールアウトできる環境を作っておくべきです」(松田氏)
プラットフォーム導入から機械学習モデル構築まで3カ月
このような考えの下、松田氏が目指したのは、スモールスタートで失敗ができる環境づくりだという。データ分析では成功もあるが、もちろん失敗も多い。損失を最小限に抑えてすぐにクロージングできる環境も重要なのだ。「(スモールスタートによって)試行回数が増えれば、成功する可能性も増えるのだから、恐れずに失敗をできる環境づくりを目指した」と同氏は説明する。また、将来的にシステムに手を入れやすくするために、ブラックボックスのような技術的負債を残さない環境をつくることも重要だと付け加えた。
分析・機械学習用のレイヤーを重ねることについては、「これをダブルコストと考えるべきではない。それよりも、ビジネスのアウトプットが遅くなることのほうが問題」だと松田氏は言う。実際に、データ分析と機械学習・AIのプラットフォームを、新レイヤーとして基幹システムに載せた経験では、プラットフォーム導入から初期の機械学習モデルの構築までを、わずか約3カ月で実現したそうだ。