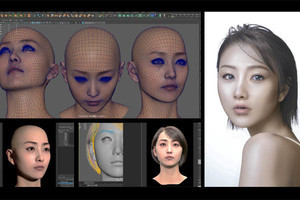「日本史上初! アベマはFIFAワールドカップ2022全64試合無料生中継」ーー次の取材先に遅刻しそうになった筆者は渋谷の井の頭通りを急ぎ足で歩いていたが、インパクトのある屋外広告を見て足が止まった。
スポーツへの興味は皆無に等しい筆者だが、ワールドカップ(W杯)だけは特別だ。ルールを把握しきれていない「にわか勢」ながら、4年に1度だけ訪れる「世界最大のスポーツイベント」にいつも熱狂させられている。
11月20日に開幕するW杯カタール大会は、インターネットテレビ「ABEMA(アベマ)」が全64試合を無料で生中継する。これまではNHKと民放各局が協力して放映権を共同購入してきたが、今大会は高騰する放送権料を理由に民放3局が降りた。1つのメディアがW杯全試合を無料で生中継するのは前代未聞だ。
そこで気になってくるのが、インターネット配信の“質"。国際サッカー連盟(FIFA)によると、前回のW杯ロシア大会では、世界の総人口(4歳以上)の半数以上にあたる約35億7200万人が試合をテレビなどで視聴したという。「1対多」の配信が基本のテレビ放送に対し、ネット配信は「1対1」の通信で利用者をつなぐ。膨大なアクセスの集中は、配信サーバに負担をかけるため、遅延や映像の乱れに直結する。
そこでABEMAは、コンテンツ配信サービス事業などを手がけるアカマイ・テクノロジーズ(アカマイ)とタッグを組み、大規模な同時接続に耐えられる環境の構築を目指している。どのようにして高品質なネット配信を実現させるのか。AbemaTV CTO(最高技術責任者)の西尾亮太氏と、アカマイ シニアプロダクトマネージャーの伊藤崇氏に話を聞いた。
「1対1」のネット配信の難しさ
--テレビ放送とネット配信の技術の違いを教えてください
西尾氏:構成するインフラが根本的に違います。テレビ放送では、映像は各地に建てられた放送用のアンテナから電波によって送信されています。地上波放送なら地域に設置した中継所を、衛星放送なら赤道上空3600キロメートルにある衛星を使って、それぞれの家庭に電波を送ります。
テレビ放送は、視聴者がアンテナを立てれば受信できます。まさに「1対多」の関係となっており、視聴者が増えたとしてもそのインフラ自体にかかる負荷は変わりません。視聴者が100人でも何十万人でも、送信側である放送局の負担に違いはないのです。
-

AbemaTV CTO 西尾亮太氏。2011年株式会社サイバーエージェントに入社。Amebaスマートフォンプラットフォーム基盤、ゲーム向けリアルタイム通信基盤の開発を経て、2016年に「ABEMA」の立ち上げに参画。2018年より株式会社AbemaTV CTOとして現在に至る。
西尾氏:一方でネット配信では、動画はインターネットにつながったサーバによって送信されています。テレビのような「1対多」の関係ではなく、一人ひとりに動画を送信する「1対1」の関係になっています。つまり、視聴者が増えるとそれだけサーバにかかる負荷も増えます。
ネットで同じ動画を大勢の人が見る場合もこの仕組みは同じです。この場合、サーバの負荷も膨大になり、安定して映像を届けること自体が難しくなります。加えて、視聴者のネットワーク環境もさまざまであるため、すべての人に安定して映像を届けることはとても難儀なことになります。
制作側と配信側の努力
--動きの速いスポーツのような中継映像を高画質かつ安定的に配信するための条件を教えてください
西尾氏:条件の1つとして、できるだけ美しい映像コンテンツを生み出す制作側の努力が挙げられます。
ABEMAでは、ネット配信においても地上デジタルテレビ放送、 BSデジタルハイビジョン(2K)放送同等もしくはそれ以上の画質を実現するために検証を重ねています。基礎理論に基づき、テレビと同レベルの画質にするエンコーディングパラメータを3カ月費やして導き出しました。
そしてその目標値に近づけるため、主に2つの検証を繰り返しました。1つはRUM(リアルユーザー監視)です。これは、実際のユーザーがABEMAから配信された映像データを再生した際のパフォーマンスやエラー情報をリアルタイムで収集し分析する手法です。UX(ユーザーエクスペリエンス)を可視化することで、我々のエンコーディング設定に基づいた映像ストリームがどのようにユーザー環境で再生されるかを把握し、結果に基づいて調整を施しています。
もう一つの検証方法はSTM(合成トランザクション監視)です。これはユーザーの行動を模したスクリプトを独自に構成された環境下で実行し、それらのデータを収集・分析する手法です。RUMでの計測ではユーザーの視聴環境下のさまざまなノイズが発生し、正確な分析が行えない側面もあるため、あらかじめ想定した環境下でノイズが含まれにくいデータも収集・分析することでより正確な調整を可能にしています。
サッカーの映像では、動選手の動きやボールの回転、細かい描写が求められます。そういった表現が難しいところの画質を崩さないように設定することも重要ですが、こだわりすぎるとその瞬間に必要になるビットレートが浪費され、ネットワークへの負荷が高くなったり、再生する際のデコード処理の負荷が高くなってしまいます。緻密な計算を重ねて「高画質」と「低負荷」を両立させる均衡点を導き出しました。
伊藤氏:制作側の努力に加えて、コンテンツを最適な映像で送り出すオリジンサーバ側の努力、そしてトラフィックのピークが来ても常に安定した配信を視聴者に届けるCDN(コンテンツデリバリネットワーク)の努力も必要不可欠です。
-

アカマイ シニアプロダクトマネージャー 伊藤崇氏。国内SIerにて、パッケージソフトウェア開発、B2Bシステムの上流工程、アーキテクト、プロジェクトマネジメントを担当。2009年アカマイに入社後、複数の大手Eコマース、メディア企業に対する大規模配信の技術コンサルティング、運用支援に従事。2015年よりプロダクトマネジメントとして、現在は、東アジアエリアにて、アカマイのWeb・動画配信・エッジアプリケーション製品群のマネジメントを担当。各地域での製品ローンチに携わる。
伊藤氏:オリジンサーバとは、オリジナルのコンテンツが存在するWebサーバのこと。そしてCDNとは、大容量のデジタルコンテンツをインターネット上で大量配信するためのネットワークのことです。テレビ放送に例えると、オリジンサーバが放送局、CDNは電波によって視聴者に映像を届ける中継局のような役割をしています。CDNは大量のサーバ(エッジサーバ)と、それにデータをコピーする仕組み、そしてボトルネックなくデータの流すための通信回線がセットになっており、インターネットというインフラを支える重要な役割を担っています。
CDNは大量なエンドユーザーリクエストがあったコンテンツを、エンドユーザーの代表としてオリジンサーバーにリクエストし、返ってきたコンテンツをエンドユーザーに届けます。つまりCDNの存在のおかげで、同じコンテンツに大量のアクセスがあったとしても、オリジンサーバに負荷をかけることなく安定的にコンテンツを配信できているのです。
-

CDNの仕組み
エンドユーザーはスマートフォンやタブレット、テレビ型のデバイスといった多様なデバイスから視聴し、Wi-Fi環境や、利用しているISPなどもさまざまです。アカマイでは、より多くの人に安定的にコンテンツを配信するために、「インターネットにかかる負荷を軽減」しながら配信を行う事を重要視しています。
我々は世界134カ国に4000以上の配信拠点があります。ネットワークに負荷がかかりにくい最適なロケーションやネットワーク経路を選択しており、ABEMAさんのコンテンツの質をできるだけ落とさないよう努力しています。