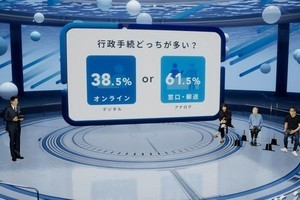視覚障がいがある人が抱える課題を解決する事業アイデアの実証成果を発表する「VISI-ONE アクセラレータープログラム」のデモデイが、10月14日にアトレ竹芝(東京・港区)にて初開催された。
同プログラムは、参天製薬、日本ブラインドサッカー協会、インターナショナル・ブラインドフットボール・ファウンデーション(IBF Foundation)の3者が主催するプログラムで、2022年2月28日より応募を開始し、1次選定と2次選定を経て、6社の企業が採択された。採択企業6社はその後、視覚障がい者のサポートを受けながら、事業アイデアのコンセプト検証やインクルージョンの視点で社会応用が可能かを測る実証実験を行い、10月14日に実証成果を発表した。
そして、参天製薬 執行役員の森田貴宏氏ら6名の審査により、アイデアの独自性や親和性、短期間での成長性と社会実装への実現性を審査基準とする「Business Innovation Award」と、視覚障がいに関する課題への理解および、中長期的な視点からの共生社会の実現性を審査基準とする「Social Innovation Award」の受賞企業を決定した。賞金はそれぞれ300万円だ。
本稿では、「Business Innovation Award」に選ばれたAshirase、「Social Innovation Award」に選ばれたGATARIの発表内容をレポートする。
靴の振動でナビゲーションする「あしらせ」
Ashiraseが発表したのは、靴に挿入するデバイスで行き先を知らせる歩行ナビゲーションシステム「あしらせ」。
同システムは、スマートフォンの専用アプリと器具が連動する。目的地を音声で入力すると、GPS(全地球測位システム)などを利用して経路を検索し、音声ではなく足への振動で道案内をしてくれる。
例えば、靴に装着したデバイスがスマートフォンから信号を受信し、右折なら右足、左折なら左足、直進なら両足の装置が振動し、曲がり角に近づくと振動のテンポが短くなるなどの仕組みだ。「利用者が直感的に単独歩行できるようになることを目指している」と、代表取締役の千野歩氏は説明した。
視覚障がいのある人が単独歩行するとき、残存視覚や耳、手や足の裏などの感覚を駆使して安全を確認しているという。それに加えて、目的地までのルートも確認しなければならない。慣れた道であれば、電柱の数や店の音・匂いなどでルートを確認できるが、新しい道になると、スマホを使ったり人に聞いたりしなければならない。
「あしらせ」は、そのルート確認を無意識化させる機能を持つ。直接的な安全確認の支援はできないが、視覚障がい者の持つ歩行能力を生かし間接的に安全性を底上げする。「靴を履き、スマホで目的地を入力し、振動に沿って歩く。独自の誘導アルゴリズムでほぼスマホを見ずに歩行することができる」(千野氏)
「あしらせ」の便利さは数字にも現れている。同社が弱視者と晴眼者を対象に行った実証実験の結果によると、「あしらせ」を利用することにより、歩行をスタートするまでの時間は約8分の1に短縮した。また、歩行のトータル時間は3分24秒も縮まり、歩晴眼者と58秒しか差がない結果になったという。
同社は2022年度内に一般消費者向けおよび企業向けのサービスの提供開始を目指す。また、空港や鉄道、旅行などの業界と連携した長距離移動向けのレンタルサービスも視野に入れる。具体的には、視覚障がい者が旅行を行う際、事前に「あしらせ」を貸し出すことで、旅先で自由に移動できるようにし、帰還後に返却するといったサービスだ。
「視覚障がいが理由で『自由に旅行することを諦めている』『出張が難しく仕事にも影響がある』といったユーザーが持つ悩みを解決していきたい」(千野氏)
同社は今後も積極的にPoC(概念実証)を実施し、視覚障がい者だけでなく健常者も含めた各企業向けのビジネスを展開していく考えだ。
MR技術で空間体験の質を向上する「Auris」
東京大学発のスタートアップGATARIが発表したのは、MR(複合現実)技術を活用したMR プラットフォーム「Auris(オーリス)」。
2020年9月より提供を開始しているAurisは、事前にアプリに取り込まれた施設のデータを活用し、施設内に入りスマートフォンのカメラを空中にかざすと、自身が空間のどの位置にいるかを高精度で測り、体の向きや対象物からの距離に応じ、あらかじめ空間に配置された音声コンテンツを楽しめるといったプラットフォームだ。
例えば、階段の前の空間を通ると「3メートル先に25段ある階段があります。気を付けて登ってください」といった音声を流すことができる。
代表取締役の竹下俊一氏は「MRは、リアルな空間にセンサーなどを配置する必要がなく、さまざまなプライベート空間を作ることができる技術。一人ひとりに対して、その人のための情報だけを提供できる」と、MRの魅力を説明した。
デジタル空間に付与できる音声コンテンツの数に限りはなく、情報をアップデートすることで、リアル空間の情報とのギャップをなくすことができる。さらに、AR(拡張現実)グラスを前提にしつつ、それに依存しない音声からのアプローチも考えていくとのこと。
同社は都内の複合施設にてMR技術を活用した空間体験の実証実験を行った。利用者からは「音の情報にワクワクしながら探索できた」といった肯定的な意見があった一方で、UIの改善を求める声もあったという。同社は今後、課題抽出とサービス改善を図り、商業施設や公共交通施設などを対象にサービスを展開していく考えだ。
「晴眼者が感じている新しい情報との出会いといった移動自体の付加価値を諦めている、もしくは諦めていることを無意識に受け入れているという課題を解決していきたい」と竹下氏は意気込んでいた。
視覚障がいの壁をテクノロジーで溶かす
受賞したAshirase、GATARI以外の採択企業の発表も、「視覚障がいの壁を溶かすことができるだろう」と感じるものだった。
ITスタートアップのクラスリーは、テキスト原稿を人間に近い精度で読み上げるAI(人工知能)ソフト「Alterly(オルタリー)」を、紛失防止デバイスを手掛けるスタートアップMAMORIOは、視覚障がい者には「ロシアンルーレット」と化している自動販売機の購入を支援するシステムを発表した。
これらのテクノロジーは、視覚障がいの「オフラインの壁」「思いがけない壁」を溶かしうるもので、発表を聞いていた記者は終始感嘆していた。
「現代は目を酷使する時代で、世界で22億もの人が、何かしらの視覚の異常を感じている。これからは、視覚障がいの有無にかかわらず、社会全体が混ざり合うことが大事だ。そして、これはわれわれだけでは解決できない問題。他社との協業やイベントを通じて、この問題を解決していきたい」(森田氏)